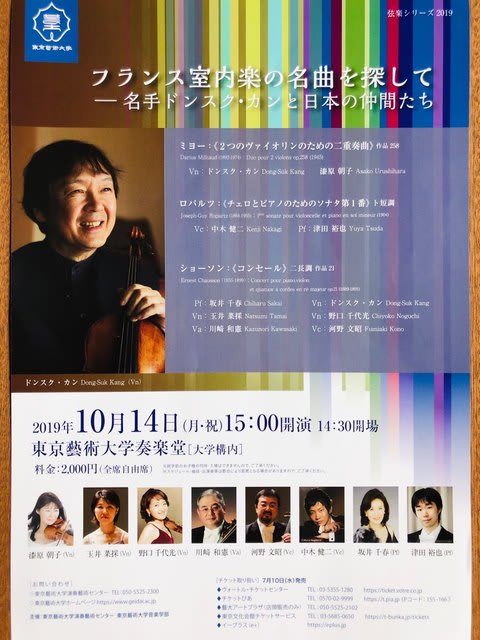21日(月)。わが家に来てから今日で1848日目を迎え、英国議会下院は19日、英国が欧州連合(EU)から離脱する案件を定めた協定案について 採決の先送りを決めたことにより、EUに対して離脱期限の延長を要請することを法的に義務付けられことになるが、ジョンソン首相は「延期の交渉はしない」と述べ、10月末の離脱にこだわる姿勢を変えていない というニュースを見て感想を述べるモコタロです

ジョンソン首相は行政府が立法府より上にあるという考えのようだが どうだろう?





昨日の日経朝刊「The STYLE / Art」面は「ヴァイオリンの神秘(下) 時代を熱狂させた悪魔の超絶技巧」のタイトルのもと、アングルによる「パガニーニの肖像」やドラクロワの「ヴァイオリンを弾くパガニーニ」の絵を紹介しています 記事の中のコラム「KEYWORD」で「f字孔」が解説されていました。超訳すると
記事の中のコラム「KEYWORD」で「f字孔」が解説されていました。超訳すると
「音を楽器の外に響かせるための『f字孔』は、ヴァイオリンのシンボルでもある ドラクロワよりも早い時期に、イタリアに旅してパガニーニの肖像画を描いたドミニク・アングルは、ドラクロワと同じくヴァイオリンを弾く画家。パガニーニと一緒に弾いたこともあるというから、ヴァイオリンに関しても相当な腕達者だったのだろう
ドラクロワよりも早い時期に、イタリアに旅してパガニーニの肖像画を描いたドミニク・アングルは、ドラクロワと同じくヴァイオリンを弾く画家。パガニーニと一緒に弾いたこともあるというから、ヴァイオリンに関しても相当な腕達者だったのだろう 長年多くのヴァイオリンを扱ってきた楽器商の神田侑晃氏は『ストラディヴァリウスを弾くと、その楽器固有の音が出る。グァルネリからは、奏者の音が出る
長年多くのヴァイオリンを扱ってきた楽器商の神田侑晃氏は『ストラディヴァリウスを弾くと、その楽器固有の音が出る。グァルネリからは、奏者の音が出る 』『ストラディヴァリウスとグァルネリではf字孔の大きさが微妙に違い、音の特性に影響している』と言う
』『ストラディヴァリウスとグァルネリではf字孔の大きさが微妙に違い、音の特性に影響している』と言う 」
」
この記事を読んで初めて知ったのは、ドラクロワもアングルも絵画の才能だけでなく、ヴァイオリンを弾く才能も持っていたということ そして、同じ名器でもストラディヴァリウスとグァルネリとでは音の特性が違うということです
そして、同じ名器でもストラディヴァリウスとグァルネリとでは音の特性が違うということです 問題は聴く側のわれわれにそれを聴き分けられる能力があるかどうかです
問題は聴く側のわれわれにそれを聴き分けられる能力があるかどうかです





昨日、上野の東京藝大奏楽堂で東京藝大「クラーラ・シューマン生誕200年に寄せて」プロジェクトの第3回「オルガンが奏でる愛と告別の調べ~クラーラとローベルト、ブラームスらの書簡と共に」を聴きました
プログラムと演奏者は次のとおりです
①ローベルト・シューマン「ペダル・フリューゲルのための4つのスケッチ」より第2曲「速すぎず、とてもはっきりと」(オルガン:近藤岳)
②クラーラ・シューマン「3つの前奏曲とフーガ」より第2曲 変ロ長調(オルガン:廣江理枝)
③ローベルト・シューマン「ペダル・フリューゲルのためのカノン形式のエチュード」より第1曲 ハ長調、第5曲 ロ短調(オルガン:徳岡めぐみ)
④クラーラ・シューマン「3つの前奏曲とフーガ」より第3曲ニ短調(オルガン:近藤岳)
⑤ローベルト・シューマン「バッハの名による6つのフーガ」より第6曲「中庸に、少しずつ速くなって」(オルガン:廣江理枝)
⑥同「森の情景」より第7曲「予言の鳥」(オルガン:近藤岳)
⑦ブラームス「フーガ 変イ短調」(オルガン:廣江理枝)
《 休 憩 》
⑧同「前奏曲とフーガ ト短調」(オルガン:近藤岳)
⑨クラーラ・シューマン「3つの前奏曲とフーガ」より第1曲 ト短調(オルガン:廣江理枝)
⑩Th.キルヒナー「オルガンのための13の小品集」より第2曲「前奏曲」、第12曲「叙情的一葉」(オルガン:徳岡めぐみ)
⑪ブラームス「4つの厳粛な歌」より第3曲「おお死よ、お前はなんと苦痛なのか」(オルガン:同)
⑫同「11のコラール前奏曲」より第10曲「わが心の切なる思い」、第11曲「おお世よ、われ汝を去らねばならない」(バリトン:萩原潤、オルガン:徳岡めぐみ)
⑬ローベルト・シューマン:オラトリオ「楽園とぺーリ」より第17曲「さあ安らかに眠れ、豊かな香りを夢見て」(ソプラノ:平松英子、バリトン:萩原潤、オルガン:廣江理枝)
プログラムの前半はクラーラとローベルトの結婚から始まり ローベルトの死までが、後半ではキルヒナーとの淡い恋、ブラームスによる死の予兆と告別が、彼らのオルガン曲と声楽曲を通して描かれます
なお手紙や書簡の朗読は川中子みのり(東京藝大大学院修士課程3年在籍)、瀬戸口 郁(文学座・俳優)です

全席自由です。1階17列25番、右ブロック左通路側を押さえました
2階正面のオルガン席で3人のオルガニスト(廣江理枝、徳岡めぐみ、近藤岳)が交代して演奏し、1階のステージにシューマン夫妻やブラームスの手紙や書簡を朗読する2人のナレーター(川中子みのり、瀬戸口 郁)がスタンバイします
全体の流れとしては、最初にナレーターにスポットライトが当てられ、手紙・書簡を読み上げ、次いでオルガニストにスポットライトが当てられて演奏を始める 演奏が終わるとオルガニストが交代し、次の手紙・書簡が読み上げられ、演奏を始める・・・という形で進行していきます
演奏が終わるとオルガニストが交代し、次の手紙・書簡が読み上げられ、演奏を始める・・・という形で進行していきます この間、1階正面の巨大スクリーンには演奏曲名とオルガニスト名、そしてクラーラやローベルト、ブラームスの顔写真や楽譜などが映し出されます
この間、1階正面の巨大スクリーンには演奏曲名とオルガニスト名、そしてクラーラやローベルト、ブラームスの顔写真や楽譜などが映し出されます これら一連の流れの中で 会場からの拍手はありません
これら一連の流れの中で 会場からの拍手はありません この演出は演奏者と聴衆の集中力を維持する上でとても有効だったと思います
この演出は演奏者と聴衆の集中力を維持する上でとても有効だったと思います

この企画の主人公クラーラ・シューマン(1819-1896)は、1828年に9歳でデビューし、1891年3月に71歳で公の舞台から降りました その間、1300回を超えるコンサートで活動し、1878年から1892年まで音楽院え後進の育成に当たっています
その間、1300回を超えるコンサートで活動し、1878年から1892年まで音楽院え後進の育成に当たっています まさに当時のスーパーレディでした
まさに当時のスーパーレディでした
この日の一連のオルガン曲を聴いて思ったのは、当たり前のことですが、バッハのオルガン曲とはまったく別物だということです 簡単に言えば、バッハのオルガン曲が「キリスト教という宗教」と切り離せないのに対し、シューマン夫妻やブラームスのオルガン曲は必ずしもそうではなく、強いて言えば「芸術としての作品」だと思われることです
簡単に言えば、バッハのオルガン曲が「キリスト教という宗教」と切り離せないのに対し、シューマン夫妻やブラームスのオルガン曲は必ずしもそうではなく、強いて言えば「芸術としての作品」だと思われることです バッハ・コレギウム・ジャパンのコンサートの時にバッハのオルガン曲を聴くと、必ずと言ってよいほど「俄かクリスチャン」になったように感じますが、この日演奏されたロマン派のオルガン曲を聴いてもそういう気持ちにはなりませんでした
バッハ・コレギウム・ジャパンのコンサートの時にバッハのオルガン曲を聴くと、必ずと言ってよいほど「俄かクリスチャン」になったように感じますが、この日演奏されたロマン派のオルガン曲を聴いてもそういう気持ちにはなりませんでした
オルガニストは3人とも素晴らしい演奏でしたし、ナレーターの2人も声に演技力があり申し分ありませんでした 何より全体の企画・演出が優れていると思いました
何より全体の企画・演出が優れていると思いました














 後者は幹事のせいではなく、親の介護等 家庭の事情があるためだと思います
後者は幹事のせいではなく、親の介護等 家庭の事情があるためだと思います 私のすぐ前に座ったMM君は会社務めのあと地元・所沢でロック酒場「ひょっとこ」を開いてビートルズを流しているのですが、地域開発の関係で立ち退きとなり11月に場所を移して新規開店するとのことでした
私のすぐ前に座ったMM君は会社務めのあと地元・所沢でロック酒場「ひょっとこ」を開いてビートルズを流しているのですが、地域開発の関係で立ち退きとなり11月に場所を移して新規開店するとのことでした 是非お祝いに駆け付けようと思っています
是非お祝いに駆け付けようと思っています
 当時は「ベトナム戦争」が行われており、北ベトナムが「南ベトナム民族解放戦線=べトコン」を結成してアメリカに対し徹底抗戦している時期でした
当時は「ベトナム戦争」が行われており、北ベトナムが「南ベトナム民族解放戦線=べトコン」を結成してアメリカに対し徹底抗戦している時期でした 秋の「文化祭」で仮装行列をすることになり、3年2組は私の提案でベトコンに対抗して「日本民族解放戦線=JAPACON(ジャパコン)」を結成することになったのです
秋の「文化祭」で仮装行列をすることになり、3年2組は私の提案でベトコンに対抗して「日本民族解放戦線=JAPACON(ジャパコン)」を結成することになったのです 私はヘルメットに角棒という全学連スタイルでしたが、クラスメイトは男子も女子も各自好きなような仮装や化粧をして「JAPACON」の横断幕や「ベトナム戦争反対!」のプラカードを掲げて校庭を練り歩きました
私はヘルメットに角棒という全学連スタイルでしたが、クラスメイトは男子も女子も各自好きなような仮装や化粧をして「JAPACON」の横断幕や「ベトナム戦争反対!」のプラカードを掲げて校庭を練り歩きました 」と担任のY先生には相当心配をかけたようです
」と担任のY先生には相当心配をかけたようです 幹事のMM君をはじめ参加の皆さんお疲れさまでした
幹事のMM君をはじめ参加の皆さんお疲れさまでした 次はいつになるのか分かりませんが、少なくともこの日参加した7人は来てほしいと思います
次はいつになるのか分かりませんが、少なくともこの日参加した7人は来てほしいと思います
 このコンサートには毎年通っていますが、全国から終結したプロ集団(コンマス=読響・小森谷巧)による演奏は感動ものです
このコンサートには毎年通っていますが、全国から終結したプロ集団(コンマス=読響・小森谷巧)による演奏は感動ものです



 すると、今度は後ろの車からぶつけられ、車のクーラーが効かないから子供だけでも乗せてくれと頼まれ 幼稚園児2人が乗り込んでくる
すると、今度は後ろの車からぶつけられ、車のクーラーが効かないから子供だけでも乗せてくれと頼まれ 幼稚園児2人が乗り込んでくる こうして狭い車内がギュウギュウ詰めになっていく中、後ろの車が急に割り込んできて
こうして狭い車内がギュウギュウ詰めになっていく中、後ろの車が急に割り込んできて さて、最後に徳夫はどうなるのでしょうか・・・・というクライム・エンターテインメントです
さて、最後に徳夫はどうなるのでしょうか・・・・というクライム・エンターテインメントです 午前中に整骨院で腱鞘炎の手当てをしてもらい、家に帰ってパソコンのスイッチを入れてみたら、インターネットが使えません
午前中に整骨院で腱鞘炎の手当てをしてもらい、家に帰ってパソコンのスイッチを入れてみたら、インターネットが使えません そんなはずはない、と電源を一旦落としてスイッチを入れ直したり いろいろ試してみたのですが、ダメでした
そんなはずはない、と電源を一旦落としてスイッチを入れ直したり いろいろ試してみたのですが、ダメでした ラチが明かないので、もう一度部屋に戻って、すべてのパソコン機材の電源やコードを抜いて、最初から組み立て直してスイッチを入れると、やっと繋がりました
ラチが明かないので、もう一度部屋に戻って、すべてのパソコン機材の電源やコードを抜いて、最初から組み立て直してスイッチを入れると、やっと繋がりました あと1年は だましだまし使おうと思っています。何とか耐えてくれよ、と祈るばかりです
あと1年は だましだまし使おうと思っています。何とか耐えてくれよ、と祈るばかりです












 「黒人用旅行ガイドブック=グリーンブック」を頼りに人種差別の色濃い南部へのツアーに出発する
「黒人用旅行ガイドブック=グリーンブック」を頼りに人種差別の色濃い南部へのツアーに出発する

 そこに1台のピアノがあるのを見つけたトニーに促され、シャーリーは静かにピアノを弾き始めます
そこに1台のピアノがあるのを見つけたトニーに促され、シャーリーは静かにピアノを弾き始めます 二人はツアーを通して、ぶつかり合いながらも、お互いに理解し合い、尊厳を尊重する姿を見ると、爽快な気持ちになります
二人はツアーを通して、ぶつかり合いながらも、お互いに理解し合い、尊厳を尊重する姿を見ると、爽快な気持ちになります




 この曲はアントン・ブルックナー(1824-1896)が1881年から1883年にかけて作曲、ライプツィヒでアルトゥール・二キシュの指揮により初演され、バイエルン国王ルートヴィヒ2世に献呈されました
この曲はアントン・ブルックナー(1824-1896)が1881年から1883年にかけて作曲、ライプツィヒでアルトゥール・二キシュの指揮により初演され、バイエルン国王ルートヴィヒ2世に献呈されました を受け取ると、オケが「ハーピーバースディーソング
を受け取ると、オケが「ハーピーバースディーソング 」を演奏し、会場は祝祭的な雰囲気に包まれました
」を演奏し、会場は祝祭的な雰囲気に包まれました 」と厳命されてしまいました
」と厳命されてしまいました