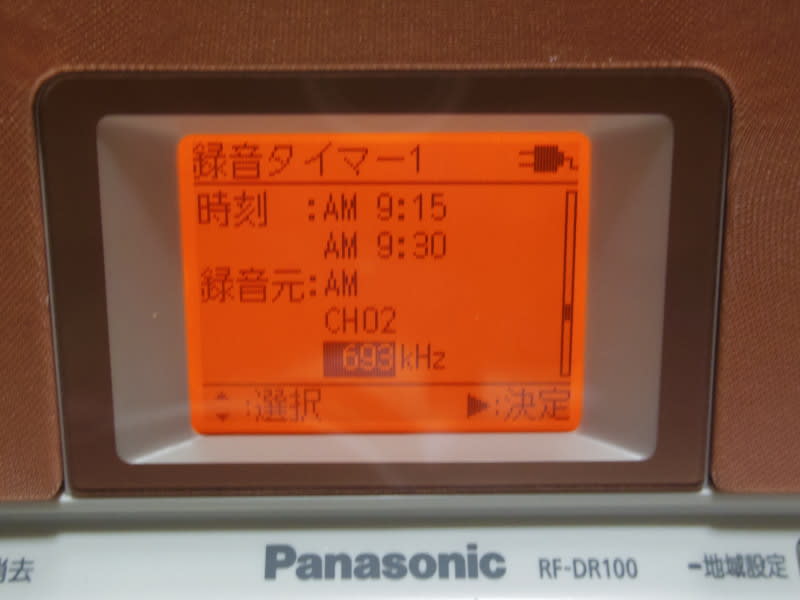ボルボが普通のエンジン付きの車の販売を順次やめていきます、と宣言したり、フランスが2040年までにガソリン車を禁止する?と宣言したりと、自動車界の動力革命はここに来て一気に加速する様子を見せてきた。
ボルボはハイブリッドなどエンジン付きの車は継続するというし、トヨタなどでもしばらくはハイブリッドを中心に製品展開していくものと思われるが、他方新規メーカーのEV参入も増えてきそうだ。EVは従来とは業界とのつながりからして違うのだそうで、日本メーカーの優位性が失われパソコンや家電と同じ道をたどるのではないかと、テレビの経済番組などでは懸念している。

何度か書いたと思うけど、僕は20代のころ、かなり熱心に車に乗っていた時期があったが、その後20年以上にわたりほとんど運転しない時期が続いた(とはいっても、年に数回程度は運転していたが)。その間に自動車も、世の中が変わったのと同じように大きく変わった。
過去に色々な知識を持っていた分、「常識」が変わったことに対し驚いたり、違和感を感じるとも、運転を再開してからしばらくは多かった。

車といえば4ドアセダンが普通だったのが、すっかり様変わりしたのは、やはりいちばんの驚きだ。迷ったらとりあえずセダンを買う、という常識が通用しなくなった。
ふつうのセダンはフォーマルすぎると、屋根を低くしたモデル(4ドアHT)に人気が集まって、中にはかなり窮屈なモデルもあったのだが、そういう車はカッコいいとされていた。
それが今はそそり立つようなミニバンが人気なのだから、変われば変わるものだ。

この、トヨタ アクアは、わりと昔のセダン風に低いポジションに座る設計で、僕なんかにはとても空間的に落ち着く。

全長4mそこそこの小型車なのだが、その割には室内は広々としている。
日産ノートなど、外観からは信じられないくらい車内が広くて、なんとなく不安になるほど?だ。あの車を見ていると、セダンが少数派になった理由がわかる気がする。
そういえば、昔は4ドア+ハッチゲートというモデルは人気がなかったね。シビックもファミリアも、一番人気は3ドア、次が4ドアセダンだった。3ドアはクーペと共に姿を消してしまった。
なぜ、プレリュードみたいなパーソナルクーペがなくなってしまったのか、不思議といえば不思議だ。

表向きは(!?)進歩した現代の車に関心を示したりしているが、本音の部分というか、もし昔の車がごく普通に手に入るなら、そっちのほうにより惹かれるものを感じる。。
写真のような車はちょっと古すぎるが、’80年代半ばから90年代前半ぐらいの車なら、別に何の気構えもなくふつうに乗れるはずだ。
なのだが、どうも中古市場などでは、そうした時代の車はあまり残っていないらしい。
むしろ、60年代のスバルとかブルーバード、箱スカなどのほうが、たくさん残っているようだ。
あれほどたくさん見かけたファミリアとか、リトラクタブルライトのアコードとか、検索してもほとんど引っかからない。プレリュードも2,3代目は見かけない。3代目なんて、人気あったのにねえ。。ただ、走り屋さんは乗らなかったというのはあるな。多少どてっとした運転感覚があれだったけど、あまり気負わずに乗れるし、普通に荷物は積めるし、一応4人は乗れるし、ダメなんですかねえ、今は。。この車見てから、最近の車見ると、やっぱりため息が出てしまう。。
別にEVでも3Dプリンタで作ってでもいいから、どこかで復刻してくれないかしら。。












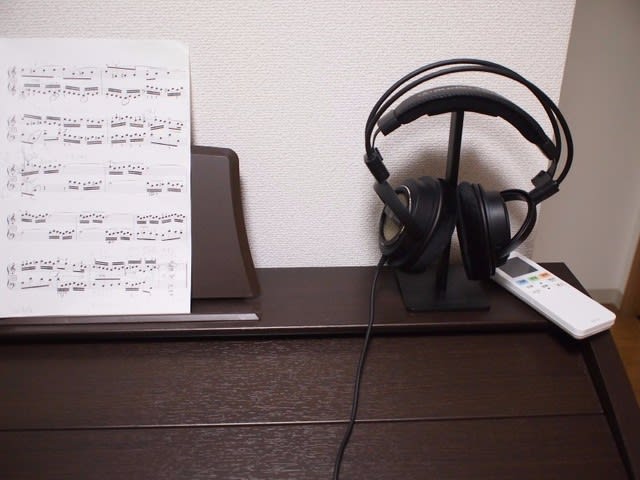

















 すみません、番号だけ残しました。。
すみません、番号だけ残しました。。