自動車評論家の特大時有恒氏が亡くなったので、家にある氏の著作を取り出してみた

僕が徳大寺氏の名前を初めて知ったのは30年ほど前のことだ。ちょうど車に興味を持ち始めた頃で、後で書くが代表著作である「間違いだらけのクルマ選び」の84年版を、地元の本屋さんで立ち読みし、面白くなってそのままレジに走ったのが最初。ほどなくして、「ベストカーガイド(現ベストカー)」誌に連載があるのを知って、時折買っては読んでいた。この連載「俺と疾れ!」は同誌の最新号まで連載されている。
同じ頃、創刊間もない「NAVI」誌に、同誌編集長だった大川悠氏、舘内端氏と共に時の新車や、特集された話題を対談形式で論ずるという、NAVI TALKが連載されているのを知った。当時よく使っていた池袋の芳林堂書店で、モデルチェンジされた日産の上級小型車、ローレル(C32型)をこき下ろしていたのを立ち読みして、う~ん、きついなあ、と思って、買うのをやめた(^^;のを覚えている。最初に買った「NAVI」は、翌年3月、ホンダ・クイントインテグラの評論が掲載された号からだ。
「NAVI」からはそれこそいろいろなことを学んだ。当時同じ二玄社から発売されていた「CAR GRAPHIC」と比べると、その編集姿勢はより柔軟で、自動車そのものと言うよりは、自動車のある生活や、自動車ファンの生き方、みたいなテーマを取り上げることも多かった(ハードのCG、ソフトのNAVIと言われていた)。上に掲げた写真でいうと、「ああ、人生グランドツーリング」などは、その頃の「NAVI」に掲載されていた記事を集めたものだ。
「クルマが好きで・・軽エンスーのBMWストーリー」というのは、都内に住む広告代理店勤務の若いサラリーマンが、当時モデルチェンジされて好評だったBMW525iを購入したという、徳大寺氏のストーリーテリングだ。名門校出で名のある広告代理店勤務、親にマンションを買ってもらって、そこそこの生活を送っている・・という、バブル時代によくあった設定の若夫婦が、今はやりのクルマを買う、というお話だ。このシリーズは面白くて、今でも最初に読んだときのことを良く覚えいている。
「金、余りて お父さんのベンツ・ストーリー」、これは神田の製版工場を畳んで、大金を手にしたお父さんが、これまた当時好評だったミディアム・メルセデス230Eを買おうと思い立ち、ベテランセールスマンにおだてられてのぼせたり、買った「ベンツ」で勇躍ゴルフに行ったりする、という話。おそらくは徳大寺氏と同世代の「オトーサン」を念頭に置きながら、当時の時代性を取り入れつつ語ったと思われるこの話、ほとんど「小沢昭一的こころ」みたいな世界だが、氏の同時代人に対する愛情が感じられる、すてきなストーリーだ。
「ダンディ・トーク」シリーズは、自動車の話と言うよりは、徳大寺氏の人生観などを織り交ぜたエッセイ集だ。本文中で否定はしているが、きざと言えばかなりきざな文章で、徳大寺氏の名調子全開という感じの作風だ。
引用したい文章はたくさんあるが、ここでそれを取り上げていると長くなりすぎる。ただ、以下のふたつだけは取り上げておきたい。
日常生活の中で、絶対声高に使ってはいけない言葉がある。
「ロマン」とか、「幸福」とかいう言葉だ。あるいは「文化」とか、「芸術」なんて言う言葉もそうだ(中略)。
なぜか?
恥ずかしいではないか。
これが、「恥ずかしい」という感覚につながらない人は、もうこの話を読む必要はない。わかる人にはすぐわかるだけの話だ(中略)。
世の中には、それを持ち出せば相手に反論の余地を与えない言葉というものがある。
たとえば、「平和」とか「反核」、あるいは「環境保護」などという言葉もそうだろう。もし、こういう言葉に「反対」を唱えたりすれば、それこそ「なぜだ?」と目をむきだしてくってかかる人たちの避難と軽蔑の視線に耐えながら、汗を飛ばしながら必死で議論するしかなくなるだろう。そして、おそらく一晩かかって話しても、結局は危険思想の持ち主とか、自覚にないエゴイストなどという烙印を押されたまま見捨てられてしまうに違いない。
(ダンディ・トークⅡ ソアラにロマンはあるか?イカロスの飛翔と墜落)
絶対的な価値を示す言葉には、大概は時代のイデオロギーを代弁していることが多い。「文化」、「ロマン」、「幸福」なども、結局は時代のイデオロギーだと思う、と言う。
こうした、絶対的な価値を示す言葉を傲然と口にする人々は、自分の価値観につゆほどの疑いを持たず、他の意見を決して許そうとしない。こうした人々の神経を、徳大寺氏は好きになれない、という。
ただ、氏は「ロマン」という言葉には自分も思い入れがあり、ここぞと言うときには使いたいのだが、と続けている。要するに、軽々しく絶対的な言葉を使うな、大人ならそうした言葉の持つ、エゴイスティックな側面を知った上で使え、ということだ。
これなど、今の日本の言論界にはものすごおく、大事なことだと思う。
健康についても決して無関心じゃないが、必ずしも長寿である必要はないと思っている。大切なことはいつお迎えが来ても”俺には○○年のすばらしい人生があった"といえることだから。
だから、ことさら健康に悪いことをしようとは思っていないが、しかし、快楽は多くの場合、長寿とは反することが多い。タバコ、酒(こいつは多くはしない)、夜更かし、女、大食い、こいつらと無縁じゃない。
かくて、私はこれからもかくのごとくノーテンキで、いつまでだかわからぬが生き続けるだろうと思う。
(ダンディ・トークあとがき 「キリギリスの心意気」)
氏がこれを執筆されたのは25年前だが、なくなる前に徳大寺氏は、自らの人生をはたしてどう振り返っておられただろう。僕などが思うに、実に見事な人生を生ききった方のように感じられるが・・。
男と女の話など、本当に面白いお話もたくさん書かれているが、別の機会に譲る。
15年ほど前に出た「ぶ男に生まれて」は、「ダンディ・・」とは全く違う文体の佳作だが、何処かに行ってしまって見つからない。書店でももうないんだろうな。

手元に偶々残っていたのは、90年代後半の分だが、「間違いだらけ」は1976年から、中断を経て30年以上にわたり刊行され続けた。僕は古本屋で買いそろえるなどして、たしか初年度から90年代ぐらいまでは全部持っていたと思う。
若い頃にはその痛快な毒舌にしびれたものだが、このシリーズが日本の自動車業界にもたらした影響の功罪については(実際、業界全体を動かす力にはなったのでしょうね)、いろいろと議論があるかとは思う。
今、僕は自動車趣味人の看板は下ろしていて、自分の車も持っていない。自動車雑誌は、この1年で1,2冊買って、その変貌ぶりに驚いた。ウェブで無料で見られる、新車評論のようなものを見るにつけ、もう昔のような自動車評論の時代は終わっているのだなあ、という気持ちを強くしている。僕が少しだけかじったいろいろな趣味の世界、たとえばオーディオの世界なんかも、読み応えのある文章を書く評論家の方がかつてはいたが、そういう、好きなものを「語りつくす」という世界は、終わってしまったようだ。それがなぜなのか、イデオロギー時代の終焉?ITとインターネットの進化?「男の世界」の終焉??わからない。
最後に、小沢コージ氏が徳大寺氏との対談を終えての感想を「徳大寺有恒からの伝言」から引用して終わりたい。
・・その面白さは、クルマ好きとカッコつけとオンナ好きが絶妙なバランスで混ぜ合わさっている点にある。それは、年齢を重ねれば重ねるほど貫禄を増していった。なぜなら発言がどんどん正直かつ正確になるからだ。なによりも、心の中をさらけ出しているような丸裸の発言なのだ。私は今までのクルマ評論一般が、なぜつまらないのか、なぜ興味がわかないのか、徳大寺さんの話を聞くたびにわかるような気がした。色っぽくないのだ。正直じゃないのだ。感情的じゃないのだ。
・・徳さんだって人間だ。貧乏は怖いし、ケンカも怖いし、時には安定もほしくなるときもあると思う。だがそんな素振りはみじんも見せず、堂々と正面から立ち向かう。だから過激だし、とてつもなく色っぽいし、男の私から見ても魅力的なのだ。そして何よりも正直である。そこに徳大寺有恒という自動車評論家の真骨頂があると私は確信しているのだ。
・・私自身思うが、特に最近、日本は男らしさ、男としての誇りが足りない。だから日本の男はモテないのである。サムライの持つ男らしさ、大和魂を忘れてしまっている。男らしさとはある種、愚直なまでのこだわりであり、主張であり、愛であり、ヤセ我慢だと思う。
拝金主義、合理化がますます進む中、そういうバカはモテないし、ウケないし、お得ではない。しかし、そういう男は常にいなくてはいけない。バカで、ヤリ過ぎで、イキがっていて、カッコつけで、誤解されるぐらいがちょうどいいのだ。日本男児は、やはりこころのどこかにサムライを持っていなければいけない。わたしはそれを勝手にこの偉大かつ愛すべき先輩から学んだと思っている。
徳大寺有恒さん、ありがとうございました。
書き始めたらこんなに長くなってしまった。
ご冥福をお祈りいたします。











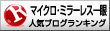














 。ああ、栗じゃあさるかに合戦になってしまうのか
。ああ、栗じゃあさるかに合戦になってしまうのか まんじゅうにしておこうか。こわいからね・・。
まんじゅうにしておこうか。こわいからね・・。




































































 、めんどくさくなってそのまま数駅先の神社を目指した。思ったより1時間は短かった・・。この時間感覚になれることも必要なようだ・。
、めんどくさくなってそのまま数駅先の神社を目指した。思ったより1時間は短かった・・。この時間感覚になれることも必要なようだ・。








