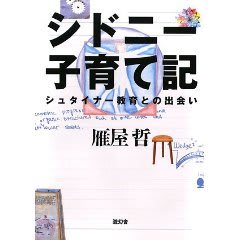宮台 真司氏の著作を読みたくて
借りてきた本。
『居場所なき時代を生きる子どもたち 』
共著:三沢 直子/宮台 真司/保坂 展人
子ども劇場全国センター出版局、」1999年
この本、あるシンポジウムの内容をまとめたものらしいです。
三沢 直子さん
臨床心理士で、一定のテーマで子どもに絵を描かせ、
それを長年経年観察してきたご経験をもとにした話。
三沢さんは、子どもたちに
家、木、人の3要素を、必ず描かせるそうなのですが
「家」が小さくなり、「家」と「人」との
関係が薄れていく傾向にあるそうです。
「家」は、子どもの精神的な基地ともいえるべきもの。
その存在が薄れていると言うことは
どういう意味を持つでしょうか。
そして、赤ちゃんを、子どもを育てると言うことは、
女性は一度「下女」の役割に徹することなのだそうです。
なるほど、納得。
子育て不安で相談に見える女性の前職をきくと
立派な職業ばかりなのだそうです。
悩むのも無理はない、とのご意見でした。
宮台真司さん
教育改革と親子関係
専業主婦不要論を唱えている方。
我が子の出来具合等のみに集中することの弊害を指摘。
いわば、「母子カプセル」の危険。
おっしゃることは的を射ているし、わかりやすいんだけど
少々過激な言葉を使う方だなあ。
でもこういうのは嫌いじゃない。
保坂展人さん
危機にある子どもの声をすくい上げるため
英国の「チャイルドライン」を視察した上で、
世田谷区に「せたがやチャイルドライン」を
実験的に導入したお話。
(のちに、せたがやチャイルドラインは
常設されました。
プレーパークせたがやの天野秀昭氏も
関わっておられました)
英国でのチャイルドラインは、
子どもの生の声を集約して、国の政策に
反映していく仕組みがあるそうです。
借りてきた本。
『居場所なき時代を生きる子どもたち 』
共著:三沢 直子/宮台 真司/保坂 展人
子ども劇場全国センター出版局、」1999年
この本、あるシンポジウムの内容をまとめたものらしいです。
三沢 直子さん
臨床心理士で、一定のテーマで子どもに絵を描かせ、
それを長年経年観察してきたご経験をもとにした話。
三沢さんは、子どもたちに
家、木、人の3要素を、必ず描かせるそうなのですが
「家」が小さくなり、「家」と「人」との
関係が薄れていく傾向にあるそうです。
「家」は、子どもの精神的な基地ともいえるべきもの。
その存在が薄れていると言うことは
どういう意味を持つでしょうか。
そして、赤ちゃんを、子どもを育てると言うことは、
女性は一度「下女」の役割に徹することなのだそうです。
なるほど、納得。
子育て不安で相談に見える女性の前職をきくと
立派な職業ばかりなのだそうです。
悩むのも無理はない、とのご意見でした。
宮台真司さん
教育改革と親子関係
専業主婦不要論を唱えている方。
我が子の出来具合等のみに集中することの弊害を指摘。
いわば、「母子カプセル」の危険。
おっしゃることは的を射ているし、わかりやすいんだけど
少々過激な言葉を使う方だなあ。
でもこういうのは嫌いじゃない。
保坂展人さん
危機にある子どもの声をすくい上げるため
英国の「チャイルドライン」を視察した上で、
世田谷区に「せたがやチャイルドライン」を
実験的に導入したお話。
(のちに、せたがやチャイルドラインは
常設されました。
プレーパークせたがやの天野秀昭氏も
関わっておられました)
英国でのチャイルドラインは、
子どもの生の声を集約して、国の政策に
反映していく仕組みがあるそうです。