年金の将来へ
先月十一月は年金月間だった。民生委員の私は今年地域型年金委員に委嘱されて、この期の19日、全国年金委員研修に参加できた。
研修はテレビ会議システムを活用して実施された。今全国で2300人余りが受講していると紹介された。内容は短時間に7項目のことが講義され、濃過ぎてとても難しいとの印象を受けた。年金委員数は職域型:約112,000人、地域型:約5000人いるとか。意見交換会の際に、委員へは「地域とつなぐ役割」をお願いしたい。委員からは国民が見えるように「現状や機構の努力を示す数値などを1回/月程度発信するとよいのでは。」など意見があった。
先日、民生委員の会において、委員研修時のポイントを紹介した。そして年金を積立てる人・受取る人の給与や年金額は、月毎に又は年毎に変更される。都度に膨大情報量を扱う。人口減少のため資金は減り、対応策で法が替わる。計算も替って、都度人数分を見直す。年金業務、処理量の多さを「大変な量だね」と理解する側の人になりませんか。
意見などの中に、人口増加の時代には資金が増えた、行政はその資金を使い国民の慰安施設などを沢山造った。倒産して今はみな無くなった。「理解する人になるのは難しい」と。場の雰囲気は急に曇る。「私達は今、年金を利用して安心して生活しています。これからの人たちも同じく、年金で安心して暮らすことができるよう、努めましょう」。精一杯のコメントだった。積立てる年金がこれからも、そんな年金であることに関係者が全力を尽くされる事をお願いしたい。











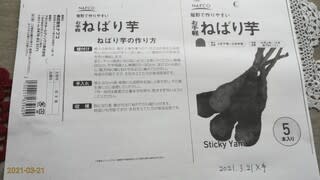 種芋
種芋 仕立て
仕立て  商品
商品




