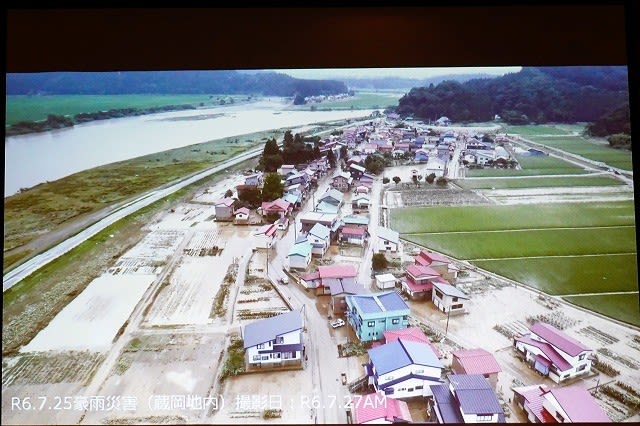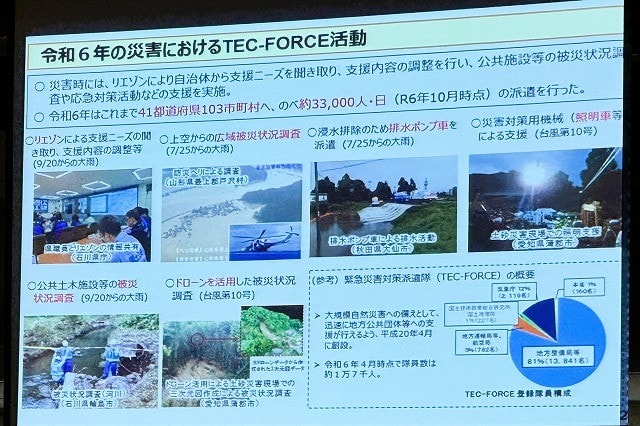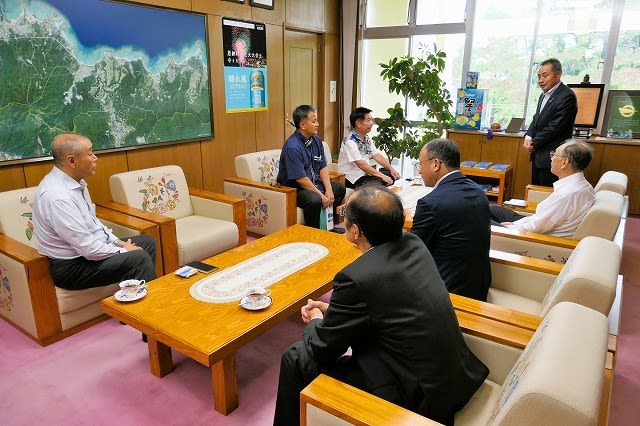9月30日(月)は雲が多くも午後には日差しが届き、朝晩は過ごしやすく、昼間は少し汗ばむ体感になりました。
東筑摩郡村長会視察研修2日目は、午前9時30分に与那原町役場に着き、最初にお忙しい中、照屋町長と城間副町長にお会いでき、視察対応の御礼の挨拶をさせていただきました。
照屋町長からは、飾ってあった与那原町の戦前から現在までの航空写真を見せていただきながら、当町の歴史や産業等の説明や脱炭素先行地域に選定した場所などの説明を伺いました。
我々は、東筑摩郡5村の位置や農業等の話をし、記念写真を撮っていただき研修室に移動しました。
研修は、与那原町の脱炭素に向けた取り組みについて、企画政策課 安慶田参事、山城課長たちに説明をしていただきました。
与那原町の概要として、場所は那覇市から車で約30分、大きさは5.18㎢キロメートルで全国4番目小さい町、人口は19,470人と近隣市町村に比べて少ないが人口密度は高い、施設は教育機関・病院・警察・商業などが揃っているとのことでした。
文化、イベントは、440年余の歴史がある「与那原大綱曳」と与那原町大綱曳資料館、郵便与那原駅舎展示資料館等があり、特産品は、赤瓦・ヤチムン、天然ヒジキ、ソデイカ等で、与那原マリーナ等の観光施設や観光ポータブルサイトの構築、キャラクターの「つなひきかちゃん」等で観光振興に取り組んでいました。
与那原町の現状と方向性として、「稼ぐ力が弱く、地域経済が循環していない地域となっている」ことにより、「地域で稼ぎ、地域で経済を循環(経済の地産地消)させるか」が重要とのことで、与那原町の東海岸を新たな価値を創造する「住む、働く、遊ぶ」を満たすエリアの実現を目指していました。
そして、再生可能エネルギー技術の発展により、地域で使う電気を地域で創ることが可能となっていることから、エネルギー関連産業を創出し、稼ぐ力と地域経済の循環を図りつつ、環境問題に取り組まれたとのことでした。
与那原町の脱炭素先行地域事業の取組として、脱炭素先行地域を「マリンタウンエリア」と「公共施設群」に設定し、令和5年度から令和9年度にかけて「再エネ導入・省エネの実施等」に取り組み、環境対策の他、①稼ぐ力不足、②災害・防災、③公共交通、④住民の健康といった課題への対策も行うこととしています。
太陽光発電・蓄電池・充放電設備・省エネ住宅等の計画、太陽光発電設備の導入・省エネの実施・大型蓄電池の導入・その他の電源の導入・EV車の導入促進等の概要、与那原町による出資・サテライトオフィスの開設等のスケジュールなどの説明を伺いました。
地域新電力の体制強化として、事業推進のため職員1名をおきなわパワーHD(株)(地域新電力会社)に派遣とサテライトオフィスを東浜地区コミュニティセンター内に開設し、地域新電力会社に25%の出資をされました。
環境省にて特筆すべき取組事例として、「自治体側も、新エネルギー会社への出資及び職員派遣を確約することによって、事業推進体制の確立に成功している」と評価されたとのことでした。
周知関連として、様々なポスターや桃太郎旗の製作、住民向け脱炭素の理解促進のため、役場1階ロビーで省エネパネル展や小学校において省エネ教室を行っていました。
令和5年度実績として、公共施設太陽光パネル設置及び充放電設備設置、中学校高効率照明機器(LED)導入、蓄電池設置、令和6年度の取組として、ソーラーアーケード、大型蓄電池、風力発電、波力発電の実証などが予定されていました。
与那原町が目指す脱炭素社会の経済面として、地域新電力を中心とした「エネルギー関連産業の創出」、MICEと連携した脱炭素ショールームによる「交流人口の増加」などを図り、マリンタウンエリアの開発とMICE施設イメージ、スポーツツーリズム イメージも説明していただきました。
その後、新エネルギー会社への出資や派遣について、効果促進事業について、沖縄県が進めるMICEについて、与那原町の現状について、与那原大綱曳の歴史と現状についてなどの質疑応答をさせていただきました。
その後、与那原大綱曳資料館(つなかん)にも寄って、与那原大綱曳について説明していただきました。
与那原大綱曳は、那覇・糸満と共にいわゆる「沖縄三大綱引」のうちの1つに数えられていて、「綱引」は沖縄県内各地で広範に分布している習俗の1つで、それぞれの地域的特色をもって行われており、地域の人々を結集するうえで大切な役割を果たしているとのことでした。
今年4月導入の360°フルスクリーンシアターで臨場感ある大綱曳映像を拝見しながら説明を聞きましたが、360°フルスクリーンの迫力ある映像で良い体験をさせていただきました。
祭りの主役となるのは、それぞれの役割を担った町民の皆さんで、綱引きを通じて、人と人をつなぐ場としての役割を担うと供に、次の世代に与那原町の歴史をつなぐ場としての役割を果たしていました。
照屋町長と城間副町長はじめ職員の皆さんには、大変お忙しい中、脱炭素に向けた取り組みを中心に、440年余の歴史がある「与那原大綱曳」まで、親切丁寧にご説明いただき感謝申し上げます。
2箇所目の視察は、昼食を途中で取り、恩納村役場に向かいました。予定の時間より早く着きましたので、恩納村の高さ20メートルの琉球石灰岩の断崖とその上に広がる芝生の公園の万座毛に寄りました。
琉球王、尚敬が「万人が座するに足る毛(野原)」として賞賛し、名前がついたと言われていて、琉球石灰岩の台地の上には、天然の芝が広がり、その周りの植物群落は、県の天然記念物に指定されている通りとても綺麗で雄大な景色でした。
その後、恩納村役場に午後1時25分に着きますと、長浜村長はじめ職員の皆さんが出迎えていただき、村長室まで伺う間に全員の職員の皆さんから歓迎の拍手をいただき感銘しました。
長浜村長から、恩納村の地形や観光客が年間400万人も訪れる観光等の村の概要、長野県川上村との「シンカプロジェクト」の経緯、農業や水産業の現状など歓迎の挨拶を頂戴しました。
東筑摩郡村長会の会長として、私から、視察研修のご対応に御礼を申し上げ、東筑摩郡の歴史と農業が基幹産業である各村の特産品の紹介、長野県町村会のことなどの御礼の挨拶をさせていただきました。
続いて、農林水産課 平安名課長達から説明していただきました。恩納村は沖縄本島のほぼ中央部西海岸側に位置し、面積が50.84㎢と広く海岸線は約46㎞と長く、移住者が多く、人口は11,275人と増え続け、住宅地価格が29%も上昇し日本一になったとのことでした。
農林水産業費は、令和6年度一般会計当初予算に占める割合は10.92%であり、農業部門では、小菊・パッションフルーツ・ドラセナ・アテモヤ・観葉鉢物が沖縄県の拠点産地に認定されていて、作物別経営体では、花卉類・花木が141経営体と最も多く、県全体の1割強を占めていて、さとうきび・野菜・果樹類も栽培しているとのことでした。
水産部門では、サンゴ礁海域を主な漁場としており、モズクなどの海藻養殖を主力として発展し、沖縄県の拠点産地に認定されているモズク、海ぶどう(クビレタス)、アーサ(ヒトエグサ)についてはブランド化に力を入れるとともに、資源管理型漁業の安定継続を目指していました。
シンカプロジェクトとは レタスの一大産地の長野県川上村より、レタスの栽培技術指導を受け、恩納村で産地化を目指し、恩納村内のホテルや飲食店へ出荷し地産地消も推進していき、「シンカ」とは沖縄の方言で「仲間」を意味する「シンカヌチャー」から由来されています。
シンカプロジェクトの始まりとして、恩納村の夏は亜熱帯気候で暑く、レタス栽培には適さない気候ですが、冬の気温は20℃前後と川上村の夏と似ていて、この温暖な気候と自然豊かな大地のもとで、川上村の長く培った野菜栽培技術を活用してレタス栽培に取り組むプロジェクトでした。
シンカプロジェクトの役割は、村内のリゾートホテルや観光客の皆さんに地元産の安全・安心はおいしい新鮮野菜を提供し、若い農業者が定着し、遊休農地の有効活用を図っていきたいとして取り組み始めました。
平成27年度に始まり、川上村の規格に適用できる農家が平成30年度に半減してしまいましたが、コロナ禍開けには2名の農家になってしまいましたが、収穫は当初より多くなって、大規模化になったとのことでした。
レタス栽培の課題として、恩納村では栽培を行う上で北風の影響大きいことが分かり、圃場によっては、風速20~30mが2日間続き、潮風による影響でレタスの外葉が枯死してしまう現象が続いたとのことでした。
また、冬になると「タイワンシロガシラ」という鳥がレタスをエサにして圃場に現れて、定食直後の苗から出荷前のレタスまで食害を発生させるほか、糞の付着など様々な害が発生していて、主な有効策として防鳥ネットを設置してもらっているが、強風の影響で設置後に破れることも多く、対策に苦慮しているとのことでした。
出荷は、おんなの駅なかゆくい市場を通して「シンカレタス」として販売していて、シェフのレタスに対する評価は高いが、ホテルの購買担当がカット加工され消毒洗浄されたレタスを求めていることが分かり、当工場がなく大きな壁となっている。
シンカプロジェクトの今後取り組みとして、販売体制の構築、安定供給体制の構築、生産者の増加の3点を改善できる取組を検討していくことが必要で、村内でも土質が違い栽培に苦慮されているなど、課題は多いとのことで、長野県の大規模な産地とは違い、ご苦労されているなどの話をさせていただきました。
実際圃場に案内されて行きましたが、何筆かを集約した圃場でも面積は狭く、粘土土で水はけが悪く、定植する準備ができていない状況でした。
定植後「タイワンシロガシラ」の防鳥ネットを設置して作業を行うとのことで、消毒や出荷作業などネットの下で行うことは効率も悪く、大型機械の導入もできず大変だと感じました。
でも、栽培をされている農家の方は、明るい顔で説明していただき、農業に対して前向きな姿勢に感心しましたし、どうにか長野県川上村からご指導いただいているレタスが、沖縄県で沢山消費していただければと感じました。
長浜村長はじめ職員各位には、お忙しい中温かく出迎えていただき、丁寧親切にご説明いただき御礼申し上げますとともに、有意義な視察研修になりましたことに感謝申し上げます。
△▽ 毎朝恒例の写真と動画は、先日撮り溜めの朝霧の中から朝日が差してきた草尾上野ぶどう畑上空から風景です。
草尾上野ぶどう畑上空からの風景
本日生坂村では、小学校でクラブ、中学校で振替休日などが行われました。