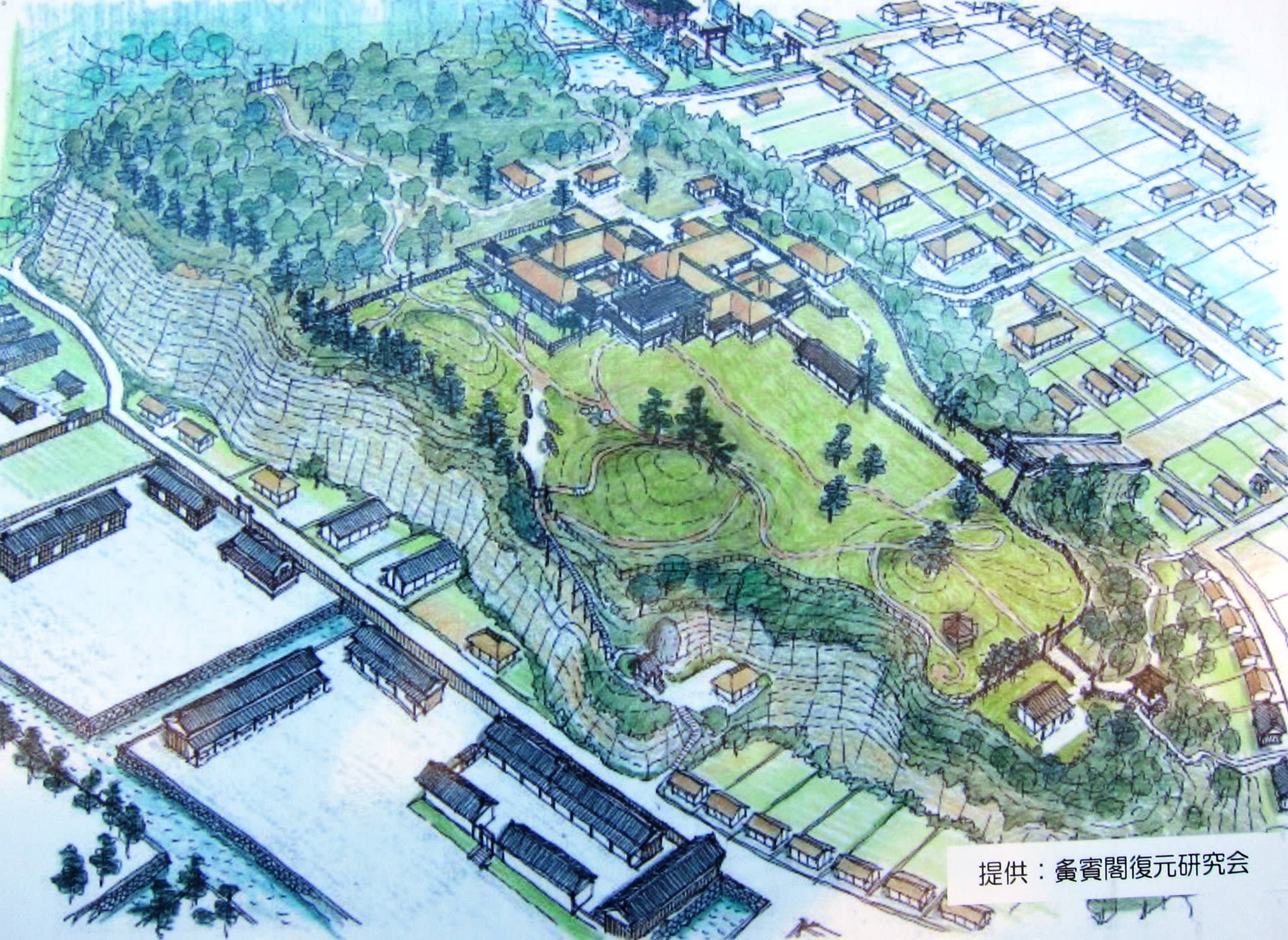このバラの花の形はなんだと思いますか。
これはヒマラヤスギの実です。松ぼっくりでなく、杉ぼっくり?その長い大きな実は鱗茎が種子と一緒に分かれて少しずつ落ちますが、先端部分だけが残って落ちているのは、まるでバラの花のようです。

その形から、シダーローズ(Cedar ヒマラヤ杉Roseバラの花)と呼ばれ、リースなどにも使われるようです。茨城県花のバラをかたどった自然のアクセサリー、自然もなかなか乙なことをするものです。

地面からニョキッと出てきた不思議な突起物、まるで夫婦地蔵か芸術作品…、これはアメリカ大陸の東南部からメキシコに分布する落葉のヒノキ科の高木、最近公園などで目にするラクウショウ(落羽松)の根で、気根、呼吸根、膝根とか呼ばれています。

湿地の生育に適した樹木で、長期間の水没に耐えることができます。普通の場所に植栽すると気根を出すことはありませんが、湿地に生育すると、根が水中で酸素不足になるため、根の上側が成長して地上に出てきて呼吸します。
環境に応じた変幻自在のたくましさ、ぜひ見習いたいものです。
1月の水戸市植物公園でのひとコマでした。