§542
— review (@myenzyklo) 2016年11月4日 - 00:44
有機的な全体としての政府にあっては、(1)主体性とは、概念が展開される中で、概念が自己自身と無限に一体となるときは、すべてを支え決裁する国家意思であり、国家の最高の頂点であり、すべてを貫いている統一であるところの君主の施政権である。概念のすべての契機をして
その自由な生存に至らしめている完全な形の国家においては、この主体性は、いわゆる「道徳的な人格」でもなければ、また多数決によって生じてくるある一つの決裁でもない。つまり、決裁する意思の統一としては現実に存在していないこれらの二つの形式ではなく、現実の個別性としての
— review (@myenzyklo) 2016年11月4日 - 00:51
一つの決裁する個人の意思である。すなわち君主制である。それゆえに君主制の国家体制(憲法)は、発展した理性の国家体制であり、それ以外の全ての国家体制は、理性のより低い実現の発展段階にあるものである。#国家体制、#君主制、#憲法
— review (@myenzyklo) 2016年11月4日 - 00:58
補註
— review (@myenzyklo) 2016年11月4日 - 01:10
家父長制的な状態がそうであるように、全ての具体的な国家権力を一つの現実の存在として統一すること(専制)、あるいは、民主主義的な憲法の場合のように、全ての人々が全ての仕事に参与すること(民主)、この二つの場合は、それだけでは権力分割の原理に、すなわち、理念の契機を展開させる
自由の原理に反する。しかし同じように、諸々の契機を分割すること、自由な総体に進むような形に諸々の契機を形成することは、統一された理念に、すなわち、主体性に還元されなければならない。理念が形成されて区別を得ること、理念を実現することは、この主体性が実在する契機として、
— review (@myenzyklo) 2016年11月4日 - 01:18
現実の存在にまで成長してきていることを本質的に含んでいる。この現実性はただ君主の個人性にのみある。すなわち、抽象的な最終の決裁の主体性、一個の人格の中に現存している主体性である。しかし個別的な意思の原子論的な性格から、民主的もしくは貴族制的な形で出てきてしばしば取り上げられている
— review (@myenzyklo) 2016年11月4日 - 01:31
例の共同の決裁や意志が持っているあらゆる形式には、抽象物としての非現実性がまといついている。大切なことは、一つには概念の契機の必然性と、その概念の契機の現実の形式という二つの規定だけである。弁証法的な概念の本性だけがこのことを理解し得るのである。国家の主体性は、
— review (@myenzyklo) 2016年11月4日 - 01:38
抽象的な決裁一般という契機であるから、一方では、君主という名目が外面的な絆として、一般に統治するときに起こりうるすべてのことの裁可として現れてくるという現実に進んでゆく。また一方では、君主が自身との単純な関係として直接性という規定を、したがって自然性という規定を自らにおいて
— review (@myenzyklo) 2016年11月4日 - 01:58
持つということになる。このために個人としての現実性によって、世襲こそが君主制的権力に値するものとして確立されることになる。#君主制、#世襲
— review (@myenzyklo) 2016年11月4日 - 02:00










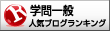





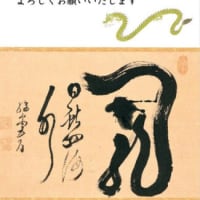
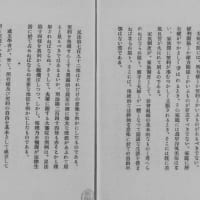

![ヘーゲル『哲学入門』第二章 義務と道徳 第三十七節 [衝動と満足の偶然性について]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/b9/ae7fc3fa05eeda789aa4d9d112b37d72.jpg)

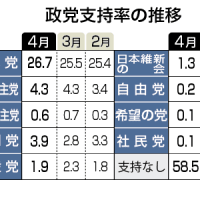







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます