これまでの従来の概念観によれば、概念とは、個別具体的な事物についての経験から、その共通点を帰納して作られた単なる「観念」としてとらえられてきた。そうした「概念観」の欠陥は、ふつうの単なる帰納法科学にすぎない生物学や人類学のレベルならとにかく、それを超えた自己運動する生命などを科学の対象にできないことである。
概念とはそのようなものではなく、たとえば光源氏の母、桐壺の更衣の胎内に観念的に宿り、自己内矛盾によって一つの種のように豊かに展開し成長する物語の生命としての存在が「概念」である。この事物に内在する矛盾を認識し、その自己運動を必然性として認識しようとすること、それが事物を概念的に把握するということにほかならない。こうした概念観が重要であるのは、本来の科学とは事物の内在的な運動の必然性を認識し、それを論証することだからである。だから、この科学は、弁証法科学もしくは演繹法科学とも呼びうるが、この概念のもっとも普遍的な運動法則を展開したものがヘーゲルの論理学である。科学としてこの論理学の意義と重要性もここにある。
源氏物語も、橡川一朗氏の提唱するような民主主義の教科書としてではなく、概念論の検証として、弁証法の検証として読むことはできないだろうか。
源氏物語は光源氏の母、桐壺の更衣の描写から始まる。
古典の中の古典『源氏物語』の主人公、光源氏の母である桐壺の更衣は、ただ源氏物語の冒頭の巻『桐壺』に登場するだけである。この冒頭の巻の中に、流星のように現われては果敢なく消えて行く。
多くの女御や更衣たちが帝に仕える中で、その美貌のゆえに帝の寵愛をうけた桐壺の更衣は、帝の寵愛がかえって不幸の種になって短い薄幸の生涯を終える。この桐壺の更衣は、主人公光源氏の母であるから、当然に源氏物語そのものの母でもある。全五十四帖の物語はすべて、この美しい悲劇の女性、桐壺の更衣の胎内に含まれている。
帝に愛されたこと、そして、すべての悲劇の種は桐壺の更衣が必ずしも高貴な身分ではなかったことにある。そのために、桐壺の更衣は帝の正妻である弘徴殿の女御や同僚や下臈の更衣たちの羨望と嫉妬を一身に集めることになる。
芸術家は批評しない。ただ、淡々として事実を芸術的な表象として描写し読者の直観にさらして行くだけである。作者紫式部もこの更衣の悲劇を事実として叙述するだけである。しかし、読者はこの悲劇の原因を目撃している。
傾城の美女の逸話がつとに人々にあまねく知られていたことは、作中に楊貴妃の例が冒頭に挙げられていることによっても分かる。実際に作中に楊貴妃の例を取り上げることによって、帝を取り巻く公卿たちに、帝の桐壺の更衣に対する寵愛振りに眉を顰めさせる。
紫式部は長恨歌をこの源氏物語の構想の下にはっきりと意識していた。そして、彼女は長恨歌と同じモチーフを、彼女の生きた平安期の貴族社会を舞台にして、彼女がその生涯の内に出会い心をときめかした事柄を、源氏物語という大作の中に封じ込めて行く。源氏物語の中には、平安の貴族社会に生きた人々の思考と感情が、紫式部という類まれな女性の意識という鏡の中に見事に映し出されている。
紫式部は道長の娘、彰子に仕えた。源氏物語が紫式部のように宮廷生活に精通した、教養豊かな女性によってしか書かれるはずのなかったことも明かである。私たちは何よりも源氏物語を読むことによって、紫式部の広大な内面世界を垣間見ることになる。
この帝と桐壺の更衣との間に皇子が生まれる。
このような子供の生まれることは、当時の人々にとっては、前世の浅からぬ因縁のゆえである。また一方で、桐壺の更衣との間に生まれた皇子が、正妻の弘徽殿の女御の第一皇子よりも比較にならないほど可愛く美しかったことがますます正妻の嫉妬と猜疑をあおることになる。これが桐壺の更衣に与えられた宿命である。
桐壺の局に住まっていた更衣のもとに頻繁に通われる帝に対して、更衣への人々の羨望も嫉妬も止む得ないものとして、作者も女御や同僚たちの恨みにも同情を寄せてもいる。そして、帝の更衣に対する寵愛が深まれば深まるほど、人々の更衣に対する羨望や嫉妬が深まるという不幸な構図が浮き彫りにされるなかで、これといった、有力な後見人を持たずに宮仕えをせざるを得なかった桐壺の更衣は、ただただ帝の庇護だけを頼りにして、不安で孤独な宮中生活を過ごさざるを得ない。
桐壺の更衣が同僚たちからどのような取り扱いを受けたか、その様子などは実際の宮中生活の体験なくしては描写できなかったように思われる。読者はこの美しい気の毒な更衣の幸せ薄い運命に同情せざるを得ない。
幼き源氏がようやく三歳になって御袴着を終えたばかりの夏には、女御や同僚の更衣たちの嫉妬やいじめが募った心労から病が篤くなり、実家に退出しようとするが、更衣を手許から離したくなかった帝は容易に許そうとはしない。とても可愛らしかった更衣ももうこのときにはすっかり面痩せて、だるげで、意識もあるかなきかの様子である。さすがに帝も拒みがたく、仕方なく退出を許されるが、加持祈祷の他にこれといった治療法もないなかで、その功もなく、更衣は里で果敢なく身罷ってしまう。
桐壺の更衣はもっとも美しい日本的な女性として、中国の傾城の美女、楊貴妃と対比するように描かれている。更衣の容貌は「いとにほいやかに、うつくしげなる人」とわずか二つの形容動詞で描写されているに過ぎないが、「唐めいた粧はうるはしうこそありけめ」と対比的に描写することによって更衣の和風の美人像が描かれる。中国の圧倒的な文化的な影響を脱して、平安期の時代としての、日本的な美意識の成熟がある。唐風の影響も残してはいるが、宮廷生活や気象天候の描写を通じて日本独自のいわゆる国風文化の美意識が作者紫式部によって明確に自覚されていることが見て取れる。
この「桐壺」の舞台は、今もなお存在する清涼殿である。紫式部は現実に存在する宮廷を物語の舞台として設定することによって、その物語の実在感を確かなものにしている。清涼殿の建築構造の正確な描写や御袴着などの宮中儀式の的確な描写を通じて、この物語のリアリズムが揺るぎなきものになっている。物語という言わば「影の国」が、単なる現実よりも現実的でありうるという優れた芸術作品の例がここにある。桐壺の更衣はこの清涼殿のなかで、桐壺の局で帝の寵愛に生き、また、女御や同僚たちのために悩み、苦しんだ。
人間関係における嫉妬、羨望、猜疑や、病気、死などの人間的な真実が、宮中生活の細部に至るまでの克明な描写と、野分や月光や八重葎の生える荒れた庭先などの自然描写を通じて、娘を失って闇に暮れ惑う北の方の心情が描き出される。
そして、このような宮中のさまざまの人間群像の実際の姿を描くことによって、源氏物語もその他の多くの古典作品と同様に人間の普遍的な真実を明らかにしてゆく。
台風一過の後の肌寒さがいっそう募る夕暮れ時の、帝よりの使者、靫負の命婦と更衣の母北の方との二人の婦人の会話、そして、彼女らの会話のなかで命婦の言葉の端々に描写される、最愛の女性を失った帝の失意と落胆の様子、また、若宮の参内の催促に対する北の方の不安と戸惑いなどに、時代を超えた人間の真実が物語として、読者の眼前に展開されて行く。その叙述にはいささかの弛みもなく古典名作の誉れにふさわしい。
ここに登場するのは、平安貴族の、しかも当時の国政の中心をなす帝とその周辺の人々の生活であるが、皇位継承に絡む確執なども唐や高麗などの異国との交流をも織り交ぜながら、藤壺とこの物語の主人公である光る君との関係を機軸とする物語の展開を暗示して桐壺の巻は閉じられる。
桐壺の更衣の死を中心に展開するこの巻の物語はたしかに悲劇とも言い得るけれども、もちろんここには神の意志や裁きといった観念はなく、帝と更衣の出会いと、その皇子光源氏の誕生も、前世の因縁の深かりしゆえと、仏教的な世界観でそれも暗示的に説明されるに過ぎない。
特に帝の性格や行動は、きわめて女性的で、帝を一個の男性として独立的に造形することに紫式部が成功しているとは言いがたい。また当時の一夫多妻制や婚姻制度ももちろん批判的な観点などはなく、貴族や女性たちの性行動も極めておおらかであり、自由で奔放ですらある。
桐壺の更衣の死の後、さらに幾月かが経過して、若宮が六歳になったときに、娘の跡を追うようにして北の方も亡くなる。孤独に取り残された光君は、父桐壺帝をのみ頼りに宮中に移り住む。高麗人の人相見を鴻臚館に招き若宮の顔相を占わせることによって、若宮の姿が描き出される。そして源氏が幼くしてすでにただならぬ存在であることが明らかにされる。そして、この高麗人の人相見から、光る君と呼ばれる若宮の容貌も母と同じく、「にほいやかでうつくし」と描写されるに過ぎない。
七歳になった若宮は学問も音楽などの技芸も上達著しく、それゆえにいっそう、第一皇子の母、弘徽殿の女御や祖父の大臣の疑いを招くことになる。高麗の人相見から若宮の不吉な未来を予言された父帝は、光君の地位を確かなものとするために、源氏姓を賜って臣下に組み入れになる。
やがて十二歳になった若宮は元服され、長い年月の経過も、慰めにはならず、帝は、内侍の勧めに従って、なき更衣の面影を持った藤壺を召し出すが、もちろん桐壺には代わるうるものではないが、それでも自然の人情として藤壺に心が移ろって行くのも感慨深いと紫式部は言う。
幼くして母を失い、その面影さえ記憶にとどめない若宮が、人々から、今はなき母更衣に似た面影を持つと噂される藤壺に心引かれ、また帝も藤壺に若宮を可愛がるようにという。若宮は左の大臣の娘、葵の上を正室に迎えてはいるが、若宮の心は藤壺の姿をたぐいなきものに思い、内裏住まいをのみ好ましく思って、葵の上の許には絶え絶えにしか参上しようとしない。このとき、若宮は元服を終えたばかりの十二歳、藤壺は十六歳。若宮は一途に藤壺に傾斜して行く。
帝の行為が、静かな湖面に投げ入れられた小石のように、無限の波紋を生んで行くなかで、光源氏の運命の歯車が回り始める。
「桐壺の巻」の構図
登場人物
帝、桐壺の更衣、母北の方、弘徽殿の女御、光る源氏、靫負の命婦、その他の更衣、女房、乳母、藤壺、葵の上、左の大臣










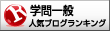






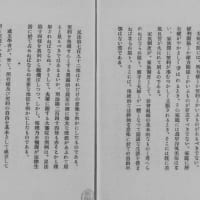

![ヘーゲル『哲学入門』第二章 義務と道徳 第三十七節 [衝動と満足の偶然性について]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/b9/ae7fc3fa05eeda789aa4d9d112b37d72.jpg)

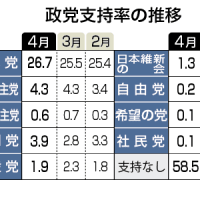







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます