1元、5元、10元、20元、50元、100元札と
全て毛沢東の顔だ。
いかにも優しく微笑む中年時代ぽい毛さんの顔(本当にこんな顔だったんだろうか)。
しかし、なぜどれもこれも毛沢東ばっかりなんだ?
(偶像崇拝だめなんじゃないの?)と中国人民のために心配してあげていたのだが、
ついに毛沢東以外の顔のあるお札を発見!
右下の2枚、1角と2角のお札だ。

両方とも、1元~100元札に比べてやや小さい。
この人たちは誰なんだろうと、4年の3人娘に聞いたら
「名も無き少数民族の人々です」
とのこと。少数民族の地位を保証しているというプロパガンダのようだ。
それにしてもこの2角札のシワクチャなこと。
触ったら手が汚れそうな気がする。


これらは新札で、以前は周恩来のお札や別の人のお札もあったとのこと。
なぜそれをやめたか、私の想像だが権力闘争の浮き沈みの中で、
お札になった人の名誉も時には失墜する可能性があるからじゃないだろうか。
(毛沢東なら間違いない)と中国造幣局?が判断したのかもしれない。
それに江沢民とかのお札が出回ったりしたら、
はっきり言って私は日本に帰らせてもらいますから。
全て毛沢東の顔だ。
いかにも優しく微笑む中年時代ぽい毛さんの顔(本当にこんな顔だったんだろうか)。
しかし、なぜどれもこれも毛沢東ばっかりなんだ?
(偶像崇拝だめなんじゃないの?)と中国人民のために心配してあげていたのだが、
ついに毛沢東以外の顔のあるお札を発見!
右下の2枚、1角と2角のお札だ。

両方とも、1元~100元札に比べてやや小さい。
この人たちは誰なんだろうと、4年の3人娘に聞いたら
「名も無き少数民族の人々です」
とのこと。少数民族の地位を保証しているというプロパガンダのようだ。
それにしてもこの2角札のシワクチャなこと。
触ったら手が汚れそうな気がする。


これらは新札で、以前は周恩来のお札や別の人のお札もあったとのこと。
なぜそれをやめたか、私の想像だが権力闘争の浮き沈みの中で、
お札になった人の名誉も時には失墜する可能性があるからじゃないだろうか。
(毛沢東なら間違いない)と中国造幣局?が判断したのかもしれない。
それに江沢民とかのお札が出回ったりしたら、
はっきり言って私は日本に帰らせてもらいますから。










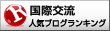

















先週末に、この日のブログを読んだ際、この記述が気になりましたので、調べてみました。
> 4年の3人娘に聞いたら
> 「名も無き少数民族の人々です」
この2角・1角の各紙幣上に印刷された少数民族には、歴とした正式名称があります。現代漢語詞典にて、民族の名称を確認しました。
2角紙幣の民族は、左が布依族、右が朝鮮族。1角紙幣の民族は、左が高山族、右が満族(満洲族)です。
猶、紙幣上の民族肖像と正式名称の照合は、別の専門辞典を参照しました。
> 少数民族の地位を保証していると云う
> プロパガンダのようだ。
御指摘の通りです。対外的に、「中国政府は少数民族を保護し尊重する民族政策を採用している。日常生活に欠かせない紙幣にも、この通り、少数民族の肖像を印刷している。」と宣伝活動に使えれば、それで十分なのです。
学生にしても、自分自身が少数民族の出身でなければ、江西省では有数の難関大学と云っても、学生の意識から少数民族は抹殺されており、始めから存在しないのです。
現代中国社会に於ける「少数民族の地位」を如実に反映した「優良学生の模範回答」ですね、これは。
貴女の解説にもある通り、この種の低額紙幣は専ら、公共バスや野菜など公共サービスや日用品の支払いに利用されるため、往往にして皺くちゃとなり破れ易く、手垢で擦れ印刷画像も消滅しがちです。
そうした「粗略に扱われ易い低額紙幣に、態々、少数民族の肖像画を配置し印刷する通貨政策」に、中国政府の少数民族政策の本音が露骨に呈示されています。
お時間ありましたら、貴女の日常生活でも、周辺に少数民族が居るのか居ないのか、注意を払って観察してみて下さい。お元気で。
「名も無き少数民族の人々です」
という学生の言葉についてですが、
Yozakuraさんの解釈には誤解があります。
「名も無き」は「少数民族」にかかるのではなく、「人々」にかかります。
いくら中国の片田舎である江西省の学生でも、小学校からの公教育で中国には56民族がいて、それぞれの民族には名前がついていることぐらいは叩き込まれていいます。たった55しかない少数民族に名前がないなどと、想像する人もいないのでは?と思うのは私の思い込みでしょうか。
文脈を確認して頂ければ、「名も無き」は、私の「この人たちは誰?」という質問への答えであることがお分かりでしょう。私の質問の意味が(ほかのお札は全部毛沢東ですね。では、これらの人たちの名前は何ですか)という意味だということも自然に理解できることではないかと、自分としてな気にも止めずに書いた文です。
確かに彼女たちは、少数民族の名前は具体的に記憶していませんでしたし、それは、中国の公教育が少数民族を重視していないことの現れだと思います。
ちなみに、江西省は中国で2番目に貧乏な省だそうですが、それは、少数民族が暮らしていないので、少数民族加配が中央政府からもらえないことも大きな原因だと、大学の中国人の先生が言っていました。
私の勤務する大学の日本語学科には、江西チワン族自治区から2つの少数民族を代表?する学生が1人ずつ、また新疆ウイグル自治区からも1人来ています。
チワン族自治区のミャオ族の子は、この前の春節休み明けに、地元の粽をお土産に持ってきてくれました。
形も独特、中身が肉やら具だくさんで、本当に美味しかったです。
日本には、アイヌ民族が存在することも知らない多くの和人がいますね(私も和人の子孫です)。「人の振り見て我が振り直せ」とは昔の人の諌めですが、今の日本人にも当てはまりそうですね。
①上から11行目の「自分としてな」の「な」は「は」に、
②下から6行目の「江西チワン族自治区」の「江西」を「広西」に訂正します(^_^;)
6月21日付けの回答、拝見しております。返信有難うございました。
私が問題としました原文「名も無き少数民族の人々----」ですが、
その発言状況や発言者の人品骨柄、語学力には、当方は何ら一次的な知識も面識もなく、そその場に直接に居合わせたものでもなく、
その発言の意味する内容や意図は不明でした。従って、反論も暫く差し控えておりました。
が、先日の「教え子がやって来た」にて紹介されていた中国人の劉思女亭・広東外語外貿大学院生(修士課程の院生?)は、その「4年の3人娘」の独りだったのでしょう?違いますか?
このブログ【終わり----始まる】2012年04月08日号では、「進学組4年生3人」として紹介されていますね?この人達でしょう?
貴方の訪日歓迎記事を拝見する限りでは、同年輩の中国人の中でみても、彼女の知的水準は高く思考は深く柔軟で、日本語の語言水準も相当な高さにあるものと推察します。
云うなれば、現代の中国青年の中でも、相当に知的レベルの高い層に属する人物でしょう。
で、そういうレベルの人物が使用した表現
「名も無き少数民族の人々----」
とは、日本語でも本来の用法である、
「名前の有無やその実態なぞ、問題ではない。どうでも宜しい。譬え名前があったとしても、名前の如何なぞ気にしなければならない程の、重要性や必然性なぞ認められない、軽い存在の人物に対しては、こうして、『名も無き人々---』と、用いるのが通例である」
と、日本国内の一般的な用法をちゃんと理解し、それを弁えた上で、立派に遣っているではないですか。
「名も無き少数民族の人々----」とは、発言者にしても、少数民族の実際の呼称や正式名称なぞ、「どうでも良い。知らなくても、構わない」と思っている、日頃の生活観念が、日常意識がポロッと言葉の端に洩れて来ただけでしょう。
要は、平素より涵養されている「少数民族に対する日常意識」が、その儘に露呈されただけなのです。
これに対し、貴方の弁明は実に不可思議ですよ。
> 「名も無き」とは、「少数民族」にかかる
> のではなく、
> 「人々」にかかります。
少数民族にせよ、人々にせよ、中国に実在する民族集団や公民の個人には、当然のことながら、個別に具体的な名称があります。付いています。
私が、態々、紙幣に引用・印刷された少数民族の名称を個別に指摘し、その「正式名称が実在する事実」を指摘したのは、
少数民族の個別名称に何ら関心を払わず、その非・重要性を当然視して憚らない、貴方の御自慢の学生達の意識構造の是非を、改めて問うてみたかったからですよ。
> 「名も無き」は、私の「この人たちは誰?」
> という質問への答えであることが
> お分かりでしょう。
個々人に名前があるとか、無いとか、そんな簡明率直な事実くらい、特に考えなくても直ちに分かる真理でしょう?違いますか?
実際に遣り取りされた会話の現場に居合わせてはいませんから、その場の人間関係や雰囲気には全く不明ですが、
通常に「名も無き少数民族の人々----」と発言されたのであれば、それはもう、
「名前の有無や実態なぞ知らなくても構わない、軽視して構わない対象としての少数民族の人々----」と解釈するのが、もっとも妥当であると私は思います。
それが、日本語としても、最も普遍的な解釈であり、亦、用法でもありましょう。
私が「優良学生の模範回答」と評した所以でももあります。
亦、「日常生活の中に存在している少数民族の実態」ですが、貴方が勤務する江西省の難関大学の日本語学科に入学し学習している少数民族学生が僅か3名と云うのは、矢張り少ないのかもしれません。
但し、そうした難関大学に学ぶ学生は、当然んことながら、各少数民族の代表に近い「優秀な学生」であり、はっきり云えば、「日常生活の中では先ず見かけない、例外的な少数民族の一例」と云えましょう。
私が6月の投稿原文で示唆したのは、
「限られた環境ではあっても、日常の在中国、在南昌生活で偶に見かける、目にする少数民族が、中国人の多数派の中で、或いは漢民族の周辺で、どの様な暮らしを送っているか、注意して観察されては如何ですか?」
と尋ねてみたのです。
例外的な存在とも云える「民族代表に近い少数民族出自の優秀な学生」では、多数派の中での少数民族の暮らしは、それ程明瞭には浮かび上がって来ないでしょう。違いますか?
もう少しで、また江西省へ帰任されるとの由、お元気で。