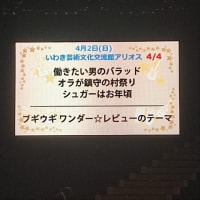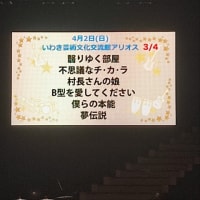以下は
「アーレントにおける二者の問題」國分功一郎氏
2017.09.09(Sat.)於:慶応大学西校舎519教室
の聞き書きノート。
例によって自分でメモした覚え書きです。
聞き間違いも多いし、メモ出来なかったところもあるので、個人的な覚え書きの域を出ません。
ご承知おきください。
以下開始-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
これは研究ノートのようなもの。
アーレント研究者のみなさんにとっては「そんなこと知ってるよ」という内容がほとんど。
まず教科書的に整理して、最後に僕なりの論点を付け加えるという感じ。
タイトルは「ハンナ・アーレントにおける二者の問題」
ハンナ・アーレントの思想において、「数」というのは本質的な意味を持っているカテゴリーである。
政治と哲学の関係というのは基本的に数によって提示される。
政治は複数に対応し、哲学は1に対応する。
政治というのは人間が必ず複数人存在する。このコロンブスの卵的な発想だが、人間は必ず複数いる。それゆえに要請される営みだ。
政治にとって根本的条件である複数性というのは、
「The Human Condition」(邦題『人間の条件』ちくま学芸文庫)
において各人の区別(distinctness)と平等(equality)という概念に翻訳されている。
「人間は一人ひとり異なる。だから必ず人間たちの間には不一致がある。しかし人間は平等であるから、その不一致を乗り越え、同意を獲得することができる。もし人間が平等でないなら、同意を獲得する可能性も必要もない。」
同意を得るための手段としてアレントがいつも強調するのは言葉。
同意を得るためには言葉によって説得しなければならない。
そこで、アレントはしばしば説得(ペオテイン)と暴力(ビヤン)との対立に言及している。
例えば「権威とは何か」において
「ギリシャにおいて前者つまりペイテイン(説得)というのは、ポリス内部の一般的解決方法であって、後者すなわち暴力(ビヤン)は他国との問題の一般的解決方法である。」
」
つまり、政治すなわちポリスの=ポリティックスとは従って平等な者の間での言葉による説得と同意を前提としている。
暴力が現れた時に政治は消える、ということ。
「暴力は有無を言わさず人々を従わせることはできるが、同意をもたらすことはできない。」(「暴力について」)
とアレントがは言っている。
説得と暴力というものの区別がアレントの中にははっきりとあって、複数人が関わる営みを政治とそうでないものとに分けるのは、この二つの区別だ。
人間が複数に関わる営みのうち、意見(オピニオン、ドクサ)を政治は扱う。
「私にどう見えるか」が問題。
だから必ずその意見というのは多様になる。
人間の複数性あるいは区別というのものは、具体的には意見の多様性として扱われる。
意見は必ず多様だ、と。
ところが、真理は違う。
「真理はその妥当性を主張する仕方において意見と鋭く対立する」(アレント)
真理は強制だ、と。
「真理を語ることを職業とする者に顕著な暴君的傾向」(アレント『真理と政治』)
つまり、「哲学者とか真理を語っている連中は非常に暴君的だ」と書いてある
これは真理に本質的な特徴。
真理というのは強制的な要素を持っている。
で、真理が強制的なものである、っていうのは、これは当たり前っていうかここから真理が多様性、すなわち複数性を断固として認めないっていうことを意味する。
真理と言うのは多様性を認めない。
単独者としての人間、singulerな存在としての人間だけに真理は関わる。
ここが「1」ということ。
哲学っていうのは哲学者が一人で営みである。
一人で行う。
だからここできれいに政治は「複数で」、哲学は「一人で」、と対立することになる。
プラトンの洞窟の比喩について、アレントは
「哲学者は一人で(洞窟から)出てくる」
と指摘している。
なるほどな、と思う。
一人で出てって太陽の下でイデアを見てきて、一人で洞窟に戻ってきて一人で
「おいおまえら一緒に外行こうぜ」
って連れてったら、連れて行かれたやつらが
「目が痛いよ、こいつ何すんだ」
ってもう一度哲学者を洞窟に連れ込んで、みんなにぼこぼこにされる……っていうのが洞窟の比喩なわけです。
哲学者は全部一人で行う。そこにアレントは注目している。
プラトンの時から哲学って一人で孤独に行うものだ……それゆえに哲学者はバカにされたりする。疎まれる。そして場合によっては殺されてしまう(ソクラテスのように)
。
哲学は哲学者が一人で行う観照(主観を交えずに自然や人生などの本質を見極めること)である、と。
で、アレントはこういう。
「意見による支持を何ら必要とせずに妥当する絶対的真理が、人間の事柄の領域で要請されるならば、一切の政治、一切の統治の根底が覆える。」
政治に真理を導入してはいけない、と。
政治が真理を援用するやいなや、政治はその根本を覆される。
しかし哲学史の起源にプラトンは哲人王の理想においてそれを追い求めた。
二十世紀には共産主義国家が歴史の真理を手にした政府っていう形でそれを実践した。
このことにアレントは大きな問題を見ていたのではないか。
とにかくこの「1と多」っていう対立でだいたい説明ができる。
哲学と政治っていうものの折り合いの悪さを、「1と多」という数の対立はこの上なくシンプルにそしてこの上なく鋭く示している。
「1」は「多」ではありえず「多」は「1」に翻訳できない。
考えれば英語もフランス語も、現代ヨーロッパ語には単数形と複数形しかない。
ある意味アレントの政治と哲学の対立は、現代ヨーロッパ語のある種の特徴である「1と多」しかない世界を翻訳している、ともいえる。
しかし(ここから注目!)
実はアレントは、哲学者は一人で思考するんだけれども
「思考とは自分自身との対話、声なき対話」
なんだとも言う。
プラトンの『ゴルギアス』の表現を引用して、アレントは「私が私自身と対話すること」あるいは「一者における二者の経験」ということを言う。Two in one なんだかシャンプーみたいだが(笑)。
一者における二者の経験、それが思考だ、とアレントは言うのだ。
solitude(孤独)とlonliness(寂しさ)の対立(國分さんの訳)
lonliness(寂しさ)は、自分が自分自身と一緒にいられない状態のこと。
私が私自身と一緒にいられないから誰かを求めてしまう。
solitude(孤独)は、私が私自身と一緒にいる状態。
と考えられる。
アレントは、『全体主義の起源』の中で、さみしさ(lonliness)というのは人間にとってもっとも絶望的な経験である。だから、寂しさの中にある人間は、多くの場合だれか一緒にいてくれる人間を求めてしまう……と指摘している。
『自由とは何か』からの引用
「孤独における一者の内なる二者(two in one of solitude)は思考過程が始まるための条件だ」
まさしくこの two in oneというのがものを考えるための絶対条件であるという。
そうすると、一見したところ「1と多」って区別を非常に根本的なところにおいて、強烈にそれを対立させて政治と哲学を対立させてみせるという思想に見える。
しかし
意外と肝心なところでもう一つ別の数のカテゴリーを導入していて、それが「2」じゃないかと思う。
「2」っていうのが実はこっそりとアレントの本の中に書き込まれているって感じがする。
しかもこの「2」は哲学と政治という対立する二つの活動の、その根本的対立を乗り越えていくときに非常に重要な意味を持ってくるのではないか。
どういうことか。
哲学というのは政治と基本的に対立していて折り合いがつかない。
しかし、
哲学者には実践の領域に入り込むための道が一つだけ残されている。
とアレントはいう。
僕はこれ非常に感銘を受けたんですけれども、読んでいて。で、
この実践の領域に入っていくときに、実は「2」っていう数字が役に立つ。
重要な役割を果たす。
どういうことか?
哲学の真理は「1」としての人に関わるもの。
で、本来的に非政治的。
つまり真理っていうのは「1」のままでは全く実践的に何の力もない。
じゃあこれをうまく多数者に関わらせればいいんじゃないか、っていう発想が出てくる。
つまり、真理を多数者の同意の対象にするということ。
真理を同意の対象にする。しかし、これはアレントが「政治と真理」の中ではっきり言ってる。ダメ。
多数者が真理に同意することはあり得るけれども、その多数者は今日は同意しても明日は同意しないかもしれない、と。
つまりそのとき真理はその性質を変えてしまう。
同意を求めると、それは単なる意見になってしまう。
だから真理を同意の対象にすることはできない。
じゃあ真理は、哲学者は、実践の領域において何の役割も果たせないのか?
でも一つだけやり方があるってアレントは言う。
それは何か?
(ソクラテスのことを念頭に置いて)哲学者が自らの生、自らの生命、自らの命ですね、それをその真理に賭けて、その真理を範例にすることだ、とアレントは言う。
それはここに関わる。
ソクラテスは『ゴルギアス』の中で不正を行うより不正を被る方がよいっていう命題を真理として出す。
ところがこの『ゴルギアス』という対話編は、最終的にカリクレスっていう相手をソクラテスが論破できない。
負けちゃう。
ほんと読んでると、カリクレスが「またこいつくだらねえことをいってる」とかそういうことが台詞として書き込んであって、ソクラテスはカリクレスを全然論破できない。
最後ソクラテスは負け惜しみのように「死後裁きにあう」みたいな話をして終わる。
「おまえたちそんなことをいってるけど生きてる間に悪いことすると将来死んだ後に罰を被るからな」っていうことを、ミュトスとかかっこつけてしゃべるが、結局現世でどうだとか話はできない。
ここ「真理」をソクラテスはどうしたかというと、ご存じの通り
「国法を破るっていう不正を行うよりは、私の冤罪を冤罪として冤罪でも受け入れる」
という、不正を被る方が良いっていう形で死刑宣告を受け入れることで、逃亡できるにもかかわらず逃亡しないということで、命をかけた行為によって一つの範例にすることになる。
つまり、人生をそれに賭けることによって、真理を範例にして、これによってこそ、これによるときのみ哲学者は実践の領域に踏み込むことができて、…とアレントは言うわけだ。
「哲学の真理が範例という形に表されることが出来る場合にのみ哲学の真理は実践的となり、政治の領域の規則を侵さずに行為を鼓舞できる」アレント
アレントは上のように哲学者に対して非常に厳しい。
しかし哲学者には慰めがある、とアレントは同時に言う。
「哲学者はいつも自分自身を同伴しているという考えに慰められる」(『人間の条件』より)
つまり哲学者ロンリネスではなくソリチュードの中に哲学者はいる。
それがあるから、哲学者は哲学と政治の対立を越えて実践領域へと赴くことができる。
(これをいっただけじゃ「ふうん」って感じかもしれませんけれども<國分せんせ>)
アレントはこれを別の人物像と比較している。
ナザレのイエス。
アレントはイエスについて語りながら、「善行を行う者」についてずっと論じている。
「善」は特殊だ、と。善は見られたり知られたりした途端、ただ善のためになされるという善の特殊な性格を失ってしまう。だからあの人はいいことをした、と思われたり、自分はいいことをしたと思った瞬間に、「善」ではなくなる。行為者ですらそれに気付かないときのみ善は存在するというふうにアレントは強調する。
だからここからイエスの有名な「右手のしていることを左手に知らせるな」っていう教えが出てくるのだという。
」つまり善行というのはそれがなされた途端にすぐに忘れられなければならない。
ロンリネスの中でも絶対的なロンリネスの中にいなきゃいけない。人間にとってもっとも絶望的な経験である寂しさの中になんとしても留まらなければならない。
しかし、アレントはここには矛盾がある、という。
善行は他人のためになされる。だから善行を行う者は必ず人々と共にある。ところが、善行を行う者は善行を見られてはいけない。それどころか自分がしている善行を安心して自分で目撃することもできない。ここでアレントはこういう。私(國分さん)が一番好きなフレーズ。
「
善行を行う者が生きねばならない寂しさ(ロンリネス)というのは、多数性という人間の条件にあまりにも矛盾している。だから長時間にわたってはとてもそれに耐えられない。それが人間存在を完全に滅ぼしてしまわないためには、善行を目撃する唯一の想像上の証人、神の同伴を必要とする」
つまり善行を行う者は、それをつきつめていくと神様をどうしても要請せざるをえない。超越的な存在を要請せざるをえない。だからこそある意味でkろえは神との二者関係がそこに現れるということだ。
まとめ。
哲学者はつねに「2」に分裂している。
それに対して善行を行う者は絶対的な「1」であるがゆえに、逆説的に超越的存在者との二者関係に入っていく。神だけが彼の行いを目撃する。
我々は最初に「多」と「1」として政治と哲学を定義したけれども、今ここで対立されているのはいわば哲学と宗教の対立で、ここでは違った仕方で「2」というのが両方で問題になる。思考における「2」と超越者との関係としての「2」。
だから、実はこの「2」っていうのは重要なところで役割を果たしているのではないか。
最後の結論の話。
一見したところ、アレントの思想っていうのは「1と多」という非常にオーソドックスな対立のもとにある。
オーソドックスというか、現代ヨーロッパ語が「1と多」というのを基本的カテゴリーにしている。
しかしアレントは政治と哲学を対立させるときは「1と多」だが、哲学と宗教を対立させるときには、いわば逆説、ちょっと変わった仕方で「2」という数字を実は取り上げている。
で、ここをまず一つ強調したい。ここから僕(國分さん)の論点。
僕が問いたいのは、アレントが問題にしているのは本当に「2」なのかということ。
哲学者の二者性っていうのはあくまでも一者が分裂したそれではないか。
アレントは、考える人にとって自己欺瞞っていうのは一番やっちゃいけないんだっていうことを「真理と政治」の中で言う。しかし、これもダイアローグというよりはモノローグ的な感じがする。
さらにいえば、善行を行う者と絶対者との関係っていうのも、これを二者関係といっていいのか(まあ言ったのは僕なんですけれども)。
絶対者との二者関係って、これを「2」というのは無理があるって感じがする。
何がいいたいかというと、「1対多」は現代ヨーロッパ語が依拠する基本的カテゴリー。
だが、多くのインドーヨーロッパ語には「双数形」という形がある。dual。
このdualをなんとかして政治理論に持って来れないか、ということが言いたい。
言い換えればアレントに欠けているのはこのdualではないか。
「いや、愛の問題があるから欠けてないよ」というつっこみもあると思うが、それは今日措く。
少なくても政治と哲学の関係を論じるときに、何かdualっていうことにアレントが「触れてるんだけど触れてない」そんな気がする。
「準2」というかそういうのだけが働いていて、本当にdualな「双数形の世界」に触れているようで触れていないようで、もしかしたら触れていうるというような、そういうのがアレントの中にあるんじゃないか。
アレントは「1と多」というカテゴリーにすごくこだわり、「2」が持ってる可能性にこう非常に厳しく目をつぶって議論を組み立てている。だからこそむしろ、「1と多」に「2」を持ってくることでアレントの論の枠組みをもうちょっと違う形で展開できないか?
ここまでいくと全くアレント研究でもなんでもないが、こういう風に考えてみたいと思う。
それを考える上ですごい大きなヒントが、アレントの哲学者と善行を行う者との対立にあると思う。最後「オレの話」になってしいまったが、こんなことを今考えている。