南岳からは右側の福島県側が
切れ落ちているので
慎重に、歩くのに専念して
写真を撮る余裕はありません。
*
忠右エ門沢カッチに着いて
進む方向に鬼ガ面山と
通った道の南岳方向の様子です。

稜線には細かい凹凸があり、それが
鬼のパンチパーマのような髪の毛を
連想させたのでしょうか?

Ⅴ

尖ったカッチと対照的に
鬼ガ面山の山頂は
お椀を伏せたような
穏やかな形状でした。

ゆっくり歩いて南岳から
40分で山頂に到着です。

*
南岳からの往路全体と
その奥に田子倉湖が
少しだけ見えています。

浅草岳方向は
藪に隠れてよく見えなかったので
少し先に進みます。
Ⅴ

左側に北岳が現れ
写真奥の右が浅草岳の前岳
写真中央にカヘヨノポッチ
遠く霞むのは守門岳です。
*
鬼ヶ面山の山頂を振り返ると
やっぱり凸凹です。

*

北岳の手前に小さなピークがあり
北岳までは、かなり下ってまた上るので
ここで戻ることにしました。
*
北岳の全貌

*
だいぶ近づいたので
裾野を広げ大迫力の浅草岳

Ⅴ
鬼ヶ面山の山頂に戻って
昼食の大休止にしました。
*
視界に入る山並みは
浅草岳のときとほとんど変わりません。
AR山ナビにて
まずは浅草岳

*
その右に
磐梯山と吾妻連峰
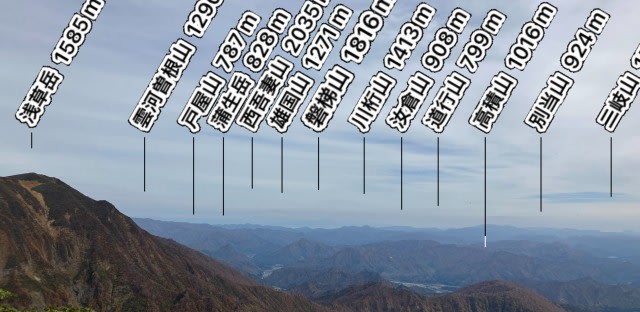
時間がお昼になってしまったので
だいぶ霞んでしまいました。
*
南岳の方向に燧ケ岳

(ここではちゃんと表示された)
その右に平が岳
山名が少し左寄りです
調整が不十分でした。
*
南南西に越後三山
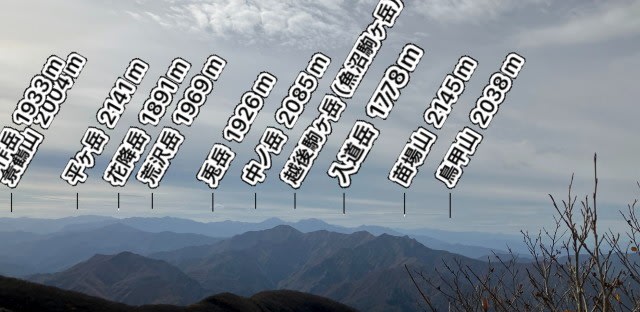
越後駒ケ岳・中ノ岳・八海山
入道岳は八海山のことです
Ⅴ
北岳方向の散策を含めて50分ほどで
鬼ヶ面山を後にします。
*
帰り道の
忠右エ門沢カッチ方向

*
南端の南岳は
きれいな円すい形の展望台です。

*
南岳には存在感のある
鬼の面のような石がありました。

Ⅴ
南岳から下はまっすぐで
一定の勾配で下る
のどかな山道です。

*
帰り道の方が紅葉が目に付くのは
視点が高いからでしょうか?

遅い秋を楽しめました。
Ⅴ
ヤマレコにて
移動距離:9.4㎞
累積標高差:936m

上り:登山口→〈0:20〉→六十里越→〈1:20〉→南岳→〈0:40〉→山頂
下り:山頂→〈0.30〉→南岳→〈0:50〉→六十里越→〈0:20〉→登山口
*
この日の歩数:19511歩
Ⅴ
急いで帰る必要がなかったので車で
六十里越トンネルを抜けて
田子倉駅跡に近い無料休憩所で
浅草岳を見上げてきました。

六十里越トンネルからここまで
人家はなく、道路脇に車を止めて
山の紅葉を眺める観光客が
大勢いました。
駅があったということは
以前には住んでいる人がいた
ということでしょう。
今はグーグルマップで見ても
痕跡は確認できません。

*
誰にも会わなかった山行だったので
日帰り温泉に寄ってみました。
寿和温泉

入場料700円
食べ物は販売されていませんので
銭湯に近い形態のところでした。
露天風呂はそよ風が気持ちよく
温まりました。

Ⅴ
Ⅴ
1週間前の浅草岳からの
鬼ヶ面山の写真を見直して
山名を入れてみました。

記憶が二重に刻まれ
忘れられない山になりました。
Ⅴ
end




























































































































































