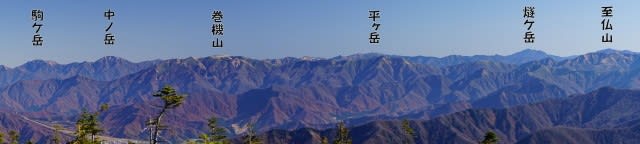揺れずに咲く花がどこにあるだろうか
この世のどんなに美しい花も揺れながら咲くのだ
<ト・ジョンファン>
苗場山の山頂湿原は
誰がどこから撮っても皆
同じような写真になります。
*
雲ひとつない秋の空
草の勢いが弱ったせいか
少し盛り上がった山頂付近が
わかりやすく
ツートーンの秋色も趣があります。
*
朝の冷え込みが池塘の池を
凍らせていますが
まぶしい太陽と
昼の暖かい空気は心地よく
2つの季節が両立しています。。
*
山頂を示す木柱の周辺は
何が変わったかはわかりませんが
以前よりすっきりした感じです。
2回目ですから、遠くから見るだけにして
ウッドデッキのベンチに腰掛け
お昼にしました。
∨
少し体力と時間に余裕があるので
9月には赤が混じった紅葉がきれいらしい
小赤沢方向を探索します。
木道の先に見える黒い山が
日本二百名山の佐武流山で
そのすぐ右奥に
浅間山が煙を吐いています。
∨
北アルプスの山々は一足早く
白い塊となっていました。
写真右側の白馬岳の手前の黒い山は
しんどかった高妻山です。
∨
キリがないくらい景色が変わらないので
時間の都合上、この辺で
帰路につくことにしました。
唯一、9月下旬の
ツツジが赤く紅葉する頃が
最も華やかな季節らしいので
3度目があるならば
その頃にしたいと思います。
∨
上り:4時間
下り:2時間30分
この日の歩数
28991歩
山頂湿原を散策したので
歩数が多くなっていますが
魚沼駒ケ岳ほどの体力は
必要ありません。
∨
帰りに
街道の湯を併設する
道の駅みつまたにて
今年最後のソフトクリームを
外で食べると寒そうなので
室内の食事スペースで
いただきました。
*
窓の外には足湯もあります。
end
苗場山は神楽ケ峰が遮って
街道から見ることができません。
股スリ岩から程なく
神楽ケ峰(8合目)に到着し。
ようやく苗場山の山頂が見えました。
冬には白く輝いて見える雪も
この日は
初雪から日数を経て
土が混ざってしまい
純白の雪という訳にはいきません。
∨
富士見坂を下り
雷清水から雲尾坂を見上げ
お花畑
9合目(鞍部)と進めば
最後の急登=雲尾坂です。
誰が名付けたのか
何が雲で、
何に見立てて「尾」なのか
趣があり印象に残る名前です。
*
ここまで登山道は
木道や木製階段で
登りやすくなっていましたが
雲尾坂は
雪が凍って緊張が続き
鎖やロープの助けもありません。
*
念のために持ってきた
アイススパイクは
2年前に買ったものです。
アイゼンよりかなり軽量で
踏み固められた雪が凍っているときに
足元がかなり安定します。
今回使用した後、残念ながら
スパイクが2つ外れたので
新しいものを買わなければなりませんが
2シーズン使用しましたから
価格と性能に不満はありません。
∨
雲尾坂の真下から仰ぎ見ると
坂の中央にある2つのコブが
重なり合って見えます。
初めは右方向の階段を上り
半分ほどの高さを稼ぐと
雲尾坂の中ほどにある
尾根にある1つ目のコブから
神楽ヶ峰を振り返り
*
進む道は2つ目のコブへ
*
2つ目のコブから
下を覗きこむと
1つ目のコブが
だいぶ下に見えます。
高度感があり
じっとしていると
クラクラします。
*
行く道は
人ひとりの幅しかありません。
雲尾坂は突然
平坦な木道に変わりました。
∨
最終回につづく
和田小屋からゲレンデを横切り
登山道に入ると北斜面になり
空気がひんやりとして
足元は霜で滑りやすく
自分が動くことで向ってくる
空気が冷たいので
ときどき止まって休みます。
緑の葉も白くデコレートされ
冷凍庫に入ったようです。
樹々の間から魚沼の里が見えると
まだ霧に覆われていました。
*
緑の葉が茂っていれば
普通に通り過ぎるはずの
日が当る斜面には
ダケカンバの白い幹や枝が
血管のように広がり
1ヶ月前には
朝日に映える黄色い紅葉が
登山者を楽しませたことでしょう。
∨
現在地を示す標柱はまだ新しく
わかりやすい所にあります。
6合・7合・8合9合の他に
6合半とか7合半とか
小さく刻んでありましたが
この道は
下ノ芝・中ノ芝・上ノ芝と
わかりやすい休憩地があるので
頼りにする必要は感じません。
*
下ノ芝
傾斜した小さな草地です。
板敷きでベンチのある
広い休憩スペースがあります。
登山口から1時間20分くらいですので
ちょうどいい休憩地ですが
展望はほとんどありません。
*
中ノ芝
下ノ芝から樹林帯を30分ほどで
笹が広がる斜面が現れ
展望のよい場所に
板敷きのスペースが設けられています。
*
快晴の朝での絶好の展望は
カメラもしっかり解像してくれました。
<北>
*
<東>
白毛門から平標山までの
横から見たS字形が
きれいに見えています。
*
*
上ノ芝
*
帰りの上ノ芝より
∨
日陰に雪が残る木道も
傾斜が緩やかとなり
最初のピークが近づいてきました。
*
股スリ岩
5年前は階段がなくて
皆さんが岩にまたがって通ったので
小さな渋滞になっていました。
*
正面に見えるピークが
神楽ケ峰だと思います。
今はりっぱな階段ができて
名前だけが残りました。
∨
つづく。