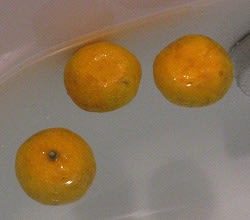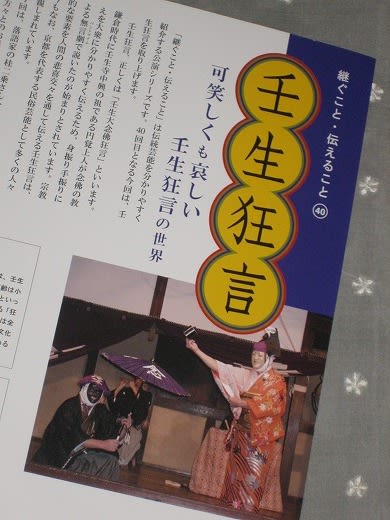おや、オバマ次期大統領もサンタの服装で応援ですか。


12月23日(天皇誕生日祝日)は天候も回復し好天になりました。
鴨川の河原で「サンタクロースマラソンin京都」(第7回だそうです)が開催されました。純粋にボランティア企画の模様です。
沢山のサンタさん、友人たちや家族で走ったり歩いたりしていました。
安全と準備の都合で事前申し込み120人限定なので、そんなに大勢ということはなかったですが、どこかユーモラス。
いいですね、不景気を吹き飛ばして、健康を増進しましょう。


この写真は、四条大橋から三条の方向です。



12月23日(天皇誕生日祝日)は天候も回復し好天になりました。
鴨川の河原で「サンタクロースマラソンin京都」(第7回だそうです)が開催されました。純粋にボランティア企画の模様です。
沢山のサンタさん、友人たちや家族で走ったり歩いたりしていました。
安全と準備の都合で事前申し込み120人限定なので、そんなに大勢ということはなかったですが、どこかユーモラス。
いいですね、不景気を吹き飛ばして、健康を増進しましょう。



この写真は、四条大橋から三条の方向です。