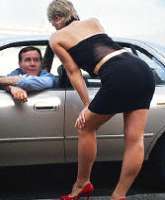久しぶりの最高裁での違憲判決です。
「国籍法は違憲」婚外子10人に日本国籍 最高裁判決
(2008年6月4日(水)20:57 朝日新聞)
国籍法の2条1号によれば、父母が結婚していない「婚外子」でも、生まれる前の段階で父の認知があれば、国籍を取得できる。一方、国籍法3条1項は、生まれた後に認知された場合に父母が結婚しなければ国籍を得られないと定めている。その違いは、出生の時点で子どもの国籍をできるだけ確定させるのが望ましいという考え方による。
この国籍法を違憲と判断したのは15人の裁判官のうち12人。このうち9人が多数意見で、「84年の立法当時は結婚によって日本との結びつきを区別することに理由があったが、その後に国内的、国際的な社会環境の変化があった」と指摘。その例として、家族生活や親子関係の意識の変化や実態の多様化、認知だけで国籍を認める諸外国の法改正を挙げた。
遅くとも、原告たちが国籍取得を法務局に届け出た03~05年には、結婚を要件に国籍を区別するのは不合理な差別になっていたと認定。3条1項のうち結婚の要件だけを無効にして、要件を満たせば国籍を認めると結論づけた。
この制度自体を知らなかったのですが、言われてみれば、認知と出生の前後関係で父母の婚姻を要件とするかしないかを変えるのはあまり合理的な理由がないように思います。
件の国籍法はこうなってます。
(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
(準正による国籍の取得)
第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
どうやら国籍法の2条1号が父「又は」母の一方が日本国民であれば出生時の父母の婚姻を要件としていないのに対し 3条1項は「父母の婚姻」と「及び」「認知」が条件になっているようです。
そしてこれは民法の嫡出子の規定からきているようです。
(準正)
第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
ということはつまり嫡出子でなければ国籍を認めない、というのは違憲だ、と言っていることですね。
今回、親子関係・国籍をめぐる変化があったと認めた期間は84年の立法当時から24年で、今までの最高裁の尺度でいえば比較的短いという感じもしますが、最高裁の時計も若干早くなったのでしょうか。
そうすると、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1であるという民法900条4号についてはの従来の合憲判断(参照)も変わる可能性が高くなったということでしょうか。(少子高齢化が進み、年金も破綻に瀕しているなかであえて日本国籍を持ちたいと思う人は歓迎すべきなどという判断をしたわけじゃないと思いますので。)