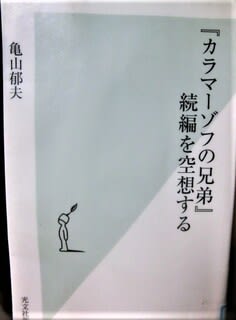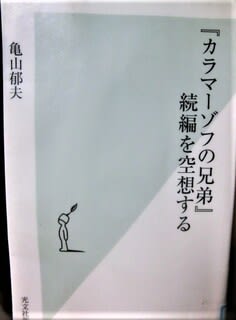
光文社の新訳シリーズの翻訳を手掛けた亀山郁夫氏による『考察』と恐らく、続編は、こんな内容になったのではないか?という、かなり納得な内容でした。
私は最初、小説のような形式で書かれているのかと思ったのですが、そうではありませんでしたが。
続編を空想する上でのポイントがいくつかありますが、大きな鍵を握っているのは、『序文』
「私の主人公アリョーシャは、たいした男ではない」と序文にはありましたが、1巻から5巻まで、全編を通して読み終えるまでもなく、1巻のみ読み終えた時点での私が、ブログに何と感想を書いたかといえば、
「まるでカオス状態。多くの登場人物の中で、アリョーシャだけが、唯一、まともだ。」でしたよね。
実は、ドストエフスキーがなくなった 直後、ロシアでは、
「第二の小説では、アリョーシャが皇帝暗殺に関わる筈だったらしい」と噂になったとか。
しかし、序文を見る限り、たとえ未遂で終わっても、皇帝殺しに関わる人の名が無名な訳がない、だから、アリョーシャは関わっていない、というのが亀井氏の意見。私もそう思います。あの天使のようなアリョーシャが、皇帝殺しだなんて...その後の13年間に何があったとしても、そこまで人格が変わるだろうか? どう転んでも...というのが感覚的に思うことです。
亀井さん曰く、「結論から述べる。恐らくアリョーシャが皇帝暗殺者そのものとして名をはせることはなかった。序文にいう、「彼は有名ではない」がその動かぬ証拠である。そしてその実際の役割は、コーリャ・クラソートキンが担う。」(138ページ15行目~139ページ2行目)
コーリャ・クラソートキン。アリョーシャに認めてもらいたくて、背伸びをしつつ会話していた、そして動物虐待など、残虐な面がある、あの少年ですね。
実際、最後の5巻の最終章では、アリョーシャと12人ほどの子供達が、将来の誓いを立て、話し合う場面で終わります。あの中で、少年達は爆弾を作り、(おもちゃのような、という断りはありますが)試してみたり、コーリャが線路に寝そべって、列車が走ってきても逃げずに寝たままでいられるか!?肝試しのようなことを過去にしたことがある、という話題が出てきたり...
どうして、こういった話が、最終章のここで、語られなければならないのか?違和感は確かに残りはしました。 亀井氏が 将来、イエス・キリストの弟子の同じ数の12人の子供達(この日、亡くなった少年一人を含む)が皇帝殺しに関わっていきますよ...という暗示だろうと、指摘されて、ああ、そうか!と納得。
当時のロシアでは、皇帝や政府高官を狙ったテロが相次ぎ、皇帝が乗った列車が通ることを予想して、線路に爆弾を仕掛けたテロがあったそうです。未遂で終わったそうが。ドストエフスキー自身、一度は有罪判決を受け、死刑を宣告されているものの、皇帝による恩赦で死刑は免れた経緯あり。
「一度は死んだ。そして恩赦により、生き返った」という自らの体験を踏まえた「第二の小説」となって当然という気がします。
第一の小説のテーマの一つは、「父親殺し」
書かれなかった第二の小説のテーマは、「皇帝殺し」
そして~小説全般を通して大きなテーマとしてあるのが、キリスト教。
このキリスト教。宗派が沢山あり、ロシアの場合は、どうなっているのか、全く知らなかったのですが、例えば、イワン・カラマーゾフの世界観は、
「Anti-cosmic dualism 「反宇宙的二元論」とは、悪や罪といった否定的なプロセスが存在する限り、この世界は認められないとする、実存的な立場」だそうです。(204ページ3~4行)
一方、「アリョーシャのキリスト教観は、汎神論とも通じ合う、大地信仰がまじりあっていた。元々ロシア正教そのものが、スラブ異教の地に外部からもたらされたことから生じた二重信仰(異教的要素たぶんに含んだキリスト教)に起源があった。」(204 7-9行目)
更には、ドストエフスキー自身の世界観は、きわめてラディカルな終末論で、教会を介さず、直接的に神を体験すれば、また大地や自然との一体化という神秘的体験があれば、それだけで神を信じたことになるという、(日本の神道のようですね)ラディカルな感性である」(204 11-13行目)
人は生まれながらに悪であり、罪びとである、という考えに違和感がある私には、イワン・カラマーゾフの立場も分かる。また、自然豊かな日本も大地信仰というより、自然そのもの、二重信仰というよりは多重信仰なので、アリョーシャの世界観も分かる。最後に、ドストエフスキー自身の世界観は、最もしっくりくる。
232ぺージ12~13行目には、「人間中心の西欧のキリスト教とはおよそ異なった、東方キリスト教に共通する独自の世界観を見てとることができる。」
森羅万象の調和。我々日本人に、最もしっくりくる世界観かもしれませんね。
ドストエフスキーは、世界が「個々のばらばらな部分」(第1巻10ページ)に分断され、孤立する中で、人類は一致して この世界観(東方キリスト教的世界観)を取り戻さねばならない、
「神のためならテロも許される」という過激思想に走った(かもしれない)コーリャたちを諭す役目をアリョーシャに託したのかも。ちょうど現代のように、なんたらファーストで分断されつつある世界や言論の自由を許さない覇権国家を見ていると、ドストエフスキーと親しかったロシアの哲学者、ゾロヴィヨフがいう、「分断」から「統合」へ~ という思想を「カラマーゾフの兄弟」「カラマーゾフの兄弟と子供達(第二の小説)」で伝えたかったのかもしれない、という亀井氏の空想も納得です。