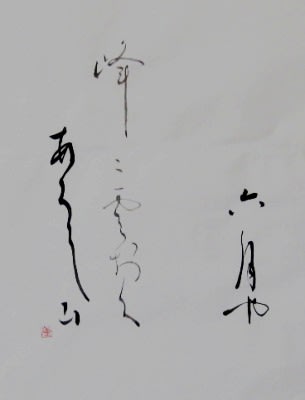
六月や 峰に雲おく あらし山(芭蕉)
(高木厚人先生の教本から臨書 半切1/3)
ここ数週間“奥行き感”なるものにこだわってまいりました。
昨年高木先生の“大字かな”関連の教本で、書道における奥行き感とか立体感という言葉に初めて出会い、
書道にもこんな概念があるのかと驚きもし、新鮮さを感じたことでした。
しかし、今一理解できずにおりました。
しからば墨絵でその雰囲気を探ってみようと、富士山の雑木林、そして松林とこれを試してきました。
そしてあらためて教本を読み返しました。
これらを通して、ほんの入り口でしょうが、書道の奥行き感とはこんなものなのかな、と感じております。
教本には色々な箇所で奥行き感について触れられていますが、この一枚を書かせていただきました。
“峰”を遠く高くに置き、全体としてみた各行の配置や流れ、余白のとり方、
そして墨の濃淡・潤渇、太細など大いに参考になりました。
また、あらし山の“あ”の字。
角張ったその力強さ、そして“あ”の中の各画線が“峰”に集中しているように見えます。
これも計算されてのことでしょう。
かって、ルノアールの“ピアノによる少女たち”を模写しました(2011.06.02付拙ブログ)が、
その原画は背景のカーテンまでを少女たちの真後ろで束ねて、絵全体を彼女たちに集中させていました。
自分はこのカーテンを結ばず、無神経に、縦長にシャーシャーと書いてしまい、
逆に集中するということはこういうことかと勉強になりましたが・・・。
更には何気ない“や”の字の右肩下がり。
これも作品全体の奥行き感を出すとともに、この部位だけでも見事なバランサ―役を果たしているのでしょう。
書道の専門家の方にとられては、何を驚いているのだと思われるかもしれませんが、
私にとっては、奥行き感というものについて、大きなエポックとなる一枚でありました。
























