
何となく自然の流れで今冬の活動は冬篭りモードに切り替わってしまっている。
今冬は何を主眼にしようかな?と色々考えたが三角点も史蹟も道祖神も
種が尽きている感じで新資料も手に入っていない。そこで中途半端に
なっている県内七福神を題材にすることにした。
県内七福神と云っても調べて見ると結構多彩であった。
先ず、通常の七福神は九つ、それに榛名神社のように一箇所の施設内に
纏まっている「一箇所七福神」が七つ、更には「ミニ一箇所七福神」と
称する単体のもの・小型のものが二十もあった。
取り敢えず手の届く範囲から訪ねるが、その中で既に探訪済みの場所も
鏑川・小幡・麻芋・八塩と数箇所あるし、他の目的だった為、完全ではない
類に榛名山や山徳記念館がある.
今日の目標は地理不案内の桐生七福神だか宮本町から梅田町に亘る推定6kmの
範囲に南北に並んでいるから何とかなりそう。
先日の大間々行きと全く同じく前橋市街地を抜けてR-50をひたすら東進、
「鹿」信号でr-69へ左折して間も無くr-122に合流して赤城駅の僅か先の
「大間々六丁目」で右折、桐生合同庁舎前を左折してr-3に乗り換え
両毛線桐生駅前で左折、上毛電鉄終点の西桐生を左に見て小曾根信号の二つ先で
左折、小さな四つ角を細道へ左折して「光明寺」。
(1)「光明寺」
桐生七福神第一番の弁財天を祀る光明寺は、東上州三十二番札所という名刹で
山号を「大慈山」、千手観世音菩薩をご本尊とする曹洞宗。
駐車場から直ぐにこの石段で山門に登っていく。丁度、花を携えた親子連れが
元気よく登っていったので負けずに後に続く。

山門右には阿形金剛力士像が

左には吽形金剛力士が出迎えるのでこんな「仁王像」があるから仁王門と
云う事かな?

山門を潜ると更なる石段の上に本堂。

六地蔵前ではさっきの親子が花を供えていた。

目標の弁財天は良く目に付く位置に配置されていたが下の写真で左の宝珠型をした仏塔がそれ、
高さは1mもないがこれが弁財天像。
その右にある琵琶を手にした大きな弁財天石像は『桐生七福神』誕生後の建立なので
本命ではないがどう見てもこっちが分り易いな。

本堂前のこの大きな立像は水子地蔵像。

近くに十三重塔が目立つが同型のものを七番目の西方寺でも見ることになる。

(2)「妙音寺」
光明寺から一旦は広い道に戻って東北への道を進み西久方町で細道へ左折。
壽老人を祀る妙音寺の山号は「平等山」、高野山真言宗のお寺。
妙音寺入り口

周りには多数の庚申塔群が並ぶ。

定番の六地蔵。

子育て地蔵尊。

青面金剛王

目当ての寿老人。寿老人は、とかく福禄寿と混同されがちと言われるが確かに
両福神ともに長い杖を持ち、巻物を持ち、長い頭で白いあご髭を有している姿
だからそれも已むを得ないが寿老人は下の写真で明確に確認出来る様に足元に
『鹿』を連れているからそれが両福神を見分けるポイントーーとは某サイトからの
完全な受け売り。

何故、そこにあるのかは知らないが句碑が一基。
阿里志日の(アリシヒノ) 面影しのび 墓参可南(ボサンカナ) 翠 堂

本堂前に十一面 観音と如意輪観音の二体を脇侍とする、珍しい不動三尊仏があった。
不動三尊仏は、 矜羯羅(コンガラ)童子と制多迦(セイタカ)童子が並び立つ
通常と聞いていたので珍しい三尊仏に対面した事になる。

不動明王をご本尊としている故か?この石碑。

太子堂。名前の通り聖徳太子像が祀られているのだろう。

(3) 法経寺
妙音寺から車道に戻って進み桐生工高先で細道へ左折。
大黒天をお祀りする妙光山法経寺は、身延山久遠寺を総本山とする日蓮宗のお寺。
寺に横から入ると手前に「大黒殿」という立派な建造物。これだと喜んで
近寄ったら「大黒天」はこの堂の中に安置されているので外から拝観の事」と
いう注意書きにガックリ。

ガラス戸が閉まっているのでガラス越しに撮ったが中は暗く距離もあって
どうやってもこれ以上は駄目。

仕方なく関係サイトから借用してこれが中にある大黒天だが「大黒殿」の
大きさを考えたら本尊は極めて小さい。

この隣に本堂。

日蓮宗の開祖・日蓮上人(1222-1282)の像。

その脇から石段。

登り切った左にこのお堂とその内部。


その右に「最上位青石稲荷大神」の掲額のあるお堂と内部。


(4) 青蓮寺(ショウレンジ)
再び車道で北上し、群大を右に見て天神町二丁目信号の手前を左に入る。
福禄寿神を祀る第四番札所・青蓮寺の山号は「仏守山義国院」で市内唯一の時宗のお寺。
まず、本堂。

福禄寿は地蔵堂の中に安置されているそうだが、お参りの目的の福禄寿神は、
山門と本堂との丁度中間にあたる参道の左側に建つ、日限地蔵堂内に祀られている。

このお堂に近寄ると「福禄寿」と「日限地蔵尊」の二つの掲額。

ガラス戸を開けて見られる福禄寿神は、豊かな髭をたくわえた像で、左手に
巻物を持ち、右手に杖をつき、満面 に笑みをたたえていた。
大きな長い頭部が印象的。

堂に向かって左側に一遍上人(遊行上人)の像。
一遍上人は、(1239-1289)に活躍した鎌倉時代の僧で、時宗の開祖。

墓地の入り口に「半僧坊大権現」と刻まれた石柱と、石の鳥居があり
半僧坊大権現への入り口で、鳥居をくぐりましたら左側へ入り、
石段を登ると、権現堂がある。

(5) 久昌寺
天神町二丁目信号でR-66に合流、GS手前の右側に九昌寺。
この寺は、桐生山鳳仙寺八世・応山牛喚大和尚が開創で
恵比須神を祀るが、曹洞宗では珍しい『不動明王をご本尊』とする寺。
本堂。

外にある恵比寿像。

恵比寿神の安置されているお堂。

恵比須神は、釣竿を持った右手を高々と挙げ、左脇には大きな鯛を抱え込んで
いる立像。

なでぼとけ

合掌小僧像

(6) 鳳仙寺
久昌寺から僅かに先の桐生女子高辺から看板で左折して暫くで鳳仙寺。
鳳仙寺は、1573年に桐生新領主となった由良成繁が、1574年に
自らの菩提所として伽藍を創建し開山した寺。
堂々たる入り口の石柱、本日見た中で最高の雰囲気。
長い参道には随所に駐車場所があるが一番下に駐車して参道を登る。

雨降り地蔵尊。
雨雲ひとつ見られない晴天の日だというのに、この地蔵尊の体が、まるで雨に
出会ったかのように濡れているということが、時々あったからとの伝承による。

鳳仙寺威徳の滝。右手の岩角に小さな石像が見えるが遠くて判別不能。

やがて前方に山門が見えた。

山門は巨大で重厚。
三間一戸楼門瓦葺入母屋造りで1704年の作。市指定重要文化財

中に仁王(増長天・持国天)がある。


潜って振り返ると左右に仁王の絵。


疣地蔵。
「山いもの実で数珠のような首飾りを作り、それを地蔵の首にかけ心を込めて
祈願をすると、体のイボを取り去っていただけるし心のイボ(悩み)
までも取り去ってくださるというありがたい仏様との民間信仰だが「地蔵」と呼ばれては
いるが、像は「薬師如来」。

毘沙門天像はガラス戸越しでしか見られない。なんとかしようにもこれで精一杯。

再び資料画像でみるとこんな様子。

(7) 西方寺
鳳仙寺から北への少しの細道伝いで最後の西方寺。布袋尊を祀る結願の寺で
臨済宗。1350年から1573年までの224年間に亘って桐生領を統治した「後桐生氏」
十代の領主の御霊を祀る名刹で『桐生氏の菩提寺』。
寺院入り口。

鐘楼

本堂

桐生七福神七つ目の布袋尊。

十三重塔の『桐生塔』
十三重塔とは、仏陀の舎利・遺髪・聖遺物などを納める塔で、釈迦の慰霊碑、
仏教のシンボル的な意味合いをもつとのこと。
西方寺の十三重塔は高さは20m、平成4年11月に落慶法要。

以上で第一回目を終了。実際の行動よりも事前の対象物場所の確認、経路の
検討等に時間がかかるし見学の主眼が七福神との意識が強すぎお寺をじっくり
拝観もせずに退出してしまう。追々方策を考える積り。
ご来訪の序に下のバナーをポチッと。
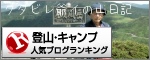
今冬は何を主眼にしようかな?と色々考えたが三角点も史蹟も道祖神も
種が尽きている感じで新資料も手に入っていない。そこで中途半端に
なっている県内七福神を題材にすることにした。
県内七福神と云っても調べて見ると結構多彩であった。
先ず、通常の七福神は九つ、それに榛名神社のように一箇所の施設内に
纏まっている「一箇所七福神」が七つ、更には「ミニ一箇所七福神」と
称する単体のもの・小型のものが二十もあった。
取り敢えず手の届く範囲から訪ねるが、その中で既に探訪済みの場所も
鏑川・小幡・麻芋・八塩と数箇所あるし、他の目的だった為、完全ではない
類に榛名山や山徳記念館がある.
今日の目標は地理不案内の桐生七福神だか宮本町から梅田町に亘る推定6kmの
範囲に南北に並んでいるから何とかなりそう。
先日の大間々行きと全く同じく前橋市街地を抜けてR-50をひたすら東進、
「鹿」信号でr-69へ左折して間も無くr-122に合流して赤城駅の僅か先の
「大間々六丁目」で右折、桐生合同庁舎前を左折してr-3に乗り換え
両毛線桐生駅前で左折、上毛電鉄終点の西桐生を左に見て小曾根信号の二つ先で
左折、小さな四つ角を細道へ左折して「光明寺」。
(1)「光明寺」
桐生七福神第一番の弁財天を祀る光明寺は、東上州三十二番札所という名刹で
山号を「大慈山」、千手観世音菩薩をご本尊とする曹洞宗。
駐車場から直ぐにこの石段で山門に登っていく。丁度、花を携えた親子連れが
元気よく登っていったので負けずに後に続く。

山門右には阿形金剛力士像が

左には吽形金剛力士が出迎えるのでこんな「仁王像」があるから仁王門と
云う事かな?

山門を潜ると更なる石段の上に本堂。

六地蔵前ではさっきの親子が花を供えていた。

目標の弁財天は良く目に付く位置に配置されていたが下の写真で左の宝珠型をした仏塔がそれ、
高さは1mもないがこれが弁財天像。
その右にある琵琶を手にした大きな弁財天石像は『桐生七福神』誕生後の建立なので
本命ではないがどう見てもこっちが分り易いな。

本堂前のこの大きな立像は水子地蔵像。

近くに十三重塔が目立つが同型のものを七番目の西方寺でも見ることになる。

(2)「妙音寺」
光明寺から一旦は広い道に戻って東北への道を進み西久方町で細道へ左折。
壽老人を祀る妙音寺の山号は「平等山」、高野山真言宗のお寺。
妙音寺入り口

周りには多数の庚申塔群が並ぶ。

定番の六地蔵。

子育て地蔵尊。

青面金剛王

目当ての寿老人。寿老人は、とかく福禄寿と混同されがちと言われるが確かに
両福神ともに長い杖を持ち、巻物を持ち、長い頭で白いあご髭を有している姿
だからそれも已むを得ないが寿老人は下の写真で明確に確認出来る様に足元に
『鹿』を連れているからそれが両福神を見分けるポイントーーとは某サイトからの
完全な受け売り。

何故、そこにあるのかは知らないが句碑が一基。
阿里志日の(アリシヒノ) 面影しのび 墓参可南(ボサンカナ) 翠 堂

本堂前に十一面 観音と如意輪観音の二体を脇侍とする、珍しい不動三尊仏があった。
不動三尊仏は、 矜羯羅(コンガラ)童子と制多迦(セイタカ)童子が並び立つ
通常と聞いていたので珍しい三尊仏に対面した事になる。

不動明王をご本尊としている故か?この石碑。

太子堂。名前の通り聖徳太子像が祀られているのだろう。

(3) 法経寺
妙音寺から車道に戻って進み桐生工高先で細道へ左折。
大黒天をお祀りする妙光山法経寺は、身延山久遠寺を総本山とする日蓮宗のお寺。
寺に横から入ると手前に「大黒殿」という立派な建造物。これだと喜んで
近寄ったら「大黒天」はこの堂の中に安置されているので外から拝観の事」と
いう注意書きにガックリ。

ガラス戸が閉まっているのでガラス越しに撮ったが中は暗く距離もあって
どうやってもこれ以上は駄目。

仕方なく関係サイトから借用してこれが中にある大黒天だが「大黒殿」の
大きさを考えたら本尊は極めて小さい。

この隣に本堂。

日蓮宗の開祖・日蓮上人(1222-1282)の像。

その脇から石段。

登り切った左にこのお堂とその内部。


その右に「最上位青石稲荷大神」の掲額のあるお堂と内部。


(4) 青蓮寺(ショウレンジ)
再び車道で北上し、群大を右に見て天神町二丁目信号の手前を左に入る。
福禄寿神を祀る第四番札所・青蓮寺の山号は「仏守山義国院」で市内唯一の時宗のお寺。
まず、本堂。

福禄寿は地蔵堂の中に安置されているそうだが、お参りの目的の福禄寿神は、
山門と本堂との丁度中間にあたる参道の左側に建つ、日限地蔵堂内に祀られている。

このお堂に近寄ると「福禄寿」と「日限地蔵尊」の二つの掲額。

ガラス戸を開けて見られる福禄寿神は、豊かな髭をたくわえた像で、左手に
巻物を持ち、右手に杖をつき、満面 に笑みをたたえていた。
大きな長い頭部が印象的。

堂に向かって左側に一遍上人(遊行上人)の像。
一遍上人は、(1239-1289)に活躍した鎌倉時代の僧で、時宗の開祖。

墓地の入り口に「半僧坊大権現」と刻まれた石柱と、石の鳥居があり
半僧坊大権現への入り口で、鳥居をくぐりましたら左側へ入り、
石段を登ると、権現堂がある。

(5) 久昌寺
天神町二丁目信号でR-66に合流、GS手前の右側に九昌寺。
この寺は、桐生山鳳仙寺八世・応山牛喚大和尚が開創で
恵比須神を祀るが、曹洞宗では珍しい『不動明王をご本尊』とする寺。
本堂。

外にある恵比寿像。

恵比寿神の安置されているお堂。

恵比須神は、釣竿を持った右手を高々と挙げ、左脇には大きな鯛を抱え込んで
いる立像。

なでぼとけ

合掌小僧像

(6) 鳳仙寺
久昌寺から僅かに先の桐生女子高辺から看板で左折して暫くで鳳仙寺。
鳳仙寺は、1573年に桐生新領主となった由良成繁が、1574年に
自らの菩提所として伽藍を創建し開山した寺。
堂々たる入り口の石柱、本日見た中で最高の雰囲気。
長い参道には随所に駐車場所があるが一番下に駐車して参道を登る。

雨降り地蔵尊。
雨雲ひとつ見られない晴天の日だというのに、この地蔵尊の体が、まるで雨に
出会ったかのように濡れているということが、時々あったからとの伝承による。

鳳仙寺威徳の滝。右手の岩角に小さな石像が見えるが遠くて判別不能。

やがて前方に山門が見えた。

山門は巨大で重厚。
三間一戸楼門瓦葺入母屋造りで1704年の作。市指定重要文化財

中に仁王(増長天・持国天)がある。


潜って振り返ると左右に仁王の絵。


疣地蔵。
「山いもの実で数珠のような首飾りを作り、それを地蔵の首にかけ心を込めて
祈願をすると、体のイボを取り去っていただけるし心のイボ(悩み)
までも取り去ってくださるというありがたい仏様との民間信仰だが「地蔵」と呼ばれては
いるが、像は「薬師如来」。

毘沙門天像はガラス戸越しでしか見られない。なんとかしようにもこれで精一杯。

再び資料画像でみるとこんな様子。

(7) 西方寺
鳳仙寺から北への少しの細道伝いで最後の西方寺。布袋尊を祀る結願の寺で
臨済宗。1350年から1573年までの224年間に亘って桐生領を統治した「後桐生氏」
十代の領主の御霊を祀る名刹で『桐生氏の菩提寺』。
寺院入り口。

鐘楼

本堂

桐生七福神七つ目の布袋尊。

十三重塔の『桐生塔』
十三重塔とは、仏陀の舎利・遺髪・聖遺物などを納める塔で、釈迦の慰霊碑、
仏教のシンボル的な意味合いをもつとのこと。
西方寺の十三重塔は高さは20m、平成4年11月に落慶法要。

以上で第一回目を終了。実際の行動よりも事前の対象物場所の確認、経路の
検討等に時間がかかるし見学の主眼が七福神との意識が強すぎお寺をじっくり
拝観もせずに退出してしまう。追々方策を考える積り。
ご来訪の序に下のバナーをポチッと。



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます