国語が得意科目になる「印つけ」読解法
著者 藤岡 豪志 (著)
出版社: ディスカヴァー・トゥエンティワン
ISBN-10: 4799318705
ISBN-13: 978-4799318706

前回の最後のカリテで国語のテストが最後まで行かなかった息子。
点数も・・・・びっくりでした。
答案は□六(四角六)の半分にもみたなかった。
しかし、この□六の正答率はどの問題もおおよそ40%以上ありました。
つまり回答できている子の正答率は高いと思っています。
わが子は設問が最後までいかない・・・・悩ましいです。
5年生、文章も長くなるでしょうし、平易ではなくなるようにも思います。
まず読めるようにしなくては・・・・・
そして読みは一回でピシッと読み込めるようにしなくては・・・・
さて、どうしたものか。
以前より気になっていた本を読んでみた。
表題の「国語が~」です。
これを読み、とりあえず息子に課したのは線を引いたり、丸をつけて読む!
この著者の本に書いてあるように、物語文ならば、説明・論説文ならば・・・、随筆ならば・・・とできるできないは
別にして、1回で読んで設問を呼んだときにヒントがあればすぐにそこから見つかられるから、とりあえず
このとおりになるべく印をつけてごらん!と話をしました。
まぁ話をするだけでできるようになれば苦労はしないのですが・・・。
当面答案直しなどの際には気をつけてみてあげる必要がありそうです。
やる気とスキル、スキルさえ身につければ何とかなるのか??
とりあえず何もやらないよりはやってみようという感じです。
それに息子には
・1回で集中して読む
・印をつける
・テストの時間配分を考える
の3つを話しました。
最後まで行くにはどうしたらいいか、□の大問がいくつで、□の漢字、語句にどれだけの時間が使えてと
少し考えてテストを受けるように話しました。
これを踏まえての2/10公開模試です。
がんばってほしいな~。
せめて最後まで解ききってほしいな~。
以下Amazonより
--------
Amazon 出版社のコメントからの抜粋
よく、「国語なんて勉強しても伸びない」と言う人がいます。
「子どものころから普通に日本語を使っているから、国語の勉強をしなくても60点ぐらいは取れるはず。
勉強をしても、70点ぐらいしか取れないだろうから、やるだけムダ」
と思っているのです。
しかし、それは違います。
本当は、100点満点を取れるのです。
では、あと30点分を伸ばすためには何が必要だと思いますか?
それは、「やる気」と「スキル」です。
このうちの「スキル」とは、どうすれば文章を正しく読み取れ、問題を正しく解けるのかという作法のことです。
具体的には、○印をつけたり傍線を引いたりしながら文章を読む「印つけ」の方法がメインになります。
「印つけ」というと、高校現代文のテストで点数を取るための「テクニック」というイメージがある方もいらっしゃいますが、
実は、文章を読むのが苦手な小学生が、文章をラクに読めるようになるきっかけとして非常にすぐれたものです。
本書では、単なるテクニックではなく、文章がラクに読めるようになるためのシンプルなメソッドとして、この「印つけ」をご紹介していきます。
------
ご照会されたわけです。
なかなか参考例は印いっぱいで、びっくりで息子はここまでは無理だろうと思うのですが・・・・基本的なことだけでも
身に着けて1回で精読する癖をつけてくれればと思っています。
さぁ公開!2/10 国語やいかに!!
^_^;あ、理科も相当ヤバいんですけどね。
著者 藤岡 豪志 (著)
出版社: ディスカヴァー・トゥエンティワン
ISBN-10: 4799318705
ISBN-13: 978-4799318706

前回の最後のカリテで国語のテストが最後まで行かなかった息子。
点数も・・・・びっくりでした。
答案は□六(四角六)の半分にもみたなかった。
しかし、この□六の正答率はどの問題もおおよそ40%以上ありました。
つまり回答できている子の正答率は高いと思っています。
わが子は設問が最後までいかない・・・・悩ましいです。
5年生、文章も長くなるでしょうし、平易ではなくなるようにも思います。
まず読めるようにしなくては・・・・・
そして読みは一回でピシッと読み込めるようにしなくては・・・・
さて、どうしたものか。
以前より気になっていた本を読んでみた。
表題の「国語が~」です。
これを読み、とりあえず息子に課したのは線を引いたり、丸をつけて読む!
この著者の本に書いてあるように、物語文ならば、説明・論説文ならば・・・、随筆ならば・・・とできるできないは
別にして、1回で読んで設問を呼んだときにヒントがあればすぐにそこから見つかられるから、とりあえず
このとおりになるべく印をつけてごらん!と話をしました。
まぁ話をするだけでできるようになれば苦労はしないのですが・・・。
当面答案直しなどの際には気をつけてみてあげる必要がありそうです。
やる気とスキル、スキルさえ身につければ何とかなるのか??
とりあえず何もやらないよりはやってみようという感じです。
それに息子には
・1回で集中して読む
・印をつける
・テストの時間配分を考える
の3つを話しました。
最後まで行くにはどうしたらいいか、□の大問がいくつで、□の漢字、語句にどれだけの時間が使えてと
少し考えてテストを受けるように話しました。
これを踏まえての2/10公開模試です。
がんばってほしいな~。
せめて最後まで解ききってほしいな~。
以下Amazonより
--------
Amazon 出版社のコメントからの抜粋
よく、「国語なんて勉強しても伸びない」と言う人がいます。
「子どものころから普通に日本語を使っているから、国語の勉強をしなくても60点ぐらいは取れるはず。
勉強をしても、70点ぐらいしか取れないだろうから、やるだけムダ」
と思っているのです。
しかし、それは違います。
本当は、100点満点を取れるのです。
では、あと30点分を伸ばすためには何が必要だと思いますか?
それは、「やる気」と「スキル」です。
このうちの「スキル」とは、どうすれば文章を正しく読み取れ、問題を正しく解けるのかという作法のことです。
具体的には、○印をつけたり傍線を引いたりしながら文章を読む「印つけ」の方法がメインになります。
「印つけ」というと、高校現代文のテストで点数を取るための「テクニック」というイメージがある方もいらっしゃいますが、
実は、文章を読むのが苦手な小学生が、文章をラクに読めるようになるきっかけとして非常にすぐれたものです。
本書では、単なるテクニックではなく、文章がラクに読めるようになるためのシンプルなメソッドとして、この「印つけ」をご紹介していきます。
------
ご照会されたわけです。
なかなか参考例は印いっぱいで、びっくりで息子はここまでは無理だろうと思うのですが・・・・基本的なことだけでも
身に着けて1回で精読する癖をつけてくれればと思っています。
さぁ公開!2/10 国語やいかに!!
^_^;あ、理科も相当ヤバいんですけどね。










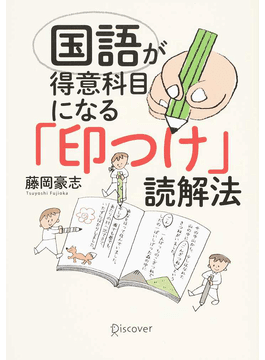
 と切実なる願いがふつふつと湧き上がります。
と切実なる願いがふつふつと湧き上がります。 苦手のままで苦労はさせたくないじゃないですか。
苦手のままで苦労はさせたくないじゃないですか。 テストで撃沈、沈没しているだけなんです。・・・・
テストで撃沈、沈没しているだけなんです。・・・・ それが問題なのですが。
それが問題なのですが。





 「もういい
「もういい 」と怒り出します。
」と怒り出します。
 「お母さんだって(お父さんだって)できてないくせに、注意しないでよ
「お母さんだって(お父さんだって)できてないくせに、注意しないでよ
 」と娘が起こります。
」と娘が起こります。


 必要だよ、少なくとも私には必要ないかもしれないけど、あなたが大人になる頃は
必要だよ、少なくとも私には必要ないかもしれないけど、あなたが大人になる頃は



 と鼻息が荒くなる私です。(笑)
と鼻息が荒くなる私です。(笑) って事もわかっているのですが・・・・
って事もわかっているのですが・・・・





