「灘→東大理III」の3兄弟を育てた母が明かす志望校に合格するために知っておきたい130のこと
佐藤 亮子 (著)
出版社: ポプラ社 (2016/4/20)
ISBN-10: 4591149900
ISBN-13: 978-4591149904
発売日: 2016/4/20

読みました。
(ーー;)財力がある人は違うわね~ってビックリでした。
三兄弟+長女で4人もお子さんがいて、灘に3人、洛南(長女)を入れて・・・・中受の塾は浜学園、灘に入ってからも大阪の
鉄〇会。
すごいです。
灘に通わせつつ、鉄〇って・・・・(>_<)
通学も奈良だったかな?から兵庫まで・・・
学校へ行って、塾へ行っての帰宅は23時とありました。
無理無理無理(@_@;)我が家には無理・・・・・
でも、庶民な私でも、これはうちでも小さいころからやってるよ!!というのは何個かありました。
しかし、お母さんが有名だと、、、ちょっとネット検索するとお子さんの顔写真とか、お名前とかも出ていたりと
少々怖いな~と思いました。
子どもが生まれる前から中受本とか読んで、熱心ぶりが半端ない。(*_*)
びっくりします。
ただただすごい!!の一言です。
そんな中でも共感した部分、我が家もやっているけどやっぱり続けようと思った部分を
留めておきます。
------
国語はやっぱり音読!
文中では小学生の時は親が音読してあげると書いてありました。
うちは新四年(現小3)(@_@;)まだまだ手取り足取りあたりまえと思った方がよさそうです。
ケアレスミスとは言わない!それはミス!!
著者の三男とまったく同じ悩みを抱えている我が家。
でも字が汚い=書道に通うというのは中受には必要ないと書いてありました。
親がつきっきりでおかしなところは直させる!!
これを1か月くらいつづけたら治ったと文中にでてきました。
(ーー;)そ、そんなには時間を避けない・・・かといって書道に通わす時間はない。
見てやれるときに見るしかないのですが、それでも治るかな~3ヶ月くらいかかっても今のうちに
なんとかしたいな~。
感銘した文章は
試験日の前々日までは「為せば成る」・・・そこまでは死ぬ気で勉強に取り組む
試験日の前日は「なるようになる」と伝える。
そうだよね~、こういう姿勢で臨まないとな~とこの文章を読んだ時からひかえておこうと思ったのでした。
学校や塾で出された課題や宿題の項目では「やらないという選択肢はない!」とありました。
まったっくもってその通りだと思います。
懇談会の時に驚くのは
「うちは言っても宿題をやらないんですぅぅぅ(笑)、私が言ってもやらないので先生からいってくださぁ~い」

とか
「うちの子は、習い事(サッカー)で夜帰宅するのが21時過ぎなんです。宿題は出さないでください。」

とか
「うちの子は習い事(書道、空手)が多いので宿題は週末まとめてやりたいんですけど」

などなど
(ーー;)なんかちょっと違うな?っていう方がいらしゃって驚いたことがあります。
本来は学校があって、習い事は各ご家庭の事情なわけで、、、、、ほかのお子さんもいるというのに
習い事が多いから宿題を減らせとかなくせとか・・・・おいおいな訳です。

なので、この項目、親がついていて回せるようにやらせる!というようなことが書いてあって
わたしだってフルタイムですが、回せるように日々工夫の連続です。
この内容には激しく共感!でした。
三男の方だったかな?早生まれだそうです。
早生まれは「かわいそうだな」と思わずに、やるべきことをしっかりやっていくというようなことが
書いてありました。
うちも早生まれ1月末なのでほぼ2月なんですが・・・・著者のお子さんは3/30生まれだそうです。
ほぼ4月ですよね。
早生まれを逃げの口実にはできないな~と、改めて考えさせられました。
「早生まれだからこそ、なんでも最低半年は早くはじめたほうがよいと思いました」とありました。
小さいからと不憫に思うのではなく、だからこそどうしたらいいかを考えていたんですね。
なんか本当にすべてが教育ありきのママなんだな~とびっくりでした。
幼児期の部分にも触れているのですが、読み聞かせも〇才までに〇〇語!みたいに(日本語の童話などの
読み聞かせですよ!!)やられていたようです。
すごいです。
筋金入りという言葉がぴったりかもしれません。
(^_^;)良い刺激となった1冊です。
大学受験までは二人三脚!みたいに出てきましたが、我が家のように激しい反抗期の娘と
腹をわってとことん話すまでには至らず(お互い短気というのもあるのですが・・・・)
なかなか勉強を親の思うようにはしてくれません。
やる気があるのかないのかさえも分かりません。
(ーー;)ここまでの育て方と言われてしまえばそれまでなのですが・・・・・。
とりあえず寄り添いつつ、言うべきことは伝える、聞く耳を持つスタンスでやっていきたいと
思います。

 怒っているのですもの。
怒っているのですもの。
 )
)









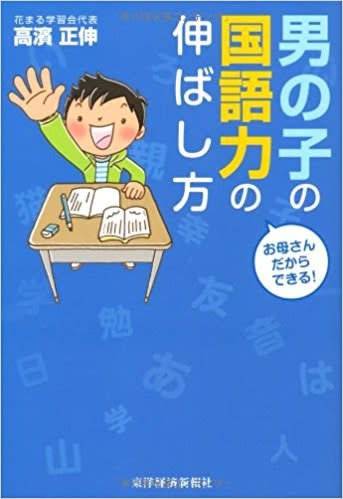
 明日は、少し国語を二人三脚でお直しに取り組みたいです。
明日は、少し国語を二人三脚でお直しに取り組みたいです。
 いやいや、見てろよ
いやいや、見てろよ



 まだまだ幼い息子をみていると
まだまだ幼い息子をみていると

 とか
とか などなど
などなど
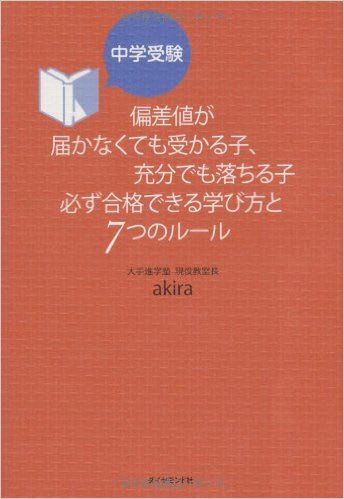
 に続き、読んでみました。
に続き、読んでみました。







