Harper’s BAZAAR 9/23(木) 22:20配信

ドラマ『POSE/ポーズ』
ドラマ『POSE /ポーズ』の制作と原案を手がけたスティーヴン・キャナルスは、共に制作に携わってくれるクルーを見つけるために、166回もミーティングを重ねたという。
『POSE /ポーズ』は、エイズの感染が最も深刻化していた頃のニューヨークのボールルーム・シーンが舞台となった作品だ。黒人とプエルトリコの血が流れるクィアの男性が中心となって脚本を手がけ、メインキャストはほぼ全員が非白人、トランスジェンダー女性が中核に据えられている3シーズンのドラマだ。
いまだBIPOC(Black:黒人、Indigenous: 先住民族、People of Color : 有色人種)とLGBTQ+を扱った作品が必要であり、利益を生むものであるとを認めるのに苦労しているハリウッドの重鎮たちは、プレゼンの段階では必ずしも全員がいい顔をしないだろうと思われたドラマシリーズだ。
最終的に、プロデューサーにライアン・マーフィー、テレビ局はFXを拠点とすることに決定した。しかし自分たちが実際に経験してきたことを芸術作品へと導き、かつ社会的現象にまで引き上げられる才能のあるトランスジェンダーの女性たちをプロデューサー陣が見つけるまでは、この作品に命が吹き込まれない。大変な苦労の末、彼らが発掘したメンバーの中にいるのがこの女性たちだ。
アクティビストでベストセラー作家のジャネット・モック。11歳で演技を始め14歳でボールルーム・シーンに入り、キャリアの半ばでトランスジェンダーであることを公表したMJ・ロドリゲス。
養護施設で育ち、10代の頃にはいじめを受けたが、現在はIMGとモデル契約を結んでいるインディア・ムーア。トリニダード・トバゴ出身の移民で真のボールルーム・アイコンになったドミニク・ジャクソン。
彼女たちはみな、苦難、ホームレス、セックスワーク、人から拒絶された時の対処法などを経験上、知っている。
しかし『POSE /ポーズ』を作り上げる際の彼女たちの仲間意識とケミストリーのおかげで、この物語は単なる苦労話以上の作品になった。この作品は喜びも伝えているのだ。苦労の末にボールルームで祝福を受けた時の喜びは、世界中のリビングで映し出された。
この見事な3部作のドラマの最後のエピソードが終了する前夜に、『POSE/ポーズ』のメインキャスト3名と脚本家のジャネット・モックが撮影の開始当時の幸福感や甘く切ない思い出について語り合う。
ジャネット・モック(以下JM):レディたち、このところ私はいつもこのマントラを頭の中で唱えているのよ。「新型コロナウイルスのパンデミックの中で、半年にわたってこのドラマを撮影できたんだったら、この先、私はほぼなんだってできるはず」って。
私たちを信じてくれたこの作品のプロデューサー、ネットワーク、スタジオを心から誇りに思っている。私たちのストーリーを信じてくれて、このドラマに価値を見出してくれて何百万ドルも投資してくれたこと、このドラマのシーズン1を作るために既に予算がかさんでいたにもかかわらず、私たちを再び起用してくれたことに本当に感謝している。私たちのストーリーは重要な課題で、とても大切で、放送されるべきものだから。
まずは、最初に戻ってみんなに聞きたい。MJ、ブランカのオーディションについて話してもらえる?
MJ・ロドリゲス(以下MR):私はその当時キャリアの岐路にいた。あまりにも多くの「ノー」ばかり受けていたから、演技を続けるべきか、続けたいのか悩んでいた。そこに2つのチャンスが舞い込んできた。ひとつは初のブロードウェイのショー。
もうひとつは『Backstage』誌で見つけた『POSE/ポーズ』の役柄の詳細だった。それを読んだ時に、ブランカとはどういう人間なのか、何を伝えたいのかを知って、私はこの役を欲しいと思った。
今も思い出すのが、オーディション会場でドミニクと少し話したこと。そこで私は、“なんだかいい感じ。このドラマはそれまで自分のストーリーを語ってこなかった強い黒人のトランス女性だけの話ではなくて、私が本当に知っている人に寄り添っているものだ”と思った。
ただその頃、私は個人的には自分がトランスジェンダーだということをそこまで広く公言していなかった。世界がどのように私を受け入れてくれるのか、また私たちのストーリーをどのように受け入れてくれるのかが心配で仕方がなかった。でも私は間違っていた。ハニー、私たちはそれを覆したのよ。
インディア・ムーア(以下IM):私がエンジェル役のオーディションを受けた時、会場には大勢の人がいた。私はこの業界では全くの経験不足で、ライアン・マーフィーのことなんて全然知らなかった。けれど、スティーヴンの顔があったのを覚えている。スティーヴンは私の家族にとても似ていた。
そう、彼は私に似ていたの。親近感を覚えてすごく気分が盛り上がったのよ。だって、この役が自分に合っているのか、私が演じる価値があるのかもわかっていなかったから。でも、なんだろう、そういうことから私たちの現実が始まるのかな、と思った。
JM:それってすごく力を与えてくれる言葉。2017年の7月から8月にかけてみんなはオーディションを受けていた。その頃、私はライアンに出会った。当時彼は『アメリカン・クライム・ストーリー』の現場で監督を務めていた。
現場のセットチェンジをしている最中に30分ほど私は彼と軽いミーティングをしたの。ライアンに「君のこれまでの作品を読んだよ。ロサンゼルスに来てこのドラマの脚本を書く気が君にあるかどうかを教えてほしい」と言われた。それに対して私は「私にとって素晴らしいチャンスだと思います。
でもその前に、質問したいことが山ほどあります」と答えた。彼は非常にクリアに、私が知りたいと思っていたことを全て明確に説明してくれた。そこで私は参加することを決めた。私は「このドラマに私は貢献できる」と思ったの。
IM:ジャネットが脚本家兼プロデューサーとして現場に現れたとき、私はこのドラマに出演するみんなは絶対に大丈夫だと安心した。ハリウッドの曲解や偏見を持った視点から私たちを守ってくれて本当に感謝してる。私たちだけでは抱えきれなかったから。
JM:撮影現場に初日に行ったとき、この作品はマジックになると確信した。インディアとMJ、ドミニクから受け取った愛情の深さを覚えている。ドミニクが完璧なママ・エレクトラの衣装で私のところに来てくれて、ハグしてくれて、「ガール、あなたがこのドラマを書いてくれていることを聞いた瞬間、私はこれが絶対にうまくいくと思ったわよ」って言ってくれた瞬間があった。
撮影期間中、ずっと私は出演しているシスターたちの保護者なのだと自分に言い聞かせていた。私はみんなを守るためにここにいる。このドラマの中での私の唯一の仕事は、その軸を守ることだけよ。
素晴らしい才能を持った演者たちによる壮大なアンサンブルの中で、女性の存在が失われないようにすること。プロデューサーとして、演出家として現場で必ず確認することが私の最も大切な仕事だと思っているから。
ドミニク・ジャクソン(以下DJ):みんなの存在がどれほど私の心に響いたか、まだ話してなかったわね。それはエンジェルが、私が演じたエレクトラに対して「ママ」と言ったときのこと。そのとき私は、「ちょっと待って、私本当に彼女のママになったみたい」と感じていた。
JM:実際にみんながボールルーム出身だからこそ聞きたいのだけれど、このドラマで欠かせないと思ったシーンはどこ? そして役を手にしたとき、それは自分にとってどんな意味があると感じた?
DJ:私は生きていても、どうあがいても手が届かないレベルがあると理解して、そこに落ち着こうとしていたところだった。2016年にウーピー・ゴールドバーグとトム・レオナルディスがエグゼクティブ・プロデューサーを務めた『ストラット』(トランスジェンダーのモデルを起用したリアリティショー)に出演した。
でもその時すでに40歳だったから、年齢の壁にぶつかったの。ウーピーは私のために戦ってくれた。オーディション会場では誰もが私に会おうとしていたけれど、私の年齢を聞いたとき、ちょっと待て、と思われたのよ。「黒人で、トランスジェンダー、移民でしかも40歳?」と思われていたはず。でも私は脳内で、「でも、とにかく私を見てよ!」と思っていたわ。
その当時のエージェントから連絡をもらって、このドラマのことを教えてもらった。エレクトラのキャラクターの部分だけを読んだ。エレクトラ以外は見なかった。私は40歳を超えているから、ブランカの役柄の詳細に関してはエージェントが私に伝えてこなかった。
エンジェルの役に至っては一切知らなかった。エージェントは多分、私にはこの役しかない、という感じだったのね。でも(この脚本には)親近感を持った。1990年代に(「House of Dupree」のマザーだった)パリス・デュプリーとニューヨークの「Two Potato」のバーで飲んでいたときのことを思い出した。
彼女はバカルディの151ショットを飲んでいて、私はキール・ロワイヤルを飲んでいた。そのとき私はこう思っていた。「どうしてこの人は私に話しかけているんだろう? ただ静かに飲んでいてはだめ? あっちに行って踊りながらつけまつげを外す様子を見せてほしいわ。そのために私は今ここにいるんだから」と思っていた。
でも彼女はエイヴィス・ペンダーヴィスやドリアン・コーリー、ペッパー・ラベイジャなどのマザーたちの話をずっとし続けた。時を経て、それが全て私の現実になった。あらすじを読んでいるときに、「ああ、この人たちがあの時に聞いた女性たちだ」と思った。
それで私は一回目のオーディションに行って、衣装を身につけた。オクタヴィア・サンローランやダニエル・レヴロンがどのように表現をしていたか、どのように現れたのかを思い出していた。彼女たちは本当に大胆な存在だった。
会場に入った私は、すでに全てのセリフを覚えていた。オーディションのシーンは、エレクトラがブランカに対して自分の頬骨を自慢する部分だったの。
JM:「空の上の太陽のように高い!」
DJ:「あなたにはまだ早い!」
MR:「あなたはまだ私と……」
全員:「並ぶなんて早い!」
DJ:(キャスティングディレクターのアレクサ・L・フォーグルと)彼女のアシスタントが互いに目を見合わせた。私はその場に立っていて、「とにかく私の時間をちょうだい」と思っていた。再び呼ばれることなんて全く期待していなかった。
「私はグリーンカードを手に入れたばかり。仕事もあるし、十分恵まれているじゃない。これ以上何か望んだらバチが当たる」と自分に言い聞かせていた。
今、みんなの前だから正直に言うけど、あの頃の私は生涯の夢を叶えている最中だった。性別適合手術の最終段階だったの。(二度目のオーディションの連絡をもらったとき)私はハイヒールを手に取って、自分に「このヒールを履いたら、傷口が開いてしまうかもしれない。病院に戻ることになるかもしれない」と、自分に問いかけた。
お金が手元にあまりなかったので、タクシー代を人に借りた。ヒールを履いてもいつもと同じような良い気分にならなかったから涙が出てきた。痛くて。でもオーディション会場に入ったときにふと何かが変わった気がした。
帰り道も私は泣いていた。でもそのときは痛かったからではなくて、達成感があったから。私はオーディション会場に行って、やり切ったと感じた。
そしてその後合格したと連絡をもらったときには、演技を学ぶ手段さえ持てなかった私は本当に幸福を感じたし、他の誰にもできない価値のあることを成し遂げたと思った。
JM:MJは11歳の頃からこの業界にいるでしょう? 技術面での準備はできていたと思うけれど“旅”の経験は浅かった。トランスジェンダーの女性として、公にトランジションをしなければならないということで、このような先駆的な女性の役を演じるという未知の次元に対する恐怖感と不安はあった ?
MR:私は以前、自分がトランスジェンダーであることを公表したけれど、当時は私を知る人は少なかった。けれどもこのようなプロジェクトの一員になるとしたら?と自問した。
「何かを公表することで自分を危険にさらし、その後の反発に耐えられるだろうか。しかもトランスジェンダー女性であるだけではなく、ラテン系かつアフリカ系アメリカ人の女性。本当に気持ちの準備はできている?」と。
ナーバスになっていたけれど、『POSE/ポーズ』に関して言えば、私が伝えたいメッセージと目的を知るためにしっかり頑張ったつもり。
つまり、この作品は私たちがどのような人間で、どう生きてきたかを示す作品でしょう。ドラマの設定は1987年から1994年だけど、その時期だけではなくて、今もこれからも私たちに何ができるかを伝えているものでしょう。
そしてここにいる仲間たちと一緒に仕事をすること、これまでずっと日陰に隠れていた私たちがさまざまなイベントで団結して立ち上がること、力を示すこと、私たちの立場を肯定して、どういう人間なのかをわかって共に立ち上がることができる、という事実のおかげで私は準備を整えられた。万端だった。いや、それ以上だったかも。
IM:私は自分自身が“スター”と呼ばれることにずっと慣れなかった。自分自身でも認めなかったし。なぜかわからないけれど、不健康な感じがしていた。でも、エンジェル役を演じている自分の姿をテレビで見た時、“オー・マイ・ゴッド、私スターだ”って感じずにはいられなかった。
JM:ハニー、そうよ、感じて!
MR:それでいいのよ、ベイビー!
JM:みんなが自分の姿を画面で見て、“ビッチ、私はスターよ”と感じてくれたのはとてもうれしい。だってそれは大切だもの。ちゃんと認めないと。それだけ影響力のあることをしたんだから。
あなたたちのために脚本を書いて演出ができたことは私の人生の中で最高のギフトだった。この先、『POSE/ポーズ』でみんなと一緒に仕事したことを超えるようなクリエイティビティにあふれた経験をできるのかはわからない。
でもこの作品は、誰からも何も与えられなかった頃にハウスを作り、社会的に認められず、何も持っていない子たちの夢をかなえた初期のマザーたちのおかげなの。
彼女たちは素晴らしいレガシーを残したと思う。私にとって『POSE/ポーズ』は、ゼロから魔法を生み出した、そんなマザーたちへのラブレターよ。
From Harper's Bazaar September 2021
https://news.yahoo.co.jp/articles/55576827e4858cfd997626807ce2638f703e8576










 2001年9月22日に町内で開催されたイチャルパ(本別アイヌ協会提供)
2001年9月22日に町内で開催されたイチャルパ(本別アイヌ協会提供)



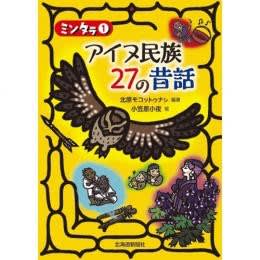 「ミンタラ《1》 アイヌ民族27の昔話」の表紙
「ミンタラ《1》 アイヌ民族27の昔話」の表紙 ドラマ『POSE/ポーズ』
ドラマ『POSE/ポーズ』



