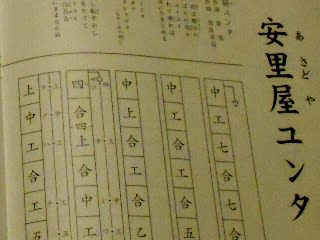厳密には中国地方ではありませんが、気になりついでに行って来ました。

絶景の雲海に浮かぶは!
・・・ごめんなさい嘘つきました(笑)ココは過去に訪れた白川郷と白山を結ぶホワイトロード上で偶然撮った写真です。思うにこういう写真は季節や天候、時刻にすらも左右されるので、ある程度霧が発生する条件が揃いやすい土地柄としても、休日等に狙って撮影するのは余程の運がないと無理ですな。竹田城跡や備中松山城も「天空の城」として有名ですけど、条件さえ整えば岐阜城も年に1回くらいシャッターチャンスがあるもので、たまに地元紙に載ったりもしますからね。というわけで、おそらく別の山から望むであろう写真は諦め、普通に登ってくるだけにしました。

城崎温泉よりまっすぐ50kmほど南下したところにありました。標高は354mの山ですが駅付近の無料駐車場辺りがすでにそれなりの標高なので、登るべき高低差は備中松山城と同じく230mほどしかないようです。その点岐阜城は標高10mより334mまで登りますから結構な山なのですよね。ここは城跡なので写真のように下から見える部分は限られていますし・・・あれ?やっぱり岐阜城最強じゃね?(笑)
登山道は駅の真裏にある道が一般的のようです。およそ900mなので、20分ほどで料金所まで着きました。日本のマチュピチュとも言われるように、山頂をしっかりした石垣が周囲をぐるっと取り囲んでいる様子はまさに圧巻ですね。

2006年に「日本百名城」に選ばれ、その後カメラマンが雲海に浮かぶ有名な写真を紹介したことで徐々に知名度が上がり、12年頃からCMや映画に使われて一気にブームに火がついたようで、観光客はその10年で一気に20倍に膨れ上がったそうです。そのため元々の山肌がむき出しの状態だった通路が観光客が歩く度にどんどん削られてしまい、崩落の危険があったためこの写真の奥側の道のように、黒い謎の素材を土嚢のように敷いてカバーしている模様でした。しかしこれ、結構デコボコして歩きにくかったですし、かなりの面積が真っ黒に敷き詰められているので景観も余り良くないように感じました。まあ将来的には手前にある3通りの舗装方法のどれかになるようで、試験的に導入して踏み応えを試してもらい、今後どうするかを予算と相談しながら決める模様です。
いつものように団体さんのガイドの声に耳を傾けつつ(笑)自由気ままに散策してきました。おそらく雲海スポットであろう対面の山は結構距離があったので、例の写真を狙うには雲だけでなくそれなりの望遠機能が必要なのかもしれません。帰りは急な階段が続く最短コースで下山。ちなみに山腹にも駐車場があり、そこから歩きやバスという選択肢もあるようです。整備計画は着実に進んでいるようですね。ブームがいつまで続くかは分かりませんが・・・
城攻めは以上ですが中国記はぼちぼち続きます。

絶景の雲海に浮かぶは!
・・・ごめんなさい嘘つきました(笑)ココは過去に訪れた白川郷と白山を結ぶホワイトロード上で偶然撮った写真です。思うにこういう写真は季節や天候、時刻にすらも左右されるので、ある程度霧が発生する条件が揃いやすい土地柄としても、休日等に狙って撮影するのは余程の運がないと無理ですな。竹田城跡や備中松山城も「天空の城」として有名ですけど、条件さえ整えば岐阜城も年に1回くらいシャッターチャンスがあるもので、たまに地元紙に載ったりもしますからね。というわけで、おそらく別の山から望むであろう写真は諦め、普通に登ってくるだけにしました。

城崎温泉よりまっすぐ50kmほど南下したところにありました。標高は354mの山ですが駅付近の無料駐車場辺りがすでにそれなりの標高なので、登るべき高低差は備中松山城と同じく230mほどしかないようです。その点岐阜城は標高10mより334mまで登りますから結構な山なのですよね。ここは城跡なので写真のように下から見える部分は限られていますし・・・あれ?やっぱり岐阜城最強じゃね?(笑)
登山道は駅の真裏にある道が一般的のようです。およそ900mなので、20分ほどで料金所まで着きました。日本のマチュピチュとも言われるように、山頂をしっかりした石垣が周囲をぐるっと取り囲んでいる様子はまさに圧巻ですね。

2006年に「日本百名城」に選ばれ、その後カメラマンが雲海に浮かぶ有名な写真を紹介したことで徐々に知名度が上がり、12年頃からCMや映画に使われて一気にブームに火がついたようで、観光客はその10年で一気に20倍に膨れ上がったそうです。そのため元々の山肌がむき出しの状態だった通路が観光客が歩く度にどんどん削られてしまい、崩落の危険があったためこの写真の奥側の道のように、黒い謎の素材を土嚢のように敷いてカバーしている模様でした。しかしこれ、結構デコボコして歩きにくかったですし、かなりの面積が真っ黒に敷き詰められているので景観も余り良くないように感じました。まあ将来的には手前にある3通りの舗装方法のどれかになるようで、試験的に導入して踏み応えを試してもらい、今後どうするかを予算と相談しながら決める模様です。
いつものように団体さんのガイドの声に耳を傾けつつ(笑)自由気ままに散策してきました。おそらく雲海スポットであろう対面の山は結構距離があったので、例の写真を狙うには雲だけでなくそれなりの望遠機能が必要なのかもしれません。帰りは急な階段が続く最短コースで下山。ちなみに山腹にも駐車場があり、そこから歩きやバスという選択肢もあるようです。整備計画は着実に進んでいるようですね。ブームがいつまで続くかは分かりませんが・・・
城攻めは以上ですが中国記はぼちぼち続きます。