言葉というものは時代とともに変遷していき、いつの間にか使われなくなってしまうものがあり、主に若者からなのだろうが新しい言葉が生まれてくることがある。
当然ながら時代、時代の思潮を反映していて、差別意識を助長するとか相手が傷つくなどと言われてマスコミなどでは今となっては不適切と判断されて使うことが出来なくなった言葉も多い。
古典落語などでも放送では演じることが出来ない話が結構あるし、昭和の映画とかドラマでも不適切な表現があるがあえてそのまま放送していると断り書きを付け加えている場合も多い。
筒井康隆は、ある種の思想統制で作家が自由に書けなくなると反発して一時断筆宣言したこともある。
酒井順子さんはそんな大上段に振りかぶらずに、いつの間にか使われなくなった言葉表現、いつの間にか使われるようになった言葉表現、さらには同じ言葉なのに意味が変わってしまった表現などから人々の意識と現代社会の変化を柔らかく論じている。
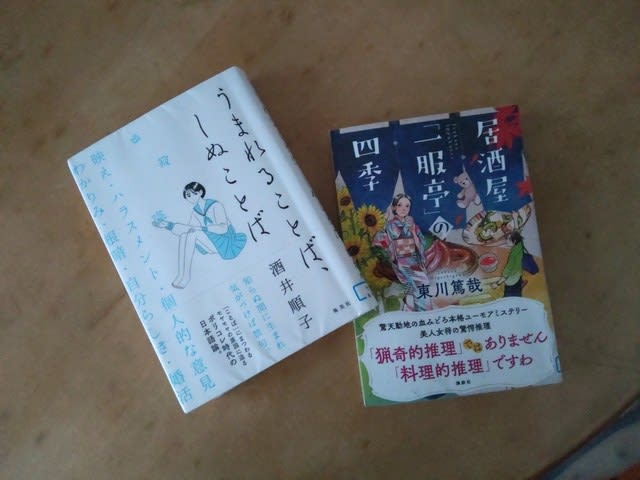
読んでなるほどと思うところが多々あり、さすが文筆を生業にしている人は、言葉に敏感でよく考えていると感心しました。まあ、当たり前ですけど。
これを読んでいる時は丁度いろいろなスポーツイベントがあった時なので、終わった後のヒーローインタビューなどで選手が何か聞かれると最初に「そうですね」と言ってから答えているようになったと書いてあるのを読んだ時は、今までまったく気にしていなかっただけにその通りとちょっとびっくり。その背景と心理を分析しているのですが、おかげでヒーローインタビューを見るたびに出だしの言葉が気になってしまいました。そうですね。
アイドルグループのメンバーが何らかの事情で脱退する時に「卒業」と言うようになったのはいつごろからか。脱退といういろいろ裏事情もありそうな現実をうまくオブラートに包んでいます。
CМとかでよくさりげなくテロップが入るようになった言葉は「個人的意見です」。健康食品とかの類のCМでよくお目にかかります。科学的根拠は薄いけど使ってみたら私はよかったですと言うことを主張する時の恥じらいの混じった言い訳です。関西の会話では最後に付け加える「知らんけど」という言葉でしょうか。
森喜朗はよく受け狙いでしょうが身内の楽屋話をそのまま公的な場面で話してしまい物議をかもしています。記憶に新しいのは「女性が沢山入っている会議は時間がかかる」云々。本人的には受ける話が出来たとその時はご満悦なのが残念。本音の差別意識はもちろん許されないのですが、それを公的場面で話して臆することがない感覚もアウトです。あえて言えば首相の時からそういう人だったんですけど、いろいろ失敗があっても学んでいない。根底にはよく本音を言ったと言う暗黙の指示があるのでしょうけど、それがいつまでも表舞台に留まらせている。
昭和の歌謡曲では今の感覚では差別意識満載で「セクハラ」だらけ。当時はセクハラなどと言う言葉はなく人口に膾炙したのは平成になってから。今ではいろいろな「ハラ」が言われてくる様になりましたが、他人から不当で不快な目に遭わされたら「〇〇ハラ」と命名することによって「NO」の声をあげやすくなり、日本社会を大きく変えることになったと言われると言葉の力を改めて考えてしまいます。そんな言葉などない時代を過ごし、当たり前のようにセクハラをしていた昭和世代のモーレツ社員は意識がついて行かなくて、黙って古き良き時代を懐かしんでいるのです。
「オレオレ詐欺」も絶妙なネーミングで注意喚起に効果を発揮したのですが、詐欺の形態が進化したのについて行けずに特殊詐欺などと言うこなれていないネーミングでイマイチインパクトがない。
ここに書いたのはほんの一部ですけど、言葉の変遷から社会の変遷がどう進んできたのかが分かるのですが、酒井順子さんは高校生の頃から東京の若者文化の最前線に身を置いていたのですが、当時の言葉でもよく分からないものがあって、名古屋ローカルで人生を終えようとしている身としては今の言葉は理解不能のものが多くて、勉強になりますが、時代について行けずに取り残された気分です。
表現の変遷に戸惑い、今の言葉がよく分からないとか違和感を感じている人は一読あれ。
一緒に映っているのは東川篤哉「居酒屋『一服亭』の四季」です。「謎解きはディナーの後で」の作者なので面白いかと何気なく借りたのですが、ストーリーも推理も荒唐無稽すぎ。突っ込みどころ満載ですが、そこがこの作者の持ち味か。寝っ転がってkill the timeとして読む本も必要で、そういう時は理屈抜きで楽しめる本に限ります。でも「謎解きはディナーの後で」の方がだいぶ出来がいいと思いますけど。
当然ながら時代、時代の思潮を反映していて、差別意識を助長するとか相手が傷つくなどと言われてマスコミなどでは今となっては不適切と判断されて使うことが出来なくなった言葉も多い。
古典落語などでも放送では演じることが出来ない話が結構あるし、昭和の映画とかドラマでも不適切な表現があるがあえてそのまま放送していると断り書きを付け加えている場合も多い。
筒井康隆は、ある種の思想統制で作家が自由に書けなくなると反発して一時断筆宣言したこともある。
酒井順子さんはそんな大上段に振りかぶらずに、いつの間にか使われなくなった言葉表現、いつの間にか使われるようになった言葉表現、さらには同じ言葉なのに意味が変わってしまった表現などから人々の意識と現代社会の変化を柔らかく論じている。
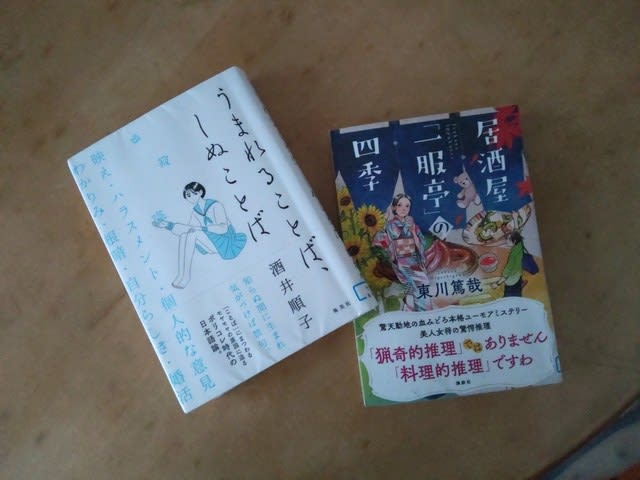
読んでなるほどと思うところが多々あり、さすが文筆を生業にしている人は、言葉に敏感でよく考えていると感心しました。まあ、当たり前ですけど。
これを読んでいる時は丁度いろいろなスポーツイベントがあった時なので、終わった後のヒーローインタビューなどで選手が何か聞かれると最初に「そうですね」と言ってから答えているようになったと書いてあるのを読んだ時は、今までまったく気にしていなかっただけにその通りとちょっとびっくり。その背景と心理を分析しているのですが、おかげでヒーローインタビューを見るたびに出だしの言葉が気になってしまいました。そうですね。
アイドルグループのメンバーが何らかの事情で脱退する時に「卒業」と言うようになったのはいつごろからか。脱退といういろいろ裏事情もありそうな現実をうまくオブラートに包んでいます。
CМとかでよくさりげなくテロップが入るようになった言葉は「個人的意見です」。健康食品とかの類のCМでよくお目にかかります。科学的根拠は薄いけど使ってみたら私はよかったですと言うことを主張する時の恥じらいの混じった言い訳です。関西の会話では最後に付け加える「知らんけど」という言葉でしょうか。
森喜朗はよく受け狙いでしょうが身内の楽屋話をそのまま公的な場面で話してしまい物議をかもしています。記憶に新しいのは「女性が沢山入っている会議は時間がかかる」云々。本人的には受ける話が出来たとその時はご満悦なのが残念。本音の差別意識はもちろん許されないのですが、それを公的場面で話して臆することがない感覚もアウトです。あえて言えば首相の時からそういう人だったんですけど、いろいろ失敗があっても学んでいない。根底にはよく本音を言ったと言う暗黙の指示があるのでしょうけど、それがいつまでも表舞台に留まらせている。
昭和の歌謡曲では今の感覚では差別意識満載で「セクハラ」だらけ。当時はセクハラなどと言う言葉はなく人口に膾炙したのは平成になってから。今ではいろいろな「ハラ」が言われてくる様になりましたが、他人から不当で不快な目に遭わされたら「〇〇ハラ」と命名することによって「NO」の声をあげやすくなり、日本社会を大きく変えることになったと言われると言葉の力を改めて考えてしまいます。そんな言葉などない時代を過ごし、当たり前のようにセクハラをしていた昭和世代のモーレツ社員は意識がついて行かなくて、黙って古き良き時代を懐かしんでいるのです。
「オレオレ詐欺」も絶妙なネーミングで注意喚起に効果を発揮したのですが、詐欺の形態が進化したのについて行けずに特殊詐欺などと言うこなれていないネーミングでイマイチインパクトがない。
ここに書いたのはほんの一部ですけど、言葉の変遷から社会の変遷がどう進んできたのかが分かるのですが、酒井順子さんは高校生の頃から東京の若者文化の最前線に身を置いていたのですが、当時の言葉でもよく分からないものがあって、名古屋ローカルで人生を終えようとしている身としては今の言葉は理解不能のものが多くて、勉強になりますが、時代について行けずに取り残された気分です。
表現の変遷に戸惑い、今の言葉がよく分からないとか違和感を感じている人は一読あれ。
一緒に映っているのは東川篤哉「居酒屋『一服亭』の四季」です。「謎解きはディナーの後で」の作者なので面白いかと何気なく借りたのですが、ストーリーも推理も荒唐無稽すぎ。突っ込みどころ満載ですが、そこがこの作者の持ち味か。寝っ転がってkill the timeとして読む本も必要で、そういう時は理屈抜きで楽しめる本に限ります。でも「謎解きはディナーの後で」の方がだいぶ出来がいいと思いますけど。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます