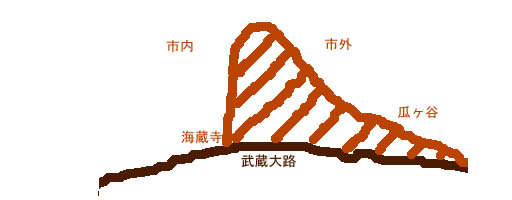この青マークの道は、
「とても古くから有る道です。」 っとされています。
具体的にどの程度古いのか?
きっとそれに答えるとすれば、
「明治の地図に載っています」 っと言う事になるでしょう。
明治の初期に作られた地図ですから、江戸時代にも使われていた筈です。
それ以前は?
鎌倉時代に使われたかも? でも、資料は、、、
平安時代は???
平安時代の鎌倉に関して資料は限られる。まして、奈良時代の道の資料は無い。
そんな曖昧な話になるでしょうね。
頼朝以前に赤と青のマークの道は繋がっていたと考えられています。
が、、、しかし、
赤と青の道は性質が違います。
青の道はユルヤカに曲がっている事を根拠に、古代東海道の痕跡と考えるのは否定されるべきでしょう。
もう一つの否定する根拠は、地図の赤い点線ですが、六浦道の延長直線は、青いマークの道から外れる。
AとB の道の目的点がDであったとすれば、、、青ラインのC点は北に寄り過ぎる。
極端な障害物の無い限り、古代道は直線的に作るのがセオリーです。
江戸モシクハ鎌倉時代の六浦道延長とすれば、青い道も肯定される話でしょうね。
何故、赤い点線の道は消え、青い道になのでしょうか?
そんな資料は無いので、、、憶測で考える訳です。
記事一覧 ★★http://blog.goo.ne.jp/mementosmori/★★
「とても古くから有る道です。」 っとされています。
具体的にどの程度古いのか?
きっとそれに答えるとすれば、
「明治の地図に載っています」 っと言う事になるでしょう。
明治の初期に作られた地図ですから、江戸時代にも使われていた筈です。
それ以前は?
鎌倉時代に使われたかも? でも、資料は、、、
平安時代は???
平安時代の鎌倉に関して資料は限られる。まして、奈良時代の道の資料は無い。
そんな曖昧な話になるでしょうね。
頼朝以前に赤と青のマークの道は繋がっていたと考えられています。
が、、、しかし、
赤と青の道は性質が違います。
青の道はユルヤカに曲がっている事を根拠に、古代東海道の痕跡と考えるのは否定されるべきでしょう。
もう一つの否定する根拠は、地図の赤い点線ですが、六浦道の延長直線は、青いマークの道から外れる。
AとB の道の目的点がDであったとすれば、、、青ラインのC点は北に寄り過ぎる。
極端な障害物の無い限り、古代道は直線的に作るのがセオリーです。
江戸モシクハ鎌倉時代の六浦道延長とすれば、青い道も肯定される話でしょうね。
何故、赤い点線の道は消え、青い道になのでしょうか?
そんな資料は無いので、、、憶測で考える訳です。
記事一覧 ★★http://blog.goo.ne.jp/mementosmori/★★