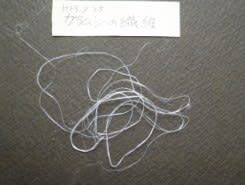京都府立植物園
久しぶりの植物園。北山の入り口近くにはコスモスの鉢がいっぱい並んでいた。
午前の半日を生態園を歩く。生態園の秋の花はもう終盤だ。


変わり咲きのアサガオ(丸葉) シナアブラギリ実


サラシナショウマ ホトトギス


カシワバハグマ タヌキマメ ほどんど実に

白のツリフネソウがあった。
今日は3人だったのでお昼の食事はレストランに入り、午後から東寺へ。
東寺
弘法大師(空海)の亡くなった日にちなみ毎月21日に弘法市が開かれる。
何回かは来たことがあるがざっとひと回り。
骨董の店が多い。
「あまり物を増やしたくないね」というのが我々の一致した意見で見るだけに。
古い着物や布は手づくりの好きな人なら喜びそうだが私には縁がない。
中に面白かったのが昔ながらの「動かせるおもちゃ」の店。
写真がないからわかりにくいが・・
下に出た糸を引っ張ると、上の人形が手を上げ下げする。たとえば張り子の牛若丸が両手に持ったナギナタをふりあげたり降ろしたり。
叉、円盤の下のおもりを揺らすと、円盤の上のニワトリが首を上げ下げして餌をついばんだり・・
店の人が動かして見せてくれたそのからくりは昔からあったものらしい。これはおもしろい。
手先の器用なMさんなら作れそう。「見ておいて作ったら?」
まあこんな客ばかりではお店も儲からないなあ。
久しぶりの植物園。北山の入り口近くにはコスモスの鉢がいっぱい並んでいた。
午前の半日を生態園を歩く。生態園の秋の花はもう終盤だ。


変わり咲きのアサガオ(丸葉) シナアブラギリ実


サラシナショウマ ホトトギス


カシワバハグマ タヌキマメ ほどんど実に

白のツリフネソウがあった。
今日は3人だったのでお昼の食事はレストランに入り、午後から東寺へ。
東寺
弘法大師(空海)の亡くなった日にちなみ毎月21日に弘法市が開かれる。
何回かは来たことがあるがざっとひと回り。
骨董の店が多い。
「あまり物を増やしたくないね」というのが我々の一致した意見で見るだけに。
古い着物や布は手づくりの好きな人なら喜びそうだが私には縁がない。
中に面白かったのが昔ながらの「動かせるおもちゃ」の店。
写真がないからわかりにくいが・・
下に出た糸を引っ張ると、上の人形が手を上げ下げする。たとえば張り子の牛若丸が両手に持ったナギナタをふりあげたり降ろしたり。
叉、円盤の下のおもりを揺らすと、円盤の上のニワトリが首を上げ下げして餌をついばんだり・・
店の人が動かして見せてくれたそのからくりは昔からあったものらしい。これはおもしろい。
手先の器用なMさんなら作れそう。「見ておいて作ったら?」
まあこんな客ばかりではお店も儲からないなあ。