
(ミトコンドリアの構造。生命科学教育画像集より引用。)
生態系におけるさまざまな種は捕食や共生によって生態系を維持しているだけでは、どうもなさそうです。細胞内装置のミトコンドリアは生体の外から来たらしく、細胞核の遺伝子とは別の遺伝子をもっています。それでいてミトコンドリアは細胞内でエネルギーを産出するという、大変重要な役割をになっています。

(T4ファージ。ウィキペディア「ファージ」より引用。)
バクテリア間でウイルスを感染させるバクテリオファージは、人間が人工的に細胞内に遺伝子を移植するのに使用します。バクテリオファージが存在するということは、異種細胞間で遺伝子がやり取りされることが生態系では普通に行われることの証拠です。
ウイルス感染というと病気のことばかりを考えますが、じつは遺伝子のやり取りが常に行われていることを意味しており、遺伝子のやり取りは生態系が存続するためには必須な営みなのかもしれません。さらに遺伝子のやり取りは、進化にも大きく影響していると考えられます。
(従来の進化論では「進化」は「突然変異」のみによって起こるとされていますが、1個体に起きたことが種全体を支配することの説明ができませんでした。バクテリオファージによる「ウイルスの一斉感染」のように遺伝子の組み込みが生じたなら、そこの説明がつくのではないでしょうか?)










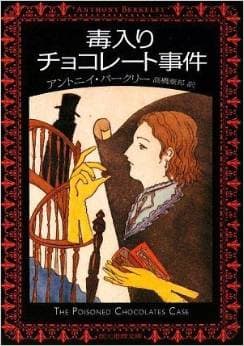 (創元推理文庫)
(創元推理文庫)




 (角川文庫。)
(角川文庫。)