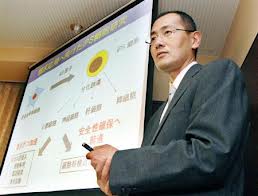今月9日で、「ジュディ・デンチ(Judi Dench、1934年生 ) は、
78歳になる。

私にとって、どうしても 目が離せない人物 (英国俳優) だ。
エリザベス女王からは最高の称号 (Dame:デイム) を得ている。
彼女は、私が この世に生まれる ずっと前の 1957年、
舞台 「ハムレット」 の オフィーリア役で デビューした。
「ロイヤル・シェークスピア・カンパニー」 で 永く活躍しており、
英国では、誰もが知っている有名女優である。

現在は、世界的に 映画 「007 シリーズ」 の 「M(役名)」 で有名だが、
私にとっては、「アイリス」 「恋におちたシェイクスピア」 の方が印象的だった。
しかし、新作 「 007 スカイフォール 」 では、往年の存在感を
しっかりと植えつけていたと、私は感じた。
シリーズ製作50周年記念作品となる当作品は、英国では興行歴代一位と
なったほか、他国でも第一位を樹立し通している。
ひところは、数十年前だろうか・・・
英国のウエストエンドのスケジュールを常にチェックして、
「ジュディ・デンチ」 と 「マギー・スミス」 が出演するという
舞台情報があれば、都合をつけて航空券をとって 渡航していた。
そんな時もあった・・・。
彼女自身は、「舞台女優」 の実績を、英国にて築いて、世界的に
知名度をあげたのは、映画出演が きっかけになっている。
それは、マギー・スミスも 一緒だ。
最新作の 「007」 では、「M」 の存在が浮き彫りになって
主役以上に印象に残るストーリーとなっている。
以前まで参加していた 「Q(役名)」 も、新しく若い青年に
なってしまって、不思議な感覚だった。
(ご高齢のため、「Q」役の俳優さんが亡くなり、降板した)
やはり、女優も、男優も、シリーズものに出演することの責任は、
変わらず持ち続けなければならないし、ある意味では、それが
モチベーションになることもあるだろう。
数年前、「あとニ作は、007に出演を快諾する 」 と言いながら、
それ以上の情報がなかったけれど・・・、あの時には、すでに
このような結果を、ご本人が 要望していたのかもしれない。
英国では、「アバター」を抜き、過去の歴代興行一位を樹立した。
アクション映画だから、当然、アクションの他.爆破シーンがあるが、
廃屋や廃墟がロケ地として たくさん使われていたのは、なんとなく、
(実際的な撮影環境を加味した理由以外に) 意図的な雰囲気を感じた。


彼女の声は、とても個性的で、皮肉屋のインタビュアーによれば、
“だみ声” と 言われることもある。
すでに高齢になったジュディ・ディンチだけれど、若い頃の舞台を
覚えている人は少ないだろう。
そして、成績は優秀で、舞台の存在感も秀逸で、「舞台人」として
素晴らしい評価を勝ち得てきたことも、私たちは何も知らない。
しかし、舞台好きの人なら、きっと理解できるはずだ。
デビュー作が 「ハムレット」 の オフィーリア役だというだけで、
当時の彼女の存在感と演技力が 想像できるはずである。
1970年、「英国ロイヤル・シェイクスピア劇団」 の一員として、
彼女は、初来日を果たして、「ウィンザーの陽気な女房たち」 と
「冬物語」 の 二作に出演している。
舞台は、1月だったけれど、当時の移動手段は 「 船 」 だったらしく、
おそらく往復三か月近くの時間をかけて、来日をしているはずだ。
(公演は、半月なのに・・・)
日本にて興行した外国カンパニーの (記念すべき) 最初の舞台である。
劇場が日比谷だったので、役者達は 歌舞伎座に毎日のように通っては、
歌舞伎のユニークなメイク方法や 演技の型を 真似たりして話題にして、
関係者の間で 「 KABUKI 」 というものが流行していったという。
その後、帰国して、英国の舞台には 歌舞伎に影響を受けた演出が目立ち、
それを取材した記事が 英国には残っている。
英国と日本の古典のかけ橋をつけてくれた人たち・・・の筆頭が、
ジュディ・デンチ達俳優陣だったのだ とも 言える。
彼らが歌舞伎に魅入られたのは、脇役俳優の若手が観光で歌舞伎座へ行き、
あまりの衝撃に、俳優仲間にそれを伝え、どんどんと鑑賞者が増えて、
その次には舞台スタッフまで歌舞伎座通いをするようになったという。
今をときめく英国有名演出家も、そのメンバーの中にいる。
歌舞伎も、シェークスピアも、両国が誇れる国民的演劇である。
歴史の生き証人は、どんどんと少なくなっていくし、ご高齢を理由に
舞台にあがることも少なくなってきて、私としては寂しい限りだ。
(今年、彼女は、難病を理由に、身体の不調を公表している)

1970年の舞台を観劇した人に話を聞くと、「鳥肌がたった」 と
観劇した状況を話してくれた。
それから、私は、特に彼女の「演技」 を観たくてたまらなくなったが、
映像記録は残っていないので、当然、不可能なことである・・・。
だから、余計に、恋しく、求めていくのかもしれない。
現在のしゃがれ声ではない、若き 「ジュディ・デンチ」 が、そこには
確固とした演技力を示しながら、舞台上に立っていたことだろう。
彼女の作品を観るたびに、その1970年の舞台を 想像する。
また、当時の日本と英国の役者達の交流を、勝手にイメージしては、
楽しく、面白い時間を過ごす時もある。
英国シェイクスピア俳優が、歌舞伎俳優にメイクの仕方を教わったという
エピソードも残っているようで、全てに興味がわいてくる。
だって、演劇の歴史なのだ・・・から・・・。
健康に気をつけて、たとえ友情出演でもいいから、時々は仕事(映画)に
出演して、私たちに姿を見せてほしい。
彼女は、演劇界の変遷を見届けてきた英国の “素敵な生き証人” である。