巻向説を含め畿内説では、前回述べたように、邪馬台国は北九州から南方向にあるという『倭人伝』の記述は東の間違いとしなくてはならない。さらに、巻向説では「女王国から東へ千里ほど海を渡ると、また国がある」という記述とも矛盾する。すなわち、邪馬台国は海に面しているか、または非常に近くて、さらにその海を東へ進める場所であるから大和ということはなく、この部分も『倭人伝』の誤りとしなくてはならない。
さて、『倭人伝』によれば、「倭国は30数カ国からなり、長い間戦乱に明け暮れていたが、協議して鬼道(呪術)に長けた邪馬台国の女性すなわち卑弥呼を王に擁立し、連合国となったら平和になった。しかし、卑弥呼の死後(南にある狗奴国との戦争において戦死した可能性もある)また戦乱となり、卑弥呼の一族の13才になる女性、壹與(トヨ)を王にしたら戦乱が収まった」という。
この歴史を踏まえて、大和岩雄は「北九州にあった邪馬台国は、卑弥呼の死後おそらく250年代に大和の巻向に遷都した。箸墓の被葬者は壹與である。遷都の理由は、魏から“親魏倭王”の金印を授与された卑弥呼の時代と違って、魏の国力が弱まり北九州にいる意味合いが薄れたこと、そして政権の勢力圏が東に伸びて、大和の方が地理的要因においてベターになったことである。倭人伝の編者陳寿は遷都の情報を得ていなかったので、『倭人伝』にはそれが記載されなかった。そのために、邪馬台国の場所についての論争が果てしなく続く結果となった」という見解を発表した(『箸墓は卑弥呼の墓か』2004年大和書房)。
安本美典もかねてより邪馬台国東遷説を唱えている(『最新邪馬台国論争』産能大学出版部 1997年)。安本は邪馬台国を福岡県夜須町および甘木市周辺に比定し、北九州と畿内に同じ地名が多いのは、政権が移転した際、地名も同時に持ち込んだからだという。安本説のユニークな点は、天照大御神伝説は卑弥呼の投影としていること。日本では247年と248年(卑弥呼の没年)と、続けて皆既日食があり、それが天の岩戸伝説だという。そして、『紀』にある神武天皇の東征は270-280年としている(『天照大御神は卑弥呼である』心交社2009年)。
終










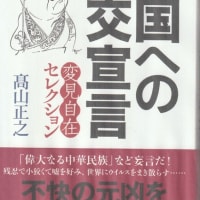








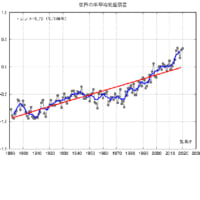
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます