新型コロナの感染拡大がやや下火になったのは、喜ばしいことである。だがその一方で、コロナ関連の財政支出が巨額になっており、これは政府つまり我々の借金である。将来、税金で返済しなくてはならず、次の世代の人々に回すツケでもあるから、最小限にとどめたいところだ。
この観点で、昨日の読売新聞夕刊に載った「コロナ交付金、謎めく使い道」の記事は腹立たしいものだった。

記事によれば、国が地方に配る地方創生臨時交付金(コロナ交付金)は自由度が高く、感染防止策だけでなく、景気対策にも使えるという。だからといって、イカのモニュメント(石川県能登町)、鶴の縫いぐるみの2体目(茨城県常陸太田市)やら、市会議員にタブレット端末を配布すること(滋賀県野州市)に使うとはいかがなものか。
巨大なスルメイカのモニュメント(全長13メートル、幅9メートルのサイズで、人が入れる)は、観光客に特産品をアピールする狙いがあるというが、そのコストは次の世代に回すツケの一部になると思えば、その自治体は気が引けるのではないか。
鶴のぬいぐるみの2体目とは、1体だけでは着る人がコロナに感染するからという理由らしいが、コロナが収束するまでイベントをやらなければ済む話だ。冗談のようなバカバカしい話である。
市会議員にタブレット端末を配布する案は、さすがに市議会内で保留になっているらしいが、当たり前だ。議員活動に不可欠なものとは思えないし、どうしても必要なら自分の小遣いで買えばよい。
コロナ交付金は、ほかにいくらでも使い道があるだろうに。いい知恵が浮かばないなら、交付金を辞退すべきだ。
そもそも、このコロナ交付金は2020年度の補正予算から4兆5千憶が計上され、感染拡大の防止や雇用拡大、経済活動の回復などの事業が対象となり、自治体が提出した実施計画が承認されれば自由に使えるという。
ということは、イカのモニュメントや鶴のぬいぐるみは国によって承認されたものと解せられる。だが、この記事から判断して、「国が承認」とは建前に過ぎず、自治体の計画は自動的に承認されるのではないか。こんな阿呆臭い無駄遣いは、もうやめてほしい。
さて、読売新聞はいい仕事をしたと評価するが、見出しの「謎めく」は適切ではない。「驚きの」とか、もっとネガティヴ感を出すべきだった。再発防止のためにも、各新聞はその監視機能を自覚して、こうした無駄遣いを徹底的に糾弾すべきである。










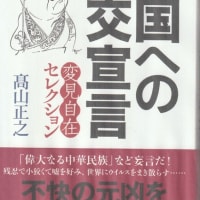








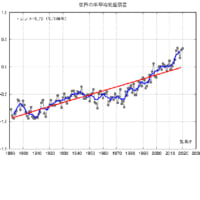
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます