最近、古代史に関する本が2点出版された。一つは「秘められた邪馬台国」で、帯封には「測量士が『翰苑』と『地球号』の実験から隠された女王国への道と解く!!」とある。もう一つは、「日本古代史を科学する」で、その帯封には「学界のタブーを破り、自然科学者の目が衝撃の事実を次々と・・・」とある。この「・・・科学する」の中に『邪馬台国への道』という章があるので、この二点に述べられた「邪馬台国の場所」を論評してみる。
まず「魏志倭人伝」に記された邪馬台国への行程の部分を再確認し、これまでの諸説を概観しておきたい。
「魏志倭人伝」には魏の使者が辿った道は次のように述べられている。出発地点は現在のソウル周辺と思われる魏の植民地、帯方郡である。
郡より、その北岸、狗邪韓国に到る、七千余里。
始めて一海を度る、千余里。対海国(対馬に比定)に至る。
又、南、一海を渡る千余里、一大国(壱岐)に至る。
又、一海を渡る千余里、末蘆国(東松浦半島)に至る。
東南陸行五百里にして、伊都国(糸島半島)に至る。
東南奴国に至る、百里。
東行不弥国に至る、百里。
(以上の距離を合計すると一万七百里)
南、投馬国に至る、水行二十日。
南、邪馬台国に至る、女王の都するところ、水行二十日・陸行一月。
一方、帯方郡から邪馬台国までの総距離は一万二千余里とある。
大多数の学者・研究家は、行程のうち、伊都国までは意見が一致するが、その先は意見が分かれる。
畿内派は、行程を「伊都国→奴国→不弥国→投馬国→邪馬台国」の順だと考え、投馬国は吉備か出雲のいずれかだと比定する。問題点は「南、邪馬台国に至る」の方向が合わぬことで、南は東の誤りだろうとする。また、投馬国→邪馬台国の所要日数が「水行二十日・陸行一月」であれば、畿内では日数がかかりすぎるが、これは許容範囲としているらしく、論述を避けている。
北九州派は、投馬国を大隅半島または鹿児島半島に比定し、「水行二十日・陸行一月」の部分になんらかの誤りがあるとする。そうでないと、邪馬台国は沖縄あたりの存在したことになってしまうからだ(実際に沖縄説もある)。
畿内派も北九州派も倭人伝通りに読み解くと、邪馬台国の場所は皆目わからず、江戸時代からずっと論争となってきた。しかし、古田武彦氏は倭人伝通りに読み解いて、邪馬台国の場所を博多湾沿岸に比定する。その要旨は次の通り。
◆ 「水行二十日・陸行一月」は倭国内の特定の場所から邪馬台国への所要日数ではなく、帯方郡から邪馬台国への総所要日数である。「陸行一月」の大部分は朝鮮半島内における所要日数。
◆ 「東南、奴国に至る、百里」と「南、投馬国に至る、水行二十日」には動詞がないから、これは行程の主線ではなく傍線である。他の行程を示す文には、「渡」「度」「行」の動詞があるから、行程の主線である。傍線であるにもかかわらず、奴国と投馬国だけ挙げたのは、この2国が邪馬台国(7万戸)に次ぐ大国だから(奴国は2万戸、投馬国は5万戸)。
◆ 「東南、奴国に至る、百里」と「南、投馬国に至る、水行二十日」を除く主線だけの距離を合計すると10,600里で、総距離12,000里には1,400里不足する。これは対馬と壱岐を半周したとすればピタリ合う。すなわち、対馬は「方可四百余里」、壱岐は「方可三百余里」とあり、それぞれ一辺を四百余里、三百余里として、島を半周するには二辺を歩くことになるから、対馬での八百里と壱岐での六百里を合計すると1400里である。
◆ 倭人伝の記述では、投馬国の次に邪馬台国の記述があるが、上述のように投馬国は主線ではないから、不弥国の次が邪馬台国になる。この2国の間に距離の記述がないのは隣接していたからである。
◆ 結論として、邪馬台国は博多湾の沿岸にあった。

『池澤康論評』
§古田氏は、対馬と壱岐を半周したとすれば、全体の距離がピタリ合うと主張するが、そこまで細部にこだわる必要はないと考える。船を島の北側に着けて、そこから南側まで歩行し、また乗船したとは常識的に考えにくい。着いた場所からまた乗船したと考えるべきだ。そもそも、陳寿は狗邪韓国→対馬、対馬→壱岐、壱岐→東松浦半島の距離をすべて千余里としており、大雑把な距離を示したにすぎない。そして、「千余里」の「余」には1割程度の許容範囲があるのではないか。それなら「余」の合計が1400里であっても納得できる。むしろ、古田式計算では「余」を無視していることになる。
§「対馬と壱岐の半周」に賛同しかねるが、それでも古田説は倭人伝を記述通りに読み解けることを示したことにおいて、画期的業績である。古田説は30年も前に発表されており、他の論者たちは古田説を読んでいるはずだが、真向から反論しているものはないのは不思議である。










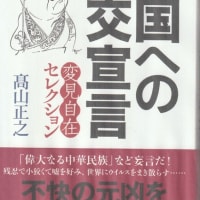








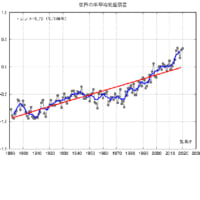
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます