「日本古代史を科学する」(PHP新書)において、中田力氏は邪馬台国の位置を宮崎平野に比定する。
(1) 伊都国
中田氏も、通説通り、魏使は東松浦半島(末蘆国)の唐津近辺に上陸したと考える。問題はそこから先である。通説(古田武彦氏など)では、伊都国を糸島半島に比定するが、中田氏は倭人伝の記述「東南陸行五百里にして伊都国に至る」をそのまま読み解くと、末蘆国からの行程は次のようになると主張する。
- 伊都国が糸島半島に存在したならば、魏使は唐津で下船せず、壱岐から直接伊都国に向かったはずだ。それにもかかわらず唐津で下船し陸行したのだから、伊都国は海岸ではなく内陸部にあったと考えるべきだ。
- 糸島半島は唐津から東北の方角にあるから、「東南陸行五百里」に符合しない。やはり、倭人伝の記載通り、東南の方向に進んだと考えるべきだ。1里を60メートルとすると、五百里は30キロメートルであり、現代の地図で調べると、それは唐津街道の山間部から平野部に出るあたりである。この地点は自然の関所のような場所で、通過するものすべての管理が可能である。倭人伝には「千余戸あり。世々王あるも、皆女王国に統属す。郡使の往来常に駐まるところなり」とあり、この地形にピタリ合う。

古田氏など伊都国を糸島半島に比定する多くの学者・研究家は、唐津を出て陸上を糸島半島に向かう時、最初は海岸沿いに東南方向に進むことになるから、倭人伝の記述に合っているとする)
(2) 奴国と不弥国
伊都国から次の奴国への行程は、「東南奴国に至る、百里」となっているから、伊都国から東南へ6キロメートルであり、JR唐津線とJR長崎本線が交わるあたりである(図1)。
奴国から次のへの行程は、「東行不弥国に至る、百里」によって奴国から東へ6キロ進むと佐賀駅あたりになる。このあたりは当時は海だった。不弥国には港があったのだろう。
(3) 投馬国
不弥国から次の投馬国への行程は、「南、投馬国に至る水行二十日」となっている。投馬国の戸数が五万余戸(人口20万)という大集落であることから、有明海の南方向にある大平野で、かつ船で20日以内に行けるところは熊本しかない。
(しかし、有明海は波が穏やかであり、佐賀から熊本までの水行に20日を要するとは考えられない)
(4) 邪馬台国
投馬国から邪馬台国への行程は「南、邪馬台国に至る、女王の都するところ、水行十日陸行一月」となっている。佐賀から熊本まで20日を要したのだから、その半分の距離の場所、すなわち八代で上陸したはずである。
(それでは佐賀→熊本の水行に20日を要したという矛盾をそのままなぞっており、熊本→八代の水行に10日を要するのは同じ矛盾と言わざるを得ない)

八代から内陸に入ると山岳地帯であり、現在と同じように球磨川沿いの道を辿ったはずだから、人吉盆地に入ったことは間違いない。ここから先はどの方角に進んだかの情報はないが、倭人伝では邪馬台国が海岸に面していたように記述されていることから、邪馬台国は西都から宮崎に至る日向灘に面した地域にあったはずである。
(八代から日向灘沿岸部までの陸行に一月を要したとは思えない。この矛盾を説明していないのは残念である)
《池澤康コメント》
中田氏は医者で、専門は脳神経学である。科学者の視点で古代史の謎を解くことに挑戦したが、邪馬台国の比定に関するかぎり、科学の力が発揮されたとは思えない。そして、倭人伝最大の問題点である「水行十日、陸行一月」を解明していない。










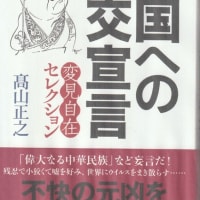








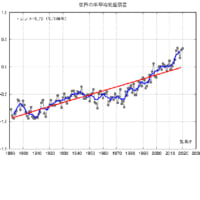
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます