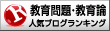よろしかったら人気blogランキングへ
よろしかったら人気blogランキングへ  クリックお願いします
クリックお願いします
ノーベル賞作家の表現の自由を守るためには、
老い先短い元軍人の人権など我慢せよ!
「集団自決訴訟」の控訴審判決で
小田裁判長の心の中で、
「被告のノーベル賞の重さと原告の短い老い先」が、
天秤に掛かっていなかったと誰が否定できよう、と「大江健三郎のいかがわしさ」で書いた。
期待した通り、夏の虫ならぬ時期遅れの蝿が飛んできた。
コメント欄の書き込みである。(笑)
≪当たり前だ。 (キー坊)
2008-11-05 22:52:44
ナニが人権なのだ。
ヨボヨボ元軍人が、書かれてから40年近くも経って、自分が読んだ事もなく、自分に関する記述も無い「沖縄ノート」が自分の名誉を傷つけたなどと、ノ-ベル賞作家を訴えた裁判で、裁判官は原告勝訴の判決を下すことできるか?
世界の物笑い、いや日本でも世間の物笑いになるだけだ。最高裁でも同じさ。 ≫
まともに相手にするのもバカバカしいが、ノーベル賞作家の前に思考停止する反日坊やの心情が垣間見れて興味深い。
猟官活動ならぬ「猟賞活動」という言葉の当否はさておき、
大江健三郎がノーベル文学賞獲得のため行った破廉恥な「猟賞行動」を知れば、殆どの日本人はノーベル文学賞作家大江健三郎を日本の恥として唾棄するであろう。
ちなみに「猟官制度」とは、アメリカ合衆国での政権交代における現象であるスポイル・システムの訳語で、スポイルとは(狩りの)獲物の意味、つまりは選挙という狩猟の成果で官職を得ると言うことである。
以下引用は評論家渡辺望氏が大江健三郎の「ノーベル賞作家」という虚構を粉砕した大江再批判の論文です。
◆
'08.10.18 ●渡辺 望氏 「ノーベル賞作家」という虚構 -大江健三郎への再批判-
実によく知られたことであるが、大江はノーベル文学賞を受賞したのち、自分は「戦後民主主義者」あるいは「民主主義者」である、という理由によって、文化勲章の受章は辞退した。大江以外の著名な戦後作家で他に、公的な文化賞を辞退した人物にたとえば、「戦友に申し訳ない」という理由で、芸術院会員になることを辞退した大岡昇平がいた。大江にしてみれば、大岡は志を同じくする人物であると考えているのであろう。しかし大岡は、昭和天皇が病に倒れたとき、その病状について、いろいろ心配や心痛を感じている、とも言っている。
私は大岡の芸術院会員辞退について、必ずしも共感を覚えない。しかし「戦友に申し訳ない」という大岡の言葉の「戦友」に、戦争を様々に現実的に経験した大岡の「卒直さ」というものを感じることはできる。大岡は国家に翻弄された戦友の心を思いやってはいるが、決して自分勝手にそれを解釈利用しているわけではない。
大岡の『俘虜記』に「戦友」という章があり、「・・・戦場から我々には何も残らなかったが、俘虜生活からは確かに残ったものがある。そのものは時々私に囁く。『お前は今でも俘虜ではないのか』と。・・・」という言葉でその章はしめくくられているが、大岡の辞退は、この言葉によくあらわれているように、「耳を澄ます」という誠実な行為をどこかに感じさせるのである。彼は「物書きだったら、公の栄誉なんか嬉しそうにもらうなよ。おまえさんはたまたま生き残ったんだからさ」という亡き戦友の声をどこかに聞いた。単にそれだけだ、と大岡は言おうとしたのではないか、と私は思う。大岡は、その亡き友の声に耳を澄まし、昭和天皇の病状を心配するということもしたのである。「俺達が恨みがましく思っているのは決して天皇に対してじゃない、戦争なんてそんな単純なものじゃない、もっと別のものに対して個々別々に、自分たちは恨みがましく思っているんだ」というふうに。
「耳を澄ます」というと、何を観念的なことを、と言われるかもしれないが、戦争体験に意味的に関連して現実的な態度をとるときに、何よりもあるべきは「耳を澄ます」という行為に他ならない。「耳を澄ます」という実感がない戦争に関しての思想の語り手の発言は、左右問わずすべて「贋物」である。
もちろん、若い頃からの無頼仲間だった小林秀雄や河上徹太郎が老年になるにつれて、文化勲章や芸術院会員を受け入れていくことに対しての、大岡の皮肉の意味を推測することもできる。しかしこの「皮肉」もまた、文人の仲間うちでわかりあえる人間的な何かであって、決してイデオロギー的なものではない。いずれにしても大岡昇平の辞退の理由はどこか人間的な匂いが感じられて、それほどの違和感を私は覚えない。それは大岡の作品の大体に対してもそうである。「イデオロギー」より「こころ」が優先する人物の匂い、とでも言うべきであろう。
しかし、大江の文化勲章辞退は、大岡の芸術院会員辞退の卒直さや人間臭さとまったく異なっている。ノーベル文学賞と文化勲章に価値的な区別をつける大江の意識には、少しも「こころ」の匂いが登場しない。「耳を澄ます」という行為も、人間的な「皮肉」も、大江を巡る一連のノーベル文学賞・文化勲章を巡るエピソードにまったく無縁なことなのだ。大江の文化勲章辞退の理由を裏返せば、ノーベル文学賞は、「戦後民主主義」「民主主義」にふさわしい賞である、ということ、日本の皇室から勲章をもらうことは、日本の皇室が有している反「戦後民主主義」的性格、反「民主主義」的性格からして、自分にふさわしくない、ということになる。しかし大江が言う「戦後民主主義」も「民主主義」も、大岡の「戦友」の確かさに露ほども及ばない。耳を澄まそうにも、それが単なる記号であって、少しも「人間」でも「こころ」でもないのである。
そしてそもそも私の考えでは、ノーベル文学賞はその実体を追えば追うほど、文化勲章に遥かに増して、「戦後民主主義」「民主主義」にふさわしくない賞なのである。大江は、そのノーベル文学賞を、狡猾な戦略で、自分及び自分の政治的方向性の友軍と化す作為をついに完成させ、「ノーベル賞作家・大江健三郎」という終身的肩書きを手に入れた。「ノーベル賞作家・大江健三郎」のさまざまな醜態を前にして、ノーベル文学賞というものがいったい何であるか、ということを私達日本人は考察し認識することが求められるのだ、と言ってもいいであろう。いずれにしても、このノーベル文学賞を巡る大江の周囲に、もう一つの大江への根底的な批判が成立するということを考えなければならないのである。
まず以下の大江の文章を引いてみよう。これはノーベル文学賞を受賞する2年前の大江が、スウェーデンを訪れたときにおこなった講演の記録である。
しかもそれは実体としてなにかをあたえられたというよりも、遠方にある実体に向けて、いつも心がそそら
れている生き方が、自分の習慣になったということでした。あこがれという詩的な言葉におきかえてしまえ
ば、美しく単純化されそうですが、それに加えて、暗く恐ろしいものですらもある巨大な力が、北欧から私を
吸引しているようで、それゆえにこそ、なかなか実際に北欧へ旅をする気持ちになれなかったのです。
しかし「あこがれ」プラスαは強く奥深くあり、それにつき動かされるようにして、スウェーデンボルグの神秘
思想からベルイマンの映像まで、私は北欧からの呼び声にいつも面と向かってきました。さら にその心の
うちの動きを、北欧の音楽がもっとも端的に把握しなおさせてくれたとも感じています。
『北欧で日本文化を語る』
この講演での大江の言葉から、第一印象として気味悪いほどのスウェーデン、北欧への「おべっか」を感じるのは私だけではないだろう。他のものも含めて大江のスウェーデンについての論考には、異常な犯罪率や極端な重税、若者の性文化の荒廃など、スウェーデンが抱える現状の問題にはいっさい触れられていない。この一連の大江の北欧の講演や北欧への平凡な賛美のメッセージは、他ならぬノーベル文学賞受賞のための営業活動に他ならないからである。
私はこうした大江の営業言動から、かつて松岡洋右が日ソ中立条約を結ぶためにスターリンの前で演じた口八丁を連想する。外相としてクレムリンを訪れた松岡はスターリンにむかって様々な「おべっか」を言う。たとえば「日本は元来、きわめて共産主義的民族である。それがアングロサクソンの個人主義・資本主義に毒されたのである」だから、日本とソビエトは根源的に盟友なのだ、松岡はと言うのである。日本国内ではコミュニズム弾圧の嵐が吹き荒れている中、よくこんな「おべっか」を、共産世界最大の独裁者に向けて、恥じらいもなく言えたものだ、と思う。松岡という人間は昭和天皇に見抜かれたように、ほとんど法螺吹き屋である。そして松岡の「おべっか」は、とうとう最後は日ソ中立条約の締結を成就させてしまう。
スターリンの心が動いたのは、言うまでもなく緊迫したヨーロッパ情勢への認識なくして考えられない。しかし松岡の営業行為的な「おべっか」は、そのあまりのすさまじさのゆえ、スターリンの心の表層を刺激して、その認識とうまく融合し、それを動かしたのである。営業が成功するとは、こういうことである。比べて、大江の場合は、このような水準の低い営業をおこなう相手のノーベル文学賞の何を刺激して融合を遂げたのか。それは「ノーベル文学賞」そのものにある、日本と日本文学に対しての、おどろくほど低い関心なのである。
ところで、日本の近代文学にとってノーベル文学賞は、いかなる意味あいをもっているのであろうか?
私が大学に入りたての1990年代初頭、文学の話題を語り合う仲間うちで、次の日本人のノーベル文学賞者が誰であるか、その話題が毎日のように語られていた。川端康成以来の日本人のノーベル文学賞受賞が迫っている、という話が広まっていた。圧倒的な第一候補は安部公房であり、その安部の後に、遠藤周作と大江健三郎が続く形で候補であった。その後、安部は1993年に急死し、その翌年、大江がノーベル文学賞を受賞することになる。
私自身も他の文学愛好者の多分に漏れず、当時、ノーベル文学賞とは文学にとっての絶対的権威であり、川端康成以来の受賞者が我が国に再び現れることが日本文学の地位を高めるとナイーブに信じていた。個人的には大江の文学に共感することは少なかったが、安部と遠藤の作品については高校時代から熱心な読者であった。そのことはおくとしても、日本国民としてというより文学ファンとして、日本人に文学の絶対権威であるノーベル文学賞が授与されるのではとドキドキした気持ちで発表を待ったものである。だが、その私のノーベル文学賞崇拝を以後ばったりと止める一冊の本があらわれる。古本屋で手に入れた、ドナルド・キーンと徳岡孝夫による三島由紀夫についての追悼の本『悼友紀行』である。
1960年代後半、川端康成と三島由紀夫の二人がノーベル文学賞の受賞を最後まで争い、結局、川端に決するその裏の具体的事情について明かす『悼友紀行』の徳岡の次のような文章を読んで、私はノーベル文学賞への崇拝的な感情がいっぺんに消し飛んだのをよくおぼえている。
ノーベル文学賞の順番が日本にまわってきたとき、川端康成と三島由紀夫の名前が出た。どちらに与え
ても不都合はない、という判断だった。ところが、最終的な決定を下すスウェーデンに、日本文学の専門家
がいない。いきおい、英訳、独訳から推測するほかない。さいわい、あるいは不幸にも、1957年のペンク
ラブ大会で日本に来て2週間ほど滞在したスウェーデンの文学者がいた。ほかにエキスパートがいないも
のだから、彼はノーベル賞委員会に対して重要な助言をする役目を与えられた。もちろん、2週間の日本
滞在で、日本の作家の比較や評価ができるはずがなかった。ところが、その人物は、キーンさんが訳した
『宴のあと』読んでいた。『宴のあと』は都知事選に取材したもので、登場人物は革新党の候補である。そ
んなところから『宴のあと』は政治小説で、書いたミシマ・ユキオはきっと「左翼」だろうということになった。
彼の助言をいれて、ノーベル賞はより穏健で日本的な美を書いた作家、川端康成が受賞することになっ
た。
徳岡孝夫・ドナルドキーン『悼友紀行』
三島由紀夫を「左翼」と誤認したこともさることながら、選考委員会は一人の選考委員が読んだ『宴のあと』の感想でもって三島という文学者への総合的評価をくだす、という信じがたい短絡を平気でおかしていたのである。
しかもこの日本文学の専門家は、その『宴のあと』の作品内容さえ誤読している。『宴のあと』はどこをどう読んでも政治小説ではない。確かに『宴のあと』は都知事選の革新陣営の候補だった元外相の有田八郎の妻を主人公にして描いているが、この妻を通して、中年女性の生きる姿、そのいろいろな過去を鮮やかに描きつくした現代小説であって、「政治」はあくまで舞台提供されただけ、この小説は政治小説ではまったくないのである。この『宴のあと』を政治小説と勘違いするのは、よほどの翻訳ミスがない限り、粗筋しか読まない人間に限られると言わなければならない。
三島はこの有田からプライバシー侵害で訴えられ、有名な憲法訴訟に発展している。「革新陣営の候補」すなわち左翼陣営の怒りを買って訴えられているのだから、三島が「左翼」であるという判断はますます成立しないはずである。しかし当時日本の文学世界を大きく揺るがしたこの事件に関して、ノーベル文学賞選考委員会はまったく無知なのである。徳岡が語るこのエピソードの時期、すでに三島の『宴のあと』訴訟は日本国内で、有名な事件になっているにもかかわらず、である。
こう考えると、川端へのノーベル賞受賞は、ある意味、「誤謬」といってよい判断だったと言わなければならないであろう。のみならず、私は日本文学自体が何か侮辱されたような憤りさえ感じた。要するにノーベル賞選考委員会は日本にも、日本文学にも、ほとんど無知な人間たちによって構成され、そしてさまざまな決定をしているのだ、と考えなければならない。私はそう思って、以後、ノーベル文学賞に対する関心をまったく喪失したのである。(続く)