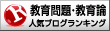|
言論封殺魔こと佐藤優氏は、「沖縄には『同調圧力』もなければ、沖縄の新聞に偏向はない」と沖縄紙に擦り寄った意見を述べている。 佐藤氏には申し訳ないが、沖縄には「同調圧力」もあれば、新聞の偏向も存在する。 当日記のように「沖縄タイムス」「琉球新報」とは異なる意見を発信していると、 「沖縄人でこんな意見を吐くはずはない」とか 「沖縄人に成りすました移住者だ」とか 挙句の果ては「沖縄の敵だから、許さない」とか、そのた数多くの罵詈雑言の書き込みを受けた。 罵詈雑言の大部分が沖縄人を名乗っている。 地元紙と意見が違うだけで「沖縄の敵」と言われるのではたまったものではない。(笑) まさか沖縄紙の記者がこのような下劣な書き込みをするとは思わないが、 とにかく、沖縄在住で地元紙と異なる意見を主張することは他県の人たちには想像できないほど疲れる!(ふ~!) もっとも、それだけ痛いところをつれて脊髄反応しているのだと思えばかえってやる気も出てくるのだが・・。 何よりも、「同調圧力」や新聞の偏向が存在するという一番の証拠は、 当日記が沖縄タイムスや琉球新報に投稿しても決して掲載されることはないことである。 何? 掲載に耐える内容ではない? こりゃ又失礼しました。(笑)
沖縄紙は言論封殺の外に印象操作も得意技とする。 「集団自決訴訟」についても、訴えられたのは大江健三郎と岩波書店の両被告のはずだが、 地元紙はあたかも「沖縄県民全員が訴えられた」かのような印象操作をして裁判官に場外から圧力をかける。 まるで「全沖縄県民が被告」といった論調で、関連記事には「県民の理解」や「県民感情」といった言葉を多用して、 「県民を敵に回したら怖いぞ!」と裁判官に威圧をかけている。 大阪高裁の控訴審判決にも地元紙は「県民納得」と、得意の述語を使用した。(笑) ⇒ 岩波・大江訴訟 県民納得の妥当判決だ (琉球新報) これでは、被告側を沖縄県民ぐるみで応援しているように錯覚してしまうではないか。(それが狙いなのだが)
ところで、言論封殺魔こと佐藤優氏が長期連載コラムを掲載している琉球新報も言論封殺では人後に落ちない大魔王である。 これについては次のエントリで詳述してある。 |
以下は渡辺望氏の「大江批判」の最終章です。 ◆ |
'08.10.18 ●渡辺 望氏 「ノーベル賞作家」という虚構 -大江健三郎への再批判-
(承前)
『あいまいな日本の私』
この『あいまいな日本の私』で大江は、自分の「営業」行為を物の見事に締めくくっている。
大江は冒頭で、スウェーデンの国民文学作品の一つである『ニルスの不思議な旅』に手ばなしの賞賛をおくったのち、川端康成がかつておこなったノーベル賞受賞講演『美しい日本の私』に触れる。そこで大江は川端の講演内容には曖昧=「vague」さにみちたものだった、と指摘する。
そう指摘した上で、「vague」では日本の文化や歴史を説明するには足りないもので、「ambiguous」という、両義的という意味での「曖昧」の方が、川端が説明した「日本」ということより、より「日本」を説明しやすいのだ、と大江はいう。そしてこの「両義的」という意味での「曖昧さ」がゆえに、近代の日本は「西欧化」と「アジア侵略」に分裂したのだ、ゆえに日本人は両義的な意味での「曖昧」があると論をすすめ、そののちに、大江は上記の二つの文章を決意表明的に語っているのである。
この「曖昧」という言葉の引っくりかえしは、この大江の講演録を幾度読んでも文章上の脈絡がまったく認められない。日本人批評として「vague」と「ambiguous」の間にどんな関係があるのかが少しも文章上、説明されないまま、文章(講演)がどんどん進んでいってしまう。そしてそもそも、川端の「美しい日本の私」を読めば、大江が勝手に解釈しているような曖昧さ、「vague」というものはどこにも認められない。
大江が川端の講演の何処に「vague」を感じたのか明確に記していないため、私達は独力で川端の講演録から大江が「vague」を感じた部分をさがさなければならない。大江の難解極まるこの『あいまいな日本の私』を幾度も精読すると、大江が川端のノーベル賞受賞講演内容で感じた「vague」の部分とは、どうやら次の二つの部分、川端が日本人の「無」を、禅宗的な概念に近いものだと説明するところであることが明らかになる。
a)禅宗に偶像崇拝はありません。禅寺にも仏像はありますけれども、修行の場、座禅して思索する堂には
仏像、仏画はなく、経 文の備えもなく、瞑目して、長い時間、無言、不動で坐っているのです。そして、無念
無想の境に入るのです。「我」なくして「無」になるのです。この「無」は西洋風の虚無ではなく、むしろその
逆で、万有が自在に通う空、無涯無辺、無尽蔵の心の宇宙なのです。禅でも師に指導され、師と問答して
啓発され、禅の古 典を習学するのは勿論ですが、思索の主はあくまで自己、さとりは自分ひとりの力でひ
らかねばならないのです。そして、論理よりも直観です。
b)私の作品を虚無と言う評者がありますが、西洋流のニヒリズムという言葉はあてはまりません。心の根本
がちがうと思っています。道元の四季の歌も『本来ノ面目』と題されておりますが、四季の美を歌いながら、
実は強く禅に通じたものでしょう。
『美しい日本の私』
川端が「美しい日本の私」で繰り返して苦心して説明しようとしているのは、日本文化における「無」というのは、ニヒリズムというような消極的概念でなく、ある種の肯定的な概念である、ということである。川端の説明は少しも「vague」なものではない。
しかし言うまでもなく、キリスト教文明的な意味でのニヒリズムという概念に依存する限り、川端のいう「無」の説明は不明確でよくわからない、すなわち曖昧=「vague」としか思えない、と言える。現代の西欧ではよほどラディカルなヨーロッパ中華思想の持ち主でない限り、そんなふうに意地悪に日本文明をとらえる人間はいないはずであるが、大江は自身がそのようなラディカルなヨーロッパ中華思想に依存するという安全策をとる。
すなわち、大江が川端に感じたという「vague」とは、西欧文明の基準からすれば川端の言っていることは「意味がよくわからない」ということ、西欧文明的な感性にまったく依存しきってみせて、川端の苦心を暗にからかっていることに他ならない。川端の言う「無」は、西欧のニヒリズムからすれば「vague」だ、ということなのである。このような「曖昧」という言葉のほとんど悪意的な操作をまず下地において、大江の「おべっか」が、スウェーデンから、西欧文明全体へと拡大していく。こうして、ノーベル賞を先んじて受賞した川端の言葉さえ巧みに利用し、大江はノーベル賞受賞に関しての営業行為を完成していくのである。
たとえば1)の文章においてなぜ「西欧先進国・アフリカ・ラテンアメリカとの深い溝」と「アジアにおいて日本の軍隊が犯した非人間的行為」が、一つの文章内で大江は併記したのであろうか?あるいは2)の文章においてなぜ、日本国憲法の平和主義原理が、「それは、良心的徴兵拒否者の寛容において永い伝統をもつ、西欧において、もっともよく理解される思想ではないでしょうか」というふうな文章の付け加えを大江はしたのであろうか?
大江が1)の文章で言っているのは単なる自虐史観ではない。大江の中での対アジアの自虐史観を、ヨーロッパとのかかわりにおいてまで、引き伸ばして自虐的に受け入れよ、と自虐史観よりも徹底的なことを主張しているのである。2)の文章で言っていることは、単なる日本国憲法万歳ではない。日本国憲法の平和主義原理は、アメリカの押し付け以前に、ヨーロッパ人の精神的伝統に由来したものである、日本人はそのことに西欧に感謝しているのである、と言いきっている。これは絶対平和主義よりもさらに徹底された平和主義であるというべきであろう。これらの決意表明を大江は、彼の基準からすれば、明らかに反民主主義的で、侵略主義的の権化のようなグスタフ3世の創設したスウェーデンアカデミーの諸氏にむかって語りかけているのである。
ここに認められるのは、あえて喩えるならスウェーデンさらには西欧への大江自身のまことに身勝手な、「無条件降伏」であると言わなければならない。たとえば、大江はノーベル賞受賞の前年のニューヨークでの大きな講演会で、「三島由紀夫の自殺は、あの自殺のパフォーマンスの主張が、西欧やアメリカに対して閉じられていたことが問題なのです」(『回路を閉じた日本人でなく』)と驚くべき発言をしているが、これは『あいまいな日本の私』の先鞭をつけた言動であると言うべきだろう。つまり彼は川端や三島という先人の作家まで巻き込んで、「無条件降伏」への儀式を盛り上げようとしたのだ。大江のノーベル文学賞受賞、それは大江自身が仕組んだ狡猾きわまる「無条件降伏」行為に他ならないものだったのである。
大江がここまでして「ノーベル賞作家」という肩書きを欲したのだ。賞を欲する作家としてのエゴイズムやナルシズムそのものを私は否定しようとはもちろん思わない。賞によって自分の作家的地位を高めようとするのは、作家の正しい職業的本能である。しかし、作家は自分を生かすために賞を欲するのであって、賞によって生かされているのではない。大江の内面ではこの図式がまったく逆転している。
賞に異常に執着し、作家としての本能を顕わにしたという文学史上のエピソードとして、芥川賞を巡る太宰治の有名なエピソードを思い出すことができる。太宰はどうしても芥川賞が欲しかった。そのために選考委員の川端康成に幾度も懇願の手紙を書 いて送る。その手紙は執拗というより惚稽なほどのもので、つい苦笑したくなるほどの喜劇さえ感じられる。「・・・労作生涯いちど報いられてよしと客観数学的なる正確さ一点うたがひ申しませぬ。何卒私に与へてください。一点の駆引ございませぬ。深き敬意と秘めたる血族感とが右の懇願の言葉を右の懇願の言葉を発せしむ様でございます。困難の一年でございました。死なずに生きとほしたことだけでもほめて下さい・・・」 しかしこの執拗さが逆作用し、川端や同じく選考委員の佐藤春夫の反感を買い、太宰は受賞を逃してしまう。太宰がここまで受賞に執着したのは、名家である太宰の実家へのせめてもの示威を彼が欲したのだ、ということが定説になっている。
しかしこの時期(昭和10年頃)、芥川賞は現在のようなネームバリューをまったくもっていなかったのである。芥川賞が文壇の権威的地位をもつようになったのは、実は昭和30年以降のことで、それまではこの賞を受賞しても、それが文壇人としての勲章になるということはまったくなかった。したがって、太宰が功名心から芥川賞を欲した、というのはおそらくあたっていない。比べて彼が当時、薬物(パピナール)中毒に苦しんでいて、その薬代あるいは中毒症状の治癒のために、芥川賞の賞金を欲していたという解釈はずっと信憑性が高いが、しかしそれでも太宰の足掻きのすべてを説明しつくしてはいないと思う。賞金ということならば、他の賞に足掻いてもいいわけだが、太宰はあくまで芥川賞に執着したのである。
私としては、賞金目当てでという解釈のさらにもう一つの有力な解釈、太宰が芥川龍之介とその作品に心酔していて、それがゆえに芥川賞という名前の賞を欲した、ということを付け加えると、太宰の子供っぽい、しかし人間臭い面が説明しつくせるように思われる。賞を求める作家の気持ちというものは、自分の文学形成にかかわってくれた人間への感謝、しかしその感謝を自分の栄誉と結び付けたいという、一見すると矛盾した人間性の発露にこそある、と私は思う。芥川賞を欲するという太宰の行為は、それが実によくあらわれているように感じられる。
この太宰のエピソードを踏まえて、もう一度、大江の『あいまいな日本の私』に戻ってみることにしよう。
大江の論理的詐術と「おべっか」の本領の極みは、実はたいへん分かりにくい形で、この受賞講演の後半部分にあるのである。
大江はこの講演の後半の部分を、彼の大学時代からの師匠でありフランス文学者の渡辺一夫からの影響とその思想についての解説に割いている。大江は渡辺から、フランスのユマニスムの思想の寛容の精神を継承した、と繰り返し説く。
大江に果たして、フランス・ユマニスムの思想の寛容が存在するのかどうか自体、大いに疑問である。が、確かに渡辺は大江の大学時代の教え手であり、フランス文学のおもしろさを大江に教えた人物であるのは間違いない。だが大江は、渡辺一夫に加えてもう一人の彼の青春時代の彼の影響元について触れることをここでしていない。
大江は確かに寛容の精神を渡辺から学んだのかもしれない。しかし、一文学青年であった大江を、60年安保をはじめ様々な「政治の季節」へと誘導する根源となり、大江という文学者の方向性を決定づけたのは社会参加の精神だったはずである。大江という作家を卒直にみれば、寛容の精神より社会参加の精神が遥かに勝っている。
だいたいこの講演録で大江が退屈に狡猾に繰り返す左翼政治的な言動からして、大江が青年期 に身につけた社会参加の精神に由来するというべきなのである。
大江文学に多少なりとも通じていれば、社会参加の精神についての精神の在り方を大江に与え、同時に初期の大江の小説の作風についても決定的な影響を与えたのがサルトルであることを知っているはずである。しかし大江はこの講演でサルトルについて触れることをまったく避けている。渡辺を通じて知ったとこの受賞講演でもっともらしくいうラブレーなど、大江に本質的な影響などほとんど与えていない。だいたい大江は渡辺の指導のもと、東京大学でサルトルを専攻したのである。サルトルなしで、大江文学を語ることは不可能であり、それは大江本人が一番よく自覚しているはずである。なぜ大江はサルトルについて語ることを避けたのであろうか?
理由の推測は簡単である。サルトルは1964年にノーベル文学賞に選出された。が、スウェーデンアカデミーの受賞基準のあまりの不公平さ、政治的性格を厳しく批判して、受賞を辞退したのである。このノーベル賞受賞式で、そのようにノーベル文学賞を軽蔑したサルトルについて触れないという「不誠実」自体が大江の、ノーベル文学賞への「おべっか」なのである。
この異様なほどに徹底された「おべっか」こそ、大江の作家としての根幹にかかわることだと言わなければならないであろう。太宰があれほどまでに足掻いて芥川賞を求めたことが、心の中の師を自分の功名心の中で求める、というような作家らしい人間味あるエゴイズム、ナルシズムが大江にはまったくみられないのである。
ここに至れば、大江の文化勲章の辞退ということも、大江にとっては、ノーベル賞受賞という「無条件降伏」という儀礼への一部分を形成したものである、ということが明らかになるであろう。先人の作家も師匠格の作家も、そして文化勲章をはじめとする日本文化も全部巻き込んで、彼は「無条件降伏」というノーベル文学賞の受賞を、ついに完成させた。それがゆえに私は「ノーベル賞作家・大江健三郎」という肩書きは、大いなる虚構としてしか感じられず、それを言葉にすることを自らに禁じているのである。
◆
|
|










 よろしかったら人気blogランキングへ
よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします。
クリックお願いします。