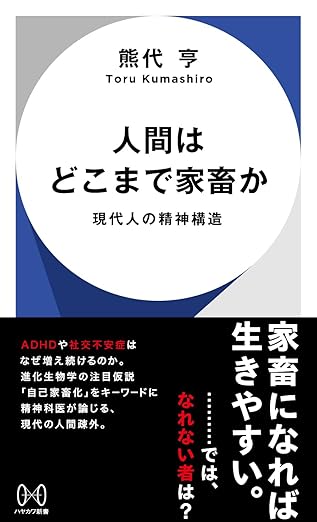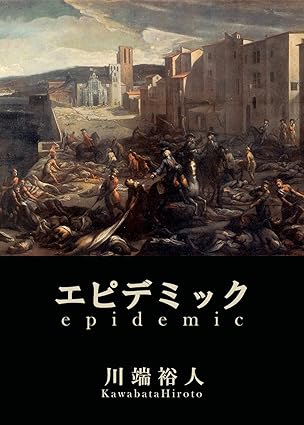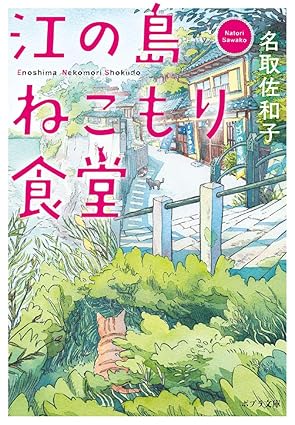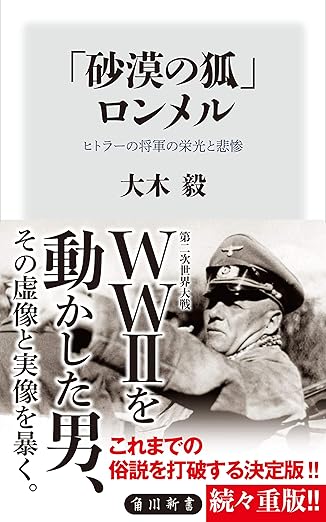意識が生まれる仕組みを科学的に解明し、意識を持つ機械を作り出せるのか。これを考えるとき、まずは意識とは何か? この定義から入ることになります。
この本では、リンゴを見たとき、「あ、リンゴが見えた」と思うこと(クオリア)を意識と定義しています。デジカメでリンゴの写真を撮ったときは、色のドットの散らばりを機械が認識しているだけなので、リンゴだとは思っていませんから、意識ではありません。
また、人間は、目に見えていても意識に上がらない視野もあり、視覚は多くの面で脳が作り出したものなのです。これを簡単な錯覚を伴う図なので、読者に体験させながら、実際のものと脳が修正して、わたしたちの意識に上げてくるものは違うと体感させられます。
風景の色は、実際にはついていないと言います。電磁波(光)の波長の違いによって違う色に見えるのですが、赤と紫の波長は、可視光線の中の長い・短いの両端にあるのに、色彩として見たときは近い関係にあります。つまり、波長の長短をグラデーションのように感じているのではなく、脳が作り出した色彩を意識しているのです。
また、よく言われることですが、行動が先で意識が後という脳の仕組みも明らかになっており、右手を上げようと意識する前に、すでに右手を上げる信号が脳から発信されているのです。意識は後付けなのですが、あたかも先だったように修正されるのが脳の奇妙なところです。
捉えどころがない課題を一つずつ解決していく科学者たちの苦闘が描かれています。意識は主観、科学で扱うのは客観。機械に意識を持たせることが出来るのか。
グーグルのレイ・カーツワイルは、21世紀半ばまで意識を機械に移植できると予言していますが、どのように人間の脳と機械を接続させ、それを確認できるかの技術的な解説もされていました。
さも意識があるようにふるまうAIの実用化は可能でしょうが、ほんとうに意識があるとわかるのは、脳と接続された機械が見たものが、脳に意識として見えることが必要となります。
この本を読んだ限りでは、まだまだ、迷宮の入口に立っている感が強かったですが、わたしが生きているうちに、意識の自然則が解明されることを期待します。