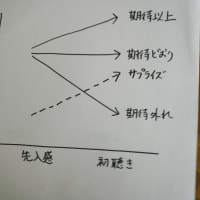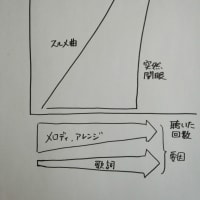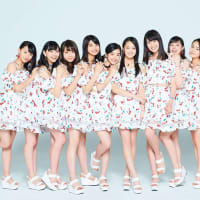森高千里についてはこのブログでも時々言及しているが、彼女の魅力について、一度まとめて書きたいと考えていた。
年末のBSフジで『アワ・フェバリットソング 私がオバさんになっても』という番組があり、録画しておいたのを視聴したのをきっかけに、私も論述を試みることにした。
初期の数曲を除き、ほとんどの持ち歌の作詞を森高自身が手掛けている。その独特の歌詞が、彼女の魅力の1つであることは、衆目の一致するところであろう。
彼女の歌詞のどういうところが独特なのか考えたが、「普通の人の日常の生活を、日常の言葉遣いでリアルに描いている」ところだと私は考える。更に付け加えれば、地方在住者の歌が多い。
その代表例と言えるのが『渡良瀬橋』(1993)だ。足利市に実在する橋をモチーフに、その近くに住む女性が、かつて交際していた男性のことを今も思って暮らしているという歌詞だ。美しいメロディーと凛とした歌唱も相俟って、ヒットした。今も多くの人の心に響く歌だと思う。後に松浦亜弥がカバーしている。
何回聴いても腑に落ちないのが、なぜこの2人は別れたのだろうということだ。そこは直接には描かれていない。彼は「電車に揺られ」彼女に会いに、おそらくは東京から頻繁に来ていた。そして「ここに住みたい」とも言った。実際、2時間くらいで着く距離だし、遠距離恋愛という程でもない。でも2人は別れてしまった。
彼女は「あなたがこの街で暮らせないことわかってた」、そして「私ここを離れて暮らすことできない」と歌う。つまり、それぞれが自分の今いる場所を離れられないことが別れの理由だったようだ。
それぞれが今いる場所を離れられない理由にまでは言及がない。彼の場合は、実家が開業医で後を継がなければならないとか、マスコミとか大学の研究者とか特殊な仕事で、当時はリモートワークなど無かった時代なので、足利に引っ越すことはできなかったのかもしれない。でも、2時間くらい通勤できなくもないとも思う。彼女の方も、もしかしたら足利の開業医の一人娘かもしれないし、あるいは親の介護が必要とかいう事情かもしれない。ただ、江戸時代ではあるまいし、愛があれば乗り越えられない障害ではないように思う。当時は珍しかったかもしれないが、別居婚という選択肢だってあるだろう。
彼女は今でも彼のことが好きで「願い事1つ叶うなら あの頃に戻りたい」と歌い、彼に電話したくなり公衆電話の受話器を持ったりもしている。また、川原で「風邪を引いちゃいました」などと軽い調子で語りかけていて、「何度も悩んだ」末の永遠の辛い別れだった風でもない。だったら、電話したいならすればいいし、今からでも遅くない、彼のところへ会いに行けばいいのではないか、と思ってしまう。それとも、彼はもう別の女性と結婚していたりするのだろうか。
決定的な理由が描かれていないので、歌を聴いた人間が自由に、無限に、色々な物語を想像することができる。そういう私も30年間想像し続けていて、それだけでも人生が豊かになっている。
『一度遊びに来てよ』(1994)は、地方都市の大学で仲が良かったボーイフレンドが卒業して東京に戻ってしまい、寂しい、一度遊びに来てほしいと誘う歌だ。彼女にとっては地元の大学に、東京生まれの彼が進学して来たのは珍しいが稀にはあることだろう。4年間を友達として楽しく過ごしたが、恋人にまではなれなかった。彼女はそれを心残りに思っているようだ。「コスモスが咲くキャンパスが懐かしいでしょう?」と歌っているから、卒業後半年経った秋なのだろうか。離れてから一層好きな気持ちが増しているのかもしれない。
彼女の母親が言った「東京は遠いよ」という言葉が、何気なく効いている。地方在住者にとって、子どもが地元に残ってくれることは何より望まれることなのだ。だから、東京の有名私大より地元の国立大の方が高評価だったりする。中島みゆきの『ファイト!』のように「出て行くんなら身内も住めんようにしてやる」とまで言われることは稀だろうが、都会に出て行くことの後ろめたさみたいなものは、濃淡こそあれ今も確かに存在する。そういう無言の圧力は『渡良瀬橋』の彼女が足利を出られない理由の一部になっているのかもしれない。
歌の中では「一度遊びに来てよ 私に逢いに来てよ」と彼女は積極的だ。彼に「好きな人ができていたらどうしよう」などと心配もしている。彼女としては、彼もまだ彼女のことが好きでいてくれると信じたいのだ。でも、一抹の不安も拭えない。そんな揺れ動く気持ちが伝わってくる歌だ。
彼の方も同じように思っていて本当に遊びに来るのか、それとも彼女はただの友達としか思っておらず、今は都会の生活の方が大事なのか、それは聴いた人間がどちらでも想像すればいいことだ。
『この街』(1991)も、地方在住者の日常を歌っていて秀逸だ。都会に出て行く彼氏や友達を見送り続けるのは寂しいが、「でもこの街が大好きよ 生まれた街だから」ときっぱり言い切る潔さ、単純さがいい。森高の歌の主人公は、あんまり1つのことにくよくよ悩まないのだ。
『アワ・フェバリットソング』の中で峯田和伸が絶賛していたのは「田んぼも」という言葉の選択センスで、他のソングライターなら絶対選ばない言葉だと私も思う。更に言えば、その後に続く「魚も安くて新鮮」というフレーズもなかなかだ。市役所の地域振興課のキャッチフレーズのようだが、これが森高の真骨頂。日常会話の言葉で、日常の生活を描いているのだ。
地方在住者の日常を描いた歌として忘れてならないのは『長男と田舎もん』(1997)だ。地方都市で付き合っているカップルの歌だ。男は長男であるがゆえに家業を継がされた。女は今18歳で、来年高校を卒業し、地元で就職するつもりだ。都会に出たい気持ちもあるが、お互い長男と田舎もんで、無理に決まっている。そういう諦めの境地で、ダラダラと毎日を送っている。
ただ、これが森高のすごいところなのだが、そういう諦めの境地でのダラダラとした生活が決してネガティブ、無気力には聴こえないのだ。「この町は田舎で最低、夢も無い」などと毒づきながら、現実を受け入れて楽しんでいる気配を感じるので、聴いていても嫌な気分にならないのだ。彼らを今風の言葉で言えば、「マイルドヤンキー」だろう。そんな言葉が無かった時代に、リアルに生き生きと描き切っていたのは素晴らしい。
「今日はどこのホテルに行こう?」と堂々と歌っているのは、彼女が18歳の設定なので法令違反でこそないが、あまりに生々しい歌詞だ。でも、このカップルにとっては当たり前の日常なのだろう。これが森高流のリアルなのだ。
年末のBSフジで『アワ・フェバリットソング 私がオバさんになっても』という番組があり、録画しておいたのを視聴したのをきっかけに、私も論述を試みることにした。
初期の数曲を除き、ほとんどの持ち歌の作詞を森高自身が手掛けている。その独特の歌詞が、彼女の魅力の1つであることは、衆目の一致するところであろう。
彼女の歌詞のどういうところが独特なのか考えたが、「普通の人の日常の生活を、日常の言葉遣いでリアルに描いている」ところだと私は考える。更に付け加えれば、地方在住者の歌が多い。
その代表例と言えるのが『渡良瀬橋』(1993)だ。足利市に実在する橋をモチーフに、その近くに住む女性が、かつて交際していた男性のことを今も思って暮らしているという歌詞だ。美しいメロディーと凛とした歌唱も相俟って、ヒットした。今も多くの人の心に響く歌だと思う。後に松浦亜弥がカバーしている。
何回聴いても腑に落ちないのが、なぜこの2人は別れたのだろうということだ。そこは直接には描かれていない。彼は「電車に揺られ」彼女に会いに、おそらくは東京から頻繁に来ていた。そして「ここに住みたい」とも言った。実際、2時間くらいで着く距離だし、遠距離恋愛という程でもない。でも2人は別れてしまった。
彼女は「あなたがこの街で暮らせないことわかってた」、そして「私ここを離れて暮らすことできない」と歌う。つまり、それぞれが自分の今いる場所を離れられないことが別れの理由だったようだ。
それぞれが今いる場所を離れられない理由にまでは言及がない。彼の場合は、実家が開業医で後を継がなければならないとか、マスコミとか大学の研究者とか特殊な仕事で、当時はリモートワークなど無かった時代なので、足利に引っ越すことはできなかったのかもしれない。でも、2時間くらい通勤できなくもないとも思う。彼女の方も、もしかしたら足利の開業医の一人娘かもしれないし、あるいは親の介護が必要とかいう事情かもしれない。ただ、江戸時代ではあるまいし、愛があれば乗り越えられない障害ではないように思う。当時は珍しかったかもしれないが、別居婚という選択肢だってあるだろう。
彼女は今でも彼のことが好きで「願い事1つ叶うなら あの頃に戻りたい」と歌い、彼に電話したくなり公衆電話の受話器を持ったりもしている。また、川原で「風邪を引いちゃいました」などと軽い調子で語りかけていて、「何度も悩んだ」末の永遠の辛い別れだった風でもない。だったら、電話したいならすればいいし、今からでも遅くない、彼のところへ会いに行けばいいのではないか、と思ってしまう。それとも、彼はもう別の女性と結婚していたりするのだろうか。
決定的な理由が描かれていないので、歌を聴いた人間が自由に、無限に、色々な物語を想像することができる。そういう私も30年間想像し続けていて、それだけでも人生が豊かになっている。
『一度遊びに来てよ』(1994)は、地方都市の大学で仲が良かったボーイフレンドが卒業して東京に戻ってしまい、寂しい、一度遊びに来てほしいと誘う歌だ。彼女にとっては地元の大学に、東京生まれの彼が進学して来たのは珍しいが稀にはあることだろう。4年間を友達として楽しく過ごしたが、恋人にまではなれなかった。彼女はそれを心残りに思っているようだ。「コスモスが咲くキャンパスが懐かしいでしょう?」と歌っているから、卒業後半年経った秋なのだろうか。離れてから一層好きな気持ちが増しているのかもしれない。
彼女の母親が言った「東京は遠いよ」という言葉が、何気なく効いている。地方在住者にとって、子どもが地元に残ってくれることは何より望まれることなのだ。だから、東京の有名私大より地元の国立大の方が高評価だったりする。中島みゆきの『ファイト!』のように「出て行くんなら身内も住めんようにしてやる」とまで言われることは稀だろうが、都会に出て行くことの後ろめたさみたいなものは、濃淡こそあれ今も確かに存在する。そういう無言の圧力は『渡良瀬橋』の彼女が足利を出られない理由の一部になっているのかもしれない。
歌の中では「一度遊びに来てよ 私に逢いに来てよ」と彼女は積極的だ。彼に「好きな人ができていたらどうしよう」などと心配もしている。彼女としては、彼もまだ彼女のことが好きでいてくれると信じたいのだ。でも、一抹の不安も拭えない。そんな揺れ動く気持ちが伝わってくる歌だ。
彼の方も同じように思っていて本当に遊びに来るのか、それとも彼女はただの友達としか思っておらず、今は都会の生活の方が大事なのか、それは聴いた人間がどちらでも想像すればいいことだ。
『この街』(1991)も、地方在住者の日常を歌っていて秀逸だ。都会に出て行く彼氏や友達を見送り続けるのは寂しいが、「でもこの街が大好きよ 生まれた街だから」ときっぱり言い切る潔さ、単純さがいい。森高の歌の主人公は、あんまり1つのことにくよくよ悩まないのだ。
『アワ・フェバリットソング』の中で峯田和伸が絶賛していたのは「田んぼも」という言葉の選択センスで、他のソングライターなら絶対選ばない言葉だと私も思う。更に言えば、その後に続く「魚も安くて新鮮」というフレーズもなかなかだ。市役所の地域振興課のキャッチフレーズのようだが、これが森高の真骨頂。日常会話の言葉で、日常の生活を描いているのだ。
地方在住者の日常を描いた歌として忘れてならないのは『長男と田舎もん』(1997)だ。地方都市で付き合っているカップルの歌だ。男は長男であるがゆえに家業を継がされた。女は今18歳で、来年高校を卒業し、地元で就職するつもりだ。都会に出たい気持ちもあるが、お互い長男と田舎もんで、無理に決まっている。そういう諦めの境地で、ダラダラと毎日を送っている。
ただ、これが森高のすごいところなのだが、そういう諦めの境地でのダラダラとした生活が決してネガティブ、無気力には聴こえないのだ。「この町は田舎で最低、夢も無い」などと毒づきながら、現実を受け入れて楽しんでいる気配を感じるので、聴いていても嫌な気分にならないのだ。彼らを今風の言葉で言えば、「マイルドヤンキー」だろう。そんな言葉が無かった時代に、リアルに生き生きと描き切っていたのは素晴らしい。
「今日はどこのホテルに行こう?」と堂々と歌っているのは、彼女が18歳の設定なので法令違反でこそないが、あまりに生々しい歌詞だ。でも、このカップルにとっては当たり前の日常なのだろう。これが森高流のリアルなのだ。