

日本映画界にまた一人有能な監督が誕生した、平松恵美子監督のデビューを祝う
「映画館がはねて、青空を仰ぎながら家路につく観客の胸が幸福な気分で包まれ、さっき観た一場面を思い返して、思わず一人笑いしてしまうような無作品ができることを念じつつ『男はつらいよ』を作っている」(山田洋次著『映画館(こや)がはねて』より)
山田洋次監督の下で、20年間助監督や共同脚本を担ってきた平松恵美子さん。昨日の夜は「MOVIX倉敷」で、その平松恵美子さんの初監督作品の「ひまわりと子犬の7日間」の特別試写会が開催され、私も魅せてもらった。この日は、平松監督の舞台挨拶もあった。
平松監督は、倉敷出身で岡山大学で学ばれている。その平松監督には助監督時代に、私が関わった山田洋次監督作品の上映会に、ゲストとして舞台挨拶をしていただいたこともある、まさにご縁をいただいている方だ。

そんな方の初監督作品を地元で公開前に「特別試写」で観てもらえるのは、監督冥利に尽きることだろう。それだけに、正直「MOVIX倉敷」は不案内だが、やはりここは参加するしかないと思って頑張って出かけた。
映画を見終えて、文字通り「幸福な気分に包まれた」。とてもハートウォーミングな映画で、感動作で全編涙を誘われた。平松監督は舞台挨拶の中で、「ファミリーピクチャー」と言う言葉を使われたが、まさにご家族連れで見るのにも相応しい映画でもある。
そして同時に、日本の映画界にまた一人の有能な監督が誕生したことを確認した。そんな地元岡山県出身の平松恵美子監督をみんなで応援したいものだ。その意味でも、3月16日(土)から公開される、監督デビュー作の映画「ひまわりと子犬の7日間」を一人でも多くの方に観て欲しいと願う。

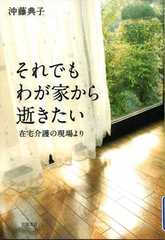

「いい男の条件はイケメン、イクメン、カジメン、カイゴメン」と学んだ
素晴らしい本と出会った。私は病院や診療所そして介護事業所の監査をさせていただいている関係で、介護の現場や介護保険のことなどについて接する機会は少なくない。
そうした中で、その本は、私が様々に見聞きしてきた「介護」について、厚労省の介護保険を巡る考え方・動きや護報酬の規定の仕方、そしてそれを受けている介護を必要とする方々の実態や思いなど、実によく整理されていて、グイグイと読み進んだ。
と同時に、そうした現場の実態や介護保険利用者の思いを知り、私自身深く考えることができ、かつ考えを整理することができた。もう一度書く、とても素晴らしい本と出会った。その本は、沖籐典子著『それでもわが家から逝きたい 在宅看護の現場より』(岩波書店刊)だ。

「暮らしの崩れは、“気力”“交流”から始まり、それが続くと家事遂行能力の低下を招き、次に日常生活動作能力の自由度が落ちる経緯がよくわかる。そして、身体機能そのものが落ちていく」(著者が本文の中で、「日本ホームヘルパー協会東京支部」の田中典子さんの文章を引用して紹介)。
「気力がなくなる、人と交流しなくなる、それが家事能力の低下を招き、やがては身体機能も悪くなる」、その通りだと実感する。私もこの頃、少しだけ気力の低下や人と交流することをタイギーと思うことがないではない。悩ましい。
この本の中には、素敵なフレーズが満載だ。少しだけメモしているものを紹介する。「わが家で死にたいなんて、男のロマン」「男はロマンで大往生、女はフマンで立ち往生」。「いいケアマネージャー、いい訪問看護師、いい主治医を持つこと。この三つが揃えば、家族も救われる」等々だ。

ところで、著者は著書の中で、「企業の社会的責任として、従業員に高齢者教育を施す」ことを提唱している。介護放棄をする男性が多いとのことで、大賛成だ。私はそれに「社会的リテラシー」も然りであり、加えるべきと考える。全ての企業は退職前に有給休暇を与えて、従業員に「介護施設での介護について学ぶ」機会と、公民館で「肩書きなしで人と交わる」ことを学ばせる必要があると考える。もちろんそれは、公務・公共の場合にはなおさらだ。
さて、「今の時代、いい男の条件は、『イケメン、イクメン、カジメン、カイゴメン』といわれている」と、著者は指摘している。私の場合には、「イケメン」には遠く、「イクメン」は通い昔であり、せめて「カジメン、カイゴメン」で「いい男」になりたいと思う。「カジメン」はできているので、問題は「カイゴメン」だ。「いい男」にならなくて良いので、パートナーに介護が必要な時が訪れないことを願うのだが、それは無理な話だろうか。さりとて、パートナーに「わがままな私の介護」の苦労はさせたくないと考えるのだが。悩ましい。
ともあれ、超高齢化社会の訪れの中で、私の健康寿命は間近になっており、平均寿命も遠い先ではない。高齢者としてどのように生きるのか、しっかりと学び考えたいと思っている。その意味でも、とても素敵な本に出会えたことを感謝している。
















