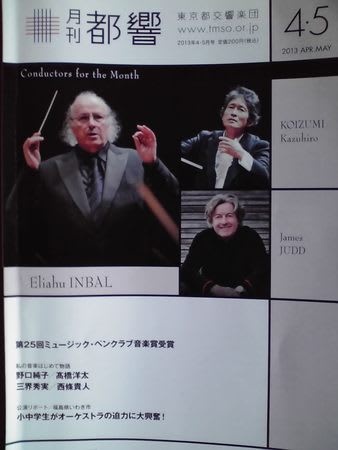28日(日)。昨日の朝日朝刊に、作曲家・佐村河内守「交響曲第1番”HIROSHIMA”」全国ツアーの全面広告が載りました コンサート・プロモーターのサモンプロモーションとCD発売元の日本コロンビアのタイアップ広告です
コンサート・プロモーターのサモンプロモーションとCD発売元の日本コロンビアのタイアップ広告です 一人の作曲家のコンサートで全面広告を打つ例は極めて稀だと思います
一人の作曲家のコンサートで全面広告を打つ例は極めて稀だと思います この広告ではこれまで発表されていた日程に加え、8月17日(土)午後2時からミューザ川崎シンフォニーホールでの公演が追加されています
この広告ではこれまで発表されていた日程に加え、8月17日(土)午後2時からミューザ川崎シンフォニーホールでの公演が追加されています チケットは昨日27日から発売とのこと。私は7月21日(日)の神奈川フィルのコンサートを押さえているので、ミューザにも行くかどうか微妙です
チケットは昨日27日から発売とのこと。私は7月21日(日)の神奈川フィルのコンサートを押さえているので、ミューザにも行くかどうか微妙です

昨日、東京文化会館小ホールで都響メンバーによる室内楽トークコンサートを聴きました プログラムは①フンメル「木管八重奏のためのパルティータ 変ホ長調」、②モーツアルト「セレナーデ第11番変ホ長調K.375」、③ドヴォルジャーク「管楽セレナーデ ニ短調」です
プログラムは①フンメル「木管八重奏のためのパルティータ 変ホ長調」、②モーツアルト「セレナーデ第11番変ホ長調K.375」、③ドヴォルジャーク「管楽セレナーデ ニ短調」です

自席はQ列15番、左寄りの一番後ろの席です。会場は8割位の入りでしょうか 最初に首席オーボエの広田智之がマイクを持って登場し、あいさつをしました
最初に首席オーボエの広田智之がマイクを持って登場し、あいさつをしました
「当初の予想では半分も埋まっていないというウワサがありましたが、連休の初日にも関わらず大勢の皆さんにお出でいただき、ありがとうございます 今回の演奏会は都響の首席のみによる演奏で、木管はオーボエ、クラリネット、ファゴットとも2人ずつ首席が出演します。実はこういう企画をすると怒られてしまうのです
今回の演奏会は都響の首席のみによる演奏で、木管はオーボエ、クラリネット、ファゴットとも2人ずつ首席が出演します。実はこういう企画をすると怒られてしまうのです と言うのは、同じ首席でも第1(ソロ・コンマス)と第2とでは役割が全く異なるからです。第1は主旋律を吹くのに対して第2は副旋律を吹いたり、オーボエだったらイングリッシュホルンに持ち替えたりするのです
と言うのは、同じ首席でも第1(ソロ・コンマス)と第2とでは役割が全く異なるからです。第1は主旋律を吹くのに対して第2は副旋律を吹いたり、オーボエだったらイングリッシュホルンに持ち替えたりするのです 今日は前半と後半で役割を入れ替えて演奏するので、いつもと違ってどれだけやれるかといったところです
今日は前半と後半で役割を入れ替えて演奏するので、いつもと違ってどれだけやれるかといったところです 」
」
「1曲目のフンメルについて説明しておきます。フンメル(1778~1837年)は現在のスロヴァキアに生まれ、幼少時にウィーンへ移り住みました。8歳の時にモーツアルトに才能を認められ、2年間も家に住みついて無償のレッスンを受けたといいますから、相当の天才だったのでしょう その後は、ピアノ演奏においてベートーヴェンと人気を二分したと言いますから、よほどピアノが上手だったようです
その後は、ピアノ演奏においてベートーヴェンと人気を二分したと言いますから、よほどピアノが上手だったようです これから演奏する木管八重奏のためのパルティータはオーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン各2本で演奏されます。パルティータというのは大まかに言えば組曲です。変ホ長調ということで、明るい曲です
これから演奏する木管八重奏のためのパルティータはオーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン各2本で演奏されます。パルティータというのは大まかに言えば組曲です。変ホ長調ということで、明るい曲です 」
」
一旦、広田智之が袖に引っ込んで、あらためて8人の奏者が登場します。左からオーボエの鷹栖美恵子、広田智之、ファゴットの岡本正之、長哲也、ホルンの野見山和子、西條貴人、クラリネットの三界秀実、サトーミチヨ(何でカタカナよ?)という配置です
広田の合図で第1楽章「アレグロ・コン・スピリト」が始まります。なるほど親しみやすい明るいメロディーです。それは第2楽章のアンダンテでも、第3楽章のヴィヴァーチェでも変わりません。師匠のモーツアルトのパルティータと比べると、何の悩みもないひたすら明るい曲です 演奏は、さすが都響の最前線で活躍する首席だけによる見事なアンサンブルです
演奏は、さすが都響の最前線で活躍する首席だけによる見事なアンサンブルです とくに左右に分かれて向かい合ったオーボエの鷹栖美恵子とクラリネットのサトーミチヨの掛け合いが聴きものでした
とくに左右に分かれて向かい合ったオーボエの鷹栖美恵子とクラリネットのサトーミチヨの掛け合いが聴きものでした
2曲目のモーツアルト「セレナード第11番K.375」の第1項(1781年作曲)はクラリネット、ホルン、ファゴット各2人、計6人による編成でしたが、翌1782年7月に自身により改訂された版によると2本のオーボエが加わり8人編成になっています
ホルンは野見山和子に代わり和田博史が登場します。この曲は馴染み深いこともありましたが、念のためウィーン・フィルハーモニー木管グループによる演奏のCD(1954年録音)で予習しておいたので、メロディーはすべて頭に入っています

この曲もテンポといい、それぞれの楽器の音色といい、全体のアンサンブルといい、素晴らしい演奏でした
20分の休憩を挟んで後半のドヴォルジャーク「管楽セレナーデ」に入ります。再び広田智之がマイクを持って登場、セレナーデについて説明します
「セレナーデというのは、夜、大切な人のために語りたいことを語る時の音楽です 次に演奏するドヴォルジャークの”管楽セレナーデ”は、モーツアルトの頃のセレナーデとは意味合いが全く違っています。モーツアルトの13楽器のためのセレナーデ”グラン・パルティータ”を意識して作曲したところも見受けられます
次に演奏するドヴォルジャークの”管楽セレナーデ”は、モーツアルトの頃のセレナーデとは意味合いが全く違っています。モーツアルトの13楽器のためのセレナーデ”グラン・パルティータ”を意識して作曲したところも見受けられます 」
」
「ここで、演奏者を迎えてインタビューしようと思います。皆さん、登場してください 」と言って出場者全員を迎えます。全員が揃ったところで、
」と言って出場者全員を迎えます。全員が揃ったところで、
「鷹栖さん(オーボエ)は東京シティフィルの首席から昨年8月に都響の首席に移ってきたんですよね」、
「長君(ファゴット)は、東京藝大卒業後、すぐに都響のコンマスに迎えられたんですよね」、
「サトーさんは、改名されたんですよね。ごめんなさい、音楽の話じゃなくて 」
」
と、相手に話してもらうよりもインタビュアーの話の方が長いようでした。
サトーさんは「サトーミチヨとカタカナに改名した方が運勢が良くなると言われたんですよ。いえ、怪しいアレじゃなくて・・・・サトウじゃだめでサトーと伸ばさないとだめだと言われたんです 」
」
すかさず広田智之が「皆さん、プログラムのメンバー表をご覧いただくとインパクトがありますよ。最初はナニ人かと思いますが・・・・・」と突っ込みます
舞台上には前半のメンバーに、チェロの田中雅弘とコントラバスの山本修が加わります。そして、それぞれの楽器で第1と第2が入れ替わります
この曲は、第1楽章冒頭の行進曲風のメロディーが特徴的ですが、私は昔NHKで放映された連続テレビ・ドラマ、向田邦子原作の「阿修羅のごとく」のテーマ音楽が、このドヴォルジャークの「管楽セレナーデ」の冒頭だと長い間思い込んでいました 今でこそ、そのテーマはオスマン・トルコの軍楽隊音楽「ジェッディン・テデン」(祖父も父も)であることが判っていますが、メロディーがよく似ているのです
今でこそ、そのテーマはオスマン・トルコの軍楽隊音楽「ジェッディン・テデン」(祖父も父も)であることが判っていますが、メロディーがよく似ているのです
何と言ってもこの曲の大きな特徴はモーツアルトのセレナーデ第10番”グランパルティータ”(13楽器のためのセレナーデ)を意識して作曲したと思われることです 第3楽章「アンダンテ・コン・モート」を聴くと、まさにグランパルティータのアダージョ楽章の世界です。ドヴォルジャークのこの曲ではチェロとコントラバスが加わっていますが、広田智之の解説のように「これらの楽器があるとないとでは、まったく違う」大きな存在です。管楽器同士のやり取りを底辺で支える頼もしい楽器です
第3楽章「アンダンテ・コン・モート」を聴くと、まさにグランパルティータのアダージョ楽章の世界です。ドヴォルジャークのこの曲ではチェロとコントラバスが加わっていますが、広田智之の解説のように「これらの楽器があるとないとでは、まったく違う」大きな存在です。管楽器同士のやり取りを底辺で支える頼もしい楽器です
アンコールにはドヴォルジャークのフィナーレ部分を演奏し、会場一杯の拍手を受けていました 都響は弦楽器が定評があると言われていますが、管楽器もどうして素晴らしい演奏家が揃っていると思いました
都響は弦楽器が定評があると言われていますが、管楽器もどうして素晴らしい演奏家が揃っていると思いました