19日(日).わが家に来てから今日で1145日目を迎え,中国の習近平国家主席の特使として訪朝している中国共産党の宋中央対外連絡部長が18日,朝鮮労働党で国際部門を統括する李副委員長と会談した というニュースを見て 二人の主張を代弁するモコタロです

宋「核ミサイル放棄してくんね?」 李「それじゃ iPhoneX 100個と交換でどう?」












N響から会員特典CDと来年のカレンダーが届きました カレンダーは楽器シリーズ路線みたいです
カレンダーは楽器シリーズ路線みたいです

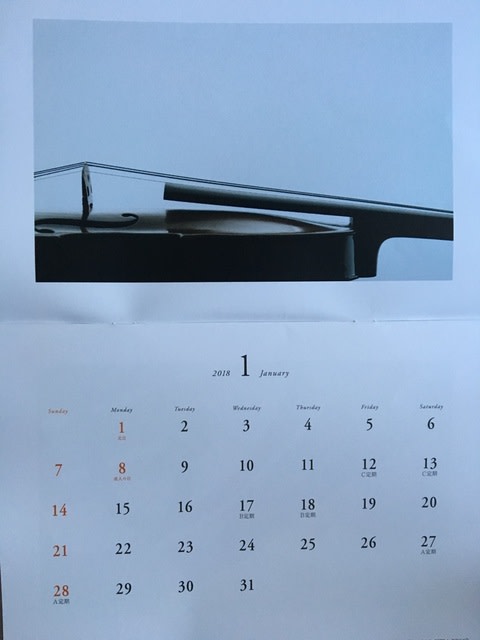












昨日,池袋の東京芸術劇場コンサートホールで「第8回音楽大学オーケストラ・フェスティバル2017」参加公演のうち東京藝大と桐朋学園大の2校の演奏を聴きました 東京藝大はストラヴィンスキーのバレエ音楽「ペトルーシュカ」で,指揮はラースロー・ティハ二,桐朋学園大はプロコフィエフのバレエ音楽「ロミオとジュリエット」で,指揮は中田延亮です
東京藝大はストラヴィンスキーのバレエ音楽「ペトルーシュカ」で,指揮はラースロー・ティハ二,桐朋学園大はプロコフィエフのバレエ音楽「ロミオとジュリエット」で,指揮は中田延亮です

このフェスティバルは毎年 日程が空いている限り聴くようにしていますが,今回は4公演のうち第1日目の昨日の公演しか聴けません 東京藝大と桐朋学園大の組み合わせとあってか,会場はほぼ満席に近い状態です
東京藝大と桐朋学園大の組み合わせとあってか,会場はほぼ満席に近い状態です もちろん出場する学生の家族・友人・その他関係者などが多く来場していることは想像できますが,それにしてもよく入りました
もちろん出場する学生の家族・友人・その他関係者などが多く来場していることは想像できますが,それにしてもよく入りました 自席は1階P列11番,左ブロック右から2つ目です
自席は1階P列11番,左ブロック右から2つ目です
東京藝大の演奏に先立って,共演校からのエールを込めたファンファーレが演奏されます 桐朋学園大の中村匡寿君作曲によるファンファーレが同大オケの金管と小太鼓・シンバルにより華やかに演奏されました
桐朋学園大の中村匡寿君作曲によるファンファーレが同大オケの金管と小太鼓・シンバルにより華やかに演奏されました
藝大の学生たちが入場し配置に着きます.東京藝大シンフォニーオーケストラの編成はヴァイオリンを左側にまとめ,右側にチェロ,ヴィオラ,コントラバスを置く並びです 指揮者の前にはグランド・ピアノが置かれています.名簿によるとコンミスは徳田真侑さん.オケは総勢84名で,相変わらず女子学生が多い(特に弦楽器)ことに変わりはありませんが,前回見た時よりも男子学生が増えているように思います
指揮者の前にはグランド・ピアノが置かれています.名簿によるとコンミスは徳田真侑さん.オケは総勢84名で,相変わらず女子学生が多い(特に弦楽器)ことに変わりはありませんが,前回見た時よりも男子学生が増えているように思います
よく知られているように,ストラヴィンスキーはディアギレフの主宰するロシア・バレエ団(バレエ・リュス)のために3つのバレエ音楽を作曲しました 作曲順に「火の鳥」(初演1910年),「ペトルーシュカ」(同1911年),「春の祭典」(同1913年)です
作曲順に「火の鳥」(初演1910年),「ペトルーシュカ」(同1911年),「春の祭典」(同1913年)です 「ペトルーシュカ」はサンクトペテルブルクの謝肉祭の市場の人形劇を題材にした作品です.この曲の特徴は,ピアノが重要な役割を果たすことで,さながら「ピアノ協奏曲」のような形態をとっていることです
「ペトルーシュカ」はサンクトペテルブルクの謝肉祭の市場の人形劇を題材にした作品です.この曲の特徴は,ピアノが重要な役割を果たすことで,さながら「ピアノ協奏曲」のような形態をとっていることです
この曲は第1場「謝肉祭の市場」,第2場「ペトルーシュカの部屋」,第3場「ムーア人の部屋」,第4場「謝肉祭の市場(夕方)それからペトルーシュカの死」の4場から成ります
ハンガリーのブタペスト生まれ,1979年からリスト音楽院の教授を務めるラースロー・ティハ二が指揮台に上がり,第1場「謝肉祭の市場」の演奏に入ります 冒頭から管弦楽による色彩感溢れる音楽が展開します
冒頭から管弦楽による色彩感溢れる音楽が展開します フルート,ファゴット,トランペット,そしてティンパニの好演が目立ちます
フルート,ファゴット,トランペット,そしてティンパニの好演が目立ちます ピアノの演奏もメリハリが効いていて素晴らしい
ピアノの演奏もメリハリが効いていて素晴らしい 弦楽器は柔軟性に富みストラヴィンスキーの変拍子をモノともしません.さすがは藝大のオケです
弦楽器は柔軟性に富みストラヴィンスキーの変拍子をモノともしません.さすがは藝大のオケです

プログラム後半は桐朋学園オーケストラによるプロコフィエフ:バレエ音楽「ロミオとジュリエット」(抜粋)です 演奏に先立って,東京藝大の石川健人君作曲によるファンファーレが華々しく演奏されました
演奏に先立って,東京藝大の石川健人君作曲によるファンファーレが華々しく演奏されました
桐朋学園大の学生たちが配置に着きます.オケは藝大と同じ並びです コンマスは女子学生ですが名前が分かりません.東京藝大よりも多い総勢95名のメンバーは,東京藝大と比べ圧倒的に女子学生が多く,特に弦楽器などは男子学生は数えるほどしかいません.これが現在の私立音楽大学の縮図でしょうか
コンマスは女子学生ですが名前が分かりません.東京藝大よりも多い総勢95名のメンバーは,東京藝大と比べ圧倒的に女子学生が多く,特に弦楽器などは男子学生は数えるほどしかいません.これが現在の私立音楽大学の縮図でしょうか
この日演奏するのはプロコフィエフ:バレエ音楽「ロミオとジュリエット」の第1組曲と第2組曲から8曲を抜粋したものです 演奏順に①第2組曲第1曲「モンテギュー家とキャビュレット家」,②第2組曲第2曲「少女ジュリエット」,③第1組曲第3曲「マドリガル」,④第1組曲第4曲「メヌエット」,⑤第1組曲第6曲「ロミオとジュリエット」,⑥第1組曲第7曲「タイボルトの死」,⑦第1組曲第5曲「別れの前のロミオとジュリエット」,⑧第2組曲第7曲「ジュリエットの墓の前のロミオ」です
演奏順に①第2組曲第1曲「モンテギュー家とキャビュレット家」,②第2組曲第2曲「少女ジュリエット」,③第1組曲第3曲「マドリガル」,④第1組曲第4曲「メヌエット」,⑤第1組曲第6曲「ロミオとジュリエット」,⑥第1組曲第7曲「タイボルトの死」,⑦第1組曲第5曲「別れの前のロミオとジュリエット」,⑧第2組曲第7曲「ジュリエットの墓の前のロミオ」です
京都生まれ,筑波大学医学専門学群在学中に桐朋学園ソリストディプロマコースに入学しコントラバスを専攻する一方指揮を学んだという変わった経歴の持ち主,中田延亮(のぶあき)が指揮台に上がります
中田氏のタクトで1曲目の「モンタギュー家とキャビレット家」が開始されます この曲は騎士と貴婦人を表す荘重な音楽で,この曲の一番有名な音楽です
この曲は騎士と貴婦人を表す荘重な音楽で,この曲の一番有名な音楽です 弦楽器がメイン・メロディーを奏で,管楽器がそれを支えます.この曲を聴いて,指揮者・中田氏の並々ならぬ気迫を感じました
弦楽器がメイン・メロディーを奏で,管楽器がそれを支えます.この曲を聴いて,指揮者・中田氏の並々ならぬ気迫を感じました 2曲目の「少女ジュリエット」ではフルートとサクソフォンが素晴らしいパフォーマンスを見せ,チェロのソロが聴かせてくれました
2曲目の「少女ジュリエット」ではフルートとサクソフォンが素晴らしいパフォーマンスを見せ,チェロのソロが聴かせてくれました 5曲目の「ロミオとジュリエット」ではコンミスのソロが冴え,6曲目の「タイボルトの死」ではオーケストラ挙げての迫力ある演奏に圧倒されました
5曲目の「ロミオとジュリエット」ではコンミスのソロが冴え,6曲目の「タイボルトの死」ではオーケストラ挙げての迫力ある演奏に圧倒されました この後,チューニングを行い,7曲目の「別れのロミオとジュリエット」に入りました
この後,チューニングを行い,7曲目の「別れのロミオとジュリエット」に入りました ここではヴィオラのソロが素晴らしい演奏を展開しました
ここではヴィオラのソロが素晴らしい演奏を展開しました そして最後の「ジュリエットの墓の前のロミオ」の演奏が静かに閉じられ,しばしの”しじま”の後,会場いっぱいの拍手とブラボーに包まれました
そして最後の「ジュリエットの墓の前のロミオ」の演奏が静かに閉じられ,しばしの”しじま”の後,会場いっぱいの拍手とブラボーに包まれました
 中田氏はセクションごとに演奏者を立たせ聴衆にアピールしていましたが,若き日のコバケン(小林研一郎氏)もこうだったのではないか,と思わるパフォーマンスでした
中田氏はセクションごとに演奏者を立たせ聴衆にアピールしていましたが,若き日のコバケン(小林研一郎氏)もこうだったのではないか,と思わるパフォーマンスでした (コバケンは藝大出身ですが)
(コバケンは藝大出身ですが)
全体を通じて,管楽器ではホルンがとても素晴らしい演奏を展開したのをはじめ,個々の楽器が並々ならぬ好演を見せ,弦楽器は厚みのある演奏を展開していました 彼らの力を最大限引き出していたのは指揮者・中田延亮氏です.今後の活躍が期待されます
彼らの力を最大限引き出していたのは指揮者・中田延亮氏です.今後の活躍が期待されます
この日のオケを聴いて思ったのは,「これが学生オーケストラの演奏だろうか? ほとんどプロの水準に達しているのではないか 」ということです
」ということです とくに桐朋学園オーケストラについては つくづくそう思いました
とくに桐朋学園オーケストラについては つくづくそう思いました
学生オーケストラの演奏を聴いていつも思うのは,1年後,あるいは2年,3年後に彼らはどこでどうしているだろうか,ということです 新聞報道では,来春は空前の就職状況だと喧伝されていますが,果たして音楽大学出身者の就職はどうなのだろうか? やりたい仕事に就ける若者が果たして何割くらいいるのだろうか? 子供の才能を信じて幼い頃から音楽教室に通わせ,音楽大学に合格したのもつかの間,授業と並行して個人レッスンも受けさせ,卒業したら大学院へ,あるいは海外に留学させ・・・と,一人の子供にいくら投資したら親として報われるのだろうか? そうした親の苦労を子供たちどう考えているのだろうか?・・・他人事ながらそんなことを考えてしまいます
新聞報道では,来春は空前の就職状況だと喧伝されていますが,果たして音楽大学出身者の就職はどうなのだろうか? やりたい仕事に就ける若者が果たして何割くらいいるのだろうか? 子供の才能を信じて幼い頃から音楽教室に通わせ,音楽大学に合格したのもつかの間,授業と並行して個人レッスンも受けさせ,卒業したら大学院へ,あるいは海外に留学させ・・・と,一人の子供にいくら投資したら親として報われるのだろうか? そうした親の苦労を子供たちどう考えているのだろうか?・・・他人事ながらそんなことを考えてしまいます
私は「教育は子供たちに対する最大の投資だ」と考えています もちろん,投資の成果を出すのは子供たち自身だということは言うまでもありません
もちろん,投資の成果を出すのは子供たち自身だということは言うまでもありません

















