26日(金)その2.よい子は「その1」も見てね。モコタロはそちらに出演しています





昨夕、サントリーホールでN響第1911回定期演奏会(Bプロ)を聴きました プログラムは①ショスタコーヴィチ「ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調作品77」、②ヴァインベルク「交響曲第12番作品114”ショスタコーヴィチの思い出に”」です
プログラムは①ショスタコーヴィチ「ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調作品77」、②ヴァインベルク「交響曲第12番作品114”ショスタコーヴィチの思い出に”」です 演奏は①のヴァイオリン独奏=ワディム・グルズマン、指揮=下野竜也です
演奏は①のヴァイオリン独奏=ワディム・グルズマン、指揮=下野竜也です
弦はいつもの並びで、左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという編成。コンマスはマロこと篠崎史紀氏です
1曲目はショスタコーヴィチ「ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調作品77」です この曲は、ドミートリ・ショスタコーヴィチ(1906ー1975)が1947年から翌48年にかけて作曲しましたが、完成後に作曲者に対する批判が出たため、初演は7年間お預けとなり、1955年10月29日にレニングラードでダヴィッド・オイストラフのヴァイオリン、エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルにより行われました
この曲は、ドミートリ・ショスタコーヴィチ(1906ー1975)が1947年から翌48年にかけて作曲しましたが、完成後に作曲者に対する批判が出たため、初演は7年間お預けとなり、1955年10月29日にレニングラードでダヴィッド・オイストラフのヴァイオリン、エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルにより行われました 第1楽章「ノクターン:モデラート」、第2楽章「スケルツォ:アレグロ」、第3楽章「パッサカリア:アンダンテ」、第4楽章「ブルレスカ:アレグロ・コン・ブリオ」の4楽章から成ります
第1楽章「ノクターン:モデラート」、第2楽章「スケルツォ:アレグロ」、第3楽章「パッサカリア:アンダンテ」、第4楽章「ブルレスカ:アレグロ・コン・ブリオ」の4楽章から成ります
1973年ウクライナ生まれ、イスラエル国籍のワディム・グルズマンが下野竜也氏とともに登場、さっそく演奏に入ります 楽譜を見ながらの演奏ですが、かなりの技巧派で、緩徐楽章はじっくりと歌わせ、アレグロ楽章は超絶技巧を凝らして下野✕N響との丁々発止のやり取りをしながら猛スピードで駆け抜けます
楽譜を見ながらの演奏ですが、かなりの技巧派で、緩徐楽章はじっくりと歌わせ、アレグロ楽章は超絶技巧を凝らして下野✕N響との丁々発止のやり取りをしながら猛スピードで駆け抜けます 十数年前 みなとみらいホールで 生まれて初めてこの曲を聴いたヒラリー・ハーン ✕ ヤンソンス ✕ ベルリン・フィルの鮮やかな演奏を思い出しました
十数年前 みなとみらいホールで 生まれて初めてこの曲を聴いたヒラリー・ハーン ✕ ヤンソンス ✕ ベルリン・フィルの鮮やかな演奏を思い出しました
終演後、「4月から休憩時間は20分となりました」というアナウンスが流れました N響の場合、プログラム冊子「Philharmony」には、ただ「休憩」と書かれているだけでしたが、今号から「休憩(20分)」と表示されるようになりました
N響の場合、プログラム冊子「Philharmony」には、ただ「休憩」と書かれているだけでしたが、今号から「休憩(20分)」と表示されるようになりました 今までは15分しか休憩がなかったので、トイレの列が解消されないうちに後半開始チャイムが鳴り始め、「トイレには行きたいけれど 時間はなし あわただしきことこの上なし」でした
今までは15分しか休憩がなかったので、トイレの列が解消されないうちに後半開始チャイムが鳴り始め、「トイレには行きたいけれど 時間はなし あわただしきことこの上なし」でした 一歩前進です
一歩前進です

プログラム後半はヴァインベルク「交響曲第12番作品114”ショスタコーヴィチの思い出に”」です この曲はユダヤ系ポーランド人として生まれたミェチスワフ・ヴァインベルク(1919-1996)が1975年から翌76年にかけて作曲、1979年10月13日にモスクワで、マキシム・ショスタコーヴィチ指揮モスクワ放送交響楽団により初演されました
この曲はユダヤ系ポーランド人として生まれたミェチスワフ・ヴァインベルク(1919-1996)が1975年から翌76年にかけて作曲、1979年10月13日にモスクワで、マキシム・ショスタコーヴィチ指揮モスクワ放送交響楽団により初演されました 第1楽章「アレグロ・モデラート」、第2楽章「アレグレット」、第3楽章「アダージョ」、第4楽章「アレグロ」の4楽章から成ります
第1楽章「アレグロ・モデラート」、第2楽章「アレグレット」、第3楽章「アダージョ」、第4楽章「アレグロ」の4楽章から成ります
この曲のサブタイトルは「ショスタコーヴィチの思い出に」となっていますが、ショスタコーヴィチの曲想に似ているのは、第2楽章及び第3楽章の一部と第4楽章のフィナーレくらいのものです 千葉潤さんによるプログラム・ノートには「マーラーやショスタコーヴィチを思わせる悲劇性やアイロニー・・・・」といった表現が使われていましたが、「目先がクルクルと変わり 先がまったく読めない」という意味ではマーラーの交響曲に似ていますが、曲想はまったく似ていません
千葉潤さんによるプログラム・ノートには「マーラーやショスタコーヴィチを思わせる悲劇性やアイロニー・・・・」といった表現が使われていましたが、「目先がクルクルと変わり 先がまったく読めない」という意味ではマーラーの交響曲に似ていますが、曲想はまったく似ていません ストーリーに関係なくいきなりダンスが踊られるインド映画(ボリウッド)のようです
ストーリーに関係なくいきなりダンスが踊られるインド映画(ボリウッド)のようです 「この人はいろいろと辛い目に遭って不満が鬱積していたのだろう
「この人はいろいろと辛い目に遭って不満が鬱積していたのだろう その辛い気持ちを交響曲の中にランダムにぶちまけたのだろう」と思ったりしました
その辛い気持ちを交響曲の中にランダムにぶちまけたのだろう」と思ったりしました
1時間にも及ぼうとする長大で難解な交響曲を聴きながら、その昔、若者たちの間で空前のヒットを記録したザ・ブロードサイド・フォーの名曲「若者たち」を想い起こしていました
 君の行く道は 果てしなく遠い だのに なぜ 歯を食いしばり 君は行くのか そんなにしてまで
君の行く道は 果てしなく遠い だのに なぜ 歯を食いしばり 君は行くのか そんなにしてまで 
 君の聴く曲は 果てしなく長い だのに なぜ 歯を食いしばり 君は聴くのか そんなにしてまで
君の聴く曲は 果てしなく長い だのに なぜ 歯を食いしばり 君は聴くのか そんなにしてまで 
冗談はさておき、終演後、何だかよく分からない曲だったけど熱演だったと カーテンコールが繰り返されました 女性ヴァイオリン奏者から花束を受け取った下野氏は、それを譜面台上のスコアブックの上に載せ、ヴァインベルクに敬意を表して 楽譜に拍手を送りました
女性ヴァイオリン奏者から花束を受け取った下野氏は、それを譜面台上のスコアブックの上に載せ、ヴァインベルクに敬意を表して 楽譜に拍手を送りました コンマスの篠崎氏には、古典派やロマン派だけでなく、あえて現代のクラシックを取り上げる下野氏をリスペクトする姿勢が見て取れました
コンマスの篠崎氏には、古典派やロマン派だけでなく、あえて現代のクラシックを取り上げる下野氏をリスペクトする姿勢が見て取れました
ところで、N響のプログラム冊子「Philharmony」は「オーケストラのゆくえ」というテーマでオーケストラを巡る様々なトピックを取り上げてきましたが、4月号はその最終回として元ウィーン・フィルのコンマスで、N響のゲスト・コンマスを務めるライナー・キュッヒル氏がインタビューに答えています。これが実に面白いのです。これについては後日あらためてご紹介することにします















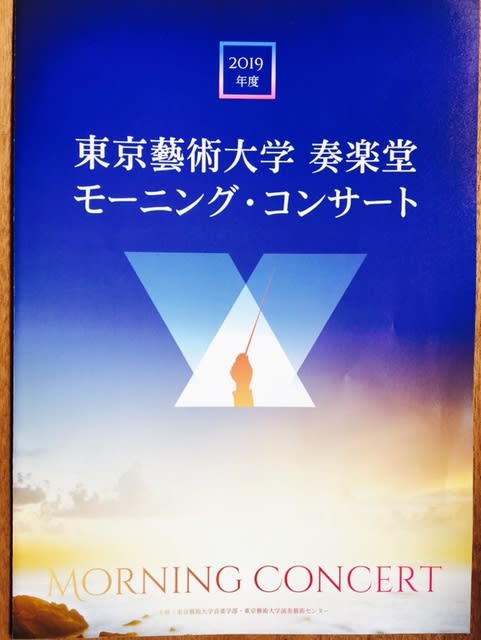
 4つの楽章は切れ目なく続けて演奏されます
4つの楽章は切れ目なく続けて演奏されます
 と言いたくなるようなスケールの大きな音楽が展開しフィナーレを迎えます
と言いたくなるようなスケールの大きな音楽が展開しフィナーレを迎えます
 一気にブラームスの世界に引き込まれます
一気にブラームスの世界に引き込まれます スケールの大きな長大な序奏に続いて独奏ピアノが入ってきますが、ピアノはオーケストラの一部と化しています。これがブラームスの狙いでしょう
スケールの大きな長大な序奏に続いて独奏ピアノが入ってきますが、ピアノはオーケストラの一部と化しています。これがブラームスの狙いでしょう 独奏ピアノとオケが混然一体となって次第にヒートアップしていき、ダイナミックな演奏を展開します
独奏ピアノとオケが混然一体となって次第にヒートアップしていき、ダイナミックな演奏を展開します



