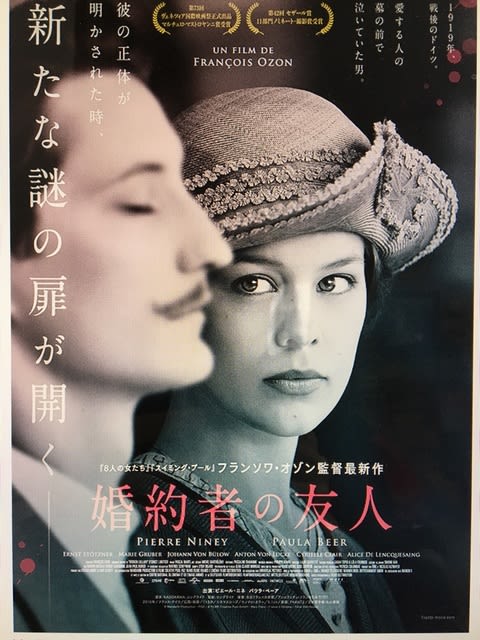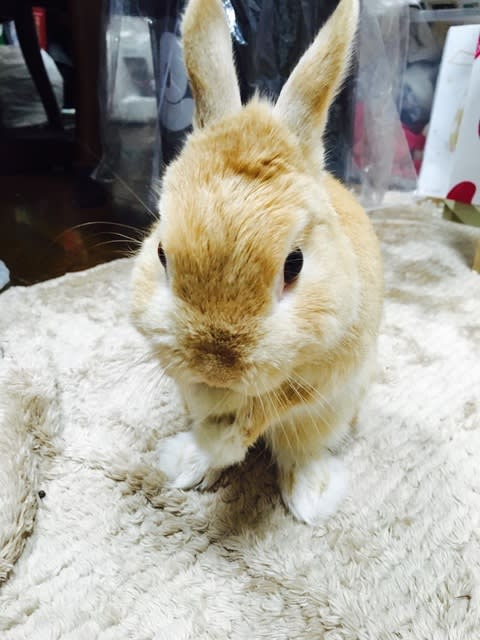20日(金)。昨夜、元の職場の同僚S氏とE氏と3人で、現役時代の行きつけの店、西新橋のK亭で飲みました 同じメンバーでの飲み会は2月9日以来です。よもやま話に花が咲きましたが、今回はE氏が身近な人を相次いで亡くし、そろそろ終活を考えなければならないな、と嘆息していたのが気になりました
同じメンバーでの飲み会は2月9日以来です。よもやま話に花が咲きましたが、今回はE氏が身近な人を相次いで亡くし、そろそろ終活を考えなければならないな、と嘆息していたのが気になりました それでも、いつものように新橋駅近くのE氏行きつけの店Sに行き2次会をやって10時ごろ引き上げました
それでも、いつものように新橋駅近くのE氏行きつけの店Sに行き2次会をやって10時ごろ引き上げました 飲むと疲れます。今朝も頭が朦朧としています
飲むと疲れます。今朝も頭が朦朧としています
という訳で、わが家に来てから今日で1296日目を迎え、テレビ朝日が19日、財務省の福田淳一事務次官を取材した女性社員がセクハラの被害を受けたとして同省に抗議文を提出したが、本人はなお否定している という記事を見て感想を述べるモコタロです

福田氏は自分が所属する財務省は あくまで罪無省だ と勘違いしているんじゃね?





昨日、夕食に「鶏ささみの野菜たっぷり照り焼き」「生野菜サラダ」「マグロの山掛け」を作りました 「鶏ささみ~」は初挑戦ですが、当ブログの読者reilaさんからコメント欄にいただいたアドヴァイスにより、ササミの筋をフォークを使って何とかきれいに取り除くことができて、初めてにしては美味しく出来ました
「鶏ささみ~」は初挑戦ですが、当ブログの読者reilaさんからコメント欄にいただいたアドヴァイスにより、ササミの筋をフォークを使って何とかきれいに取り除くことができて、初めてにしては美味しく出来ました reilaさん、ありがとうございました
reilaさん、ありがとうございました






昨日、早稲田松竹でダニエル・シャイナート&ダニエル・クワン監督による2016年アメリカ映画「スイス・アーミー・マン」(97分)を観ました
遭難して無人島に漂着した青年ハンク(ポール・ダノ)は、誰も助けに来ないことに絶望して命を断とうとした時、波打ち際に男の死体(ダニエル・ラドクリフ)が打ち上げられているのを発見する 死体からはガスが出ており、浮力があることに気が付いたハンクは、意を決して死体にまたがり死体からのガスの噴出力で無人島を脱出することを試みる
死体からはガスが出ており、浮力があることに気が付いたハンクは、意を決して死体にまたがり死体からのガスの噴出力で無人島を脱出することを試みる ところが、途中でまたしても海に投げ出されてしまい、今後は別の無人島の砂浜で目が覚める
ところが、途中でまたしても海に投げ出されてしまい、今後は別の無人島の砂浜で目が覚める 一人寂しいハンクは死体に声をかけると思いがけなく返事が返ってきて、死体は自らをメニーと名乗った。メニーは生前の記憶を無くしていたためハンクは様々なことを教えてあげる。実はハンクには片思いの女性がいて、どうしても会いたかった
一人寂しいハンクは死体に声をかけると思いがけなく返事が返ってきて、死体は自らをメニーと名乗った。メニーは生前の記憶を無くしていたためハンクは様々なことを教えてあげる。実はハンクには片思いの女性がいて、どうしても会いたかった 熊に襲われるという絶体絶命の危機に瀕しながらもメニーの力で脱出し、二人はハンクの故郷を目指す
熊に襲われるという絶体絶命の危機に瀕しながらもメニーの力で脱出し、二人はハンクの故郷を目指す

97分のストーリーのうち、ほぼ90%は登場人物がハンクと死体の2人(?)だけです。よくも飽きさせずに終盤まで引っ張ったものだと感心します タイトルの「スイス・アーミー・マン」についてですが、「アーミー・ナイフ」は軍隊向けの、缶切り、栓抜き、ハサミ、やすり、ドライバーなどが折り畳まれた多機能ナイフのことですが、この映画では死体のメニーが口から飲料水を出したり、ガスを発射してジェットスキー代わりになったりと、ハンクのために多方面で役に立つ人間(死体だけど)だからという意味で「アーミー・マン」なのです
タイトルの「スイス・アーミー・マン」についてですが、「アーミー・ナイフ」は軍隊向けの、缶切り、栓抜き、ハサミ、やすり、ドライバーなどが折り畳まれた多機能ナイフのことですが、この映画では死体のメニーが口から飲料水を出したり、ガスを発射してジェットスキー代わりになったりと、ハンクのために多方面で役に立つ人間(死体だけど)だからという意味で「アーミー・マン」なのです
それにしても、と思うのは、同じ「ハリー・ポッター・シリーズ」で主役級を務めた役者でも、片やハーマイオニーを演じたエマ・ワトソンが ディズニーの「美女と野獣」で美しきヒロインを演じたのに対して、ヒーローのハリーポッターを演じたダニエル・ラドクリフが死体役ですから、この落差は何なんだろうか、と思わざるを得ません





ジェフリー・ディーヴァー著「ゴースト・スナイパー(上・下)」(文春文庫)を読み終わりました ジェフリー・ディーヴァーの作品は文庫化されるたびに このブログでご紹介してきましたが、念のために略歴をご紹介しておきます。1950年シカゴ生まれ。ミズーリ大学でジャーナリズムを専攻し、雑誌記者、弁護士を経て40歳で小説家となる
ジェフリー・ディーヴァーの作品は文庫化されるたびに このブログでご紹介してきましたが、念のために略歴をご紹介しておきます。1950年シカゴ生まれ。ミズーリ大学でジャーナリズムを専攻し、雑誌記者、弁護士を経て40歳で小説家となる ”科学捜査の天才”リンカーン・ライム・シリーズや”人間ウソ発見器”キャサリン・ダンス・シリーズなど多くの作品が世界中で愛読されています
”科学捜査の天才”リンカーン・ライム・シリーズや”人間ウソ発見器”キャサリン・ダンス・シリーズなど多くの作品が世界中で愛読されています

バハマで反米活動家のロバート・モレノが殺害された 2キロも離れた超長距離狙撃による暗殺だった。その直後、リンカーン・ライムのもとに地方検事補ローレルが訪ねてきた。彼女によると、その暗殺は米国政府諜報機関NIOSの仕業でありテロリストとして射殺されたモレノは無実だったという
2キロも離れた超長距離狙撃による暗殺だった。その直後、リンカーン・ライムのもとに地方検事補ローレルが訪ねてきた。彼女によると、その暗殺は米国政府諜報機関NIOSの仕業でありテロリストとして射殺されたモレノは無実だったという ニューヨークからかなり離れたバハマでの事件、しかも物的証拠がほとんど残されていない中で、現地の警察の若き巡査部長ポワティエの電話連絡による協力を得て、ライムとアメリア・サックスたちは捜査を開始する
ニューヨークからかなり離れたバハマでの事件、しかも物的証拠がほとんど残されていない中で、現地の警察の若き巡査部長ポワティエの電話連絡による協力を得て、ライムとアメリア・サックスたちは捜査を開始する

殺人現場は汚染され、証人が次々と殺されていく中で、現地の警察が思うように動いてくれないことにしびれを切らしたライムは、車椅子ともどもバハマの現場に乗り込むことを決意し現地に赴く ポワティエ巡査部長の全面的な協力を取り付けたライムは身の危険を冒して真犯人に迫っていく
ポワティエ巡査部長の全面的な協力を取り付けたライムは身の危険を冒して真犯人に迫っていく そして、実は犯人の真の標的はモレノではなく、すぐそばにいた人物だったことを突き止める
そして、実は犯人の真の標的はモレノではなく、すぐそばにいた人物だったことを突き止める
この作品の一番のポイントは、2キロも先の特定の人間だけを射殺することが可能なのかどうか、ということです この問題は、現地の警察により回収された弾丸と、それがどういう軌道(弾道)を画いてモレノに命中したのかという推理によって解決されます。推理の決め手は弾丸のスピードと角度です
この問題は、現地の警察により回収された弾丸と、それがどういう軌道(弾道)を画いてモレノに命中したのかという推理によって解決されます。推理の決め手は弾丸のスピードと角度です
いつもの通り、どんでん返しの連続で読む手が止まりません。お薦めします

















 いつもこういう葛藤があります。次に大江君がヴァイオリン・ソナタを弾きますが、本当は全曲弾きたいのだと思いますが、これも第2楽章だけとなりました
いつもこういう葛藤があります。次に大江君がヴァイオリン・ソナタを弾きますが、本当は全曲弾きたいのだと思いますが、これも第2楽章だけとなりました 第1楽章もすごくいい曲なので、ほんの数小節だけ演奏して 続けて第2楽章を弾いてもらうことにします
第1楽章もすごくいい曲なので、ほんの数小節だけ演奏して 続けて第2楽章を弾いてもらうことにします 何とも贅沢な豪華共演
何とも贅沢な豪華共演 竹山さん、時間外手当を要求した方がいいですよ
竹山さん、時間外手当を要求した方がいいですよ 大江君の演奏はやや線が細いと感じましたが、短調特有の憂いに満ちた演奏が素晴らしかったです
大江君の演奏はやや線が細いと感じましたが、短調特有の憂いに満ちた演奏が素晴らしかったです スーツ姿の大江君とヴィオラの佐々木氏とともに、譜めくり労働から解放された竹山愛さんがピンクの鮮やかな衣装で登場し、さっそく「フルート四重奏曲ニ長調K.285」の演奏に入ります
スーツ姿の大江君とヴィオラの佐々木氏とともに、譜めくり労働から解放された竹山愛さんがピンクの鮮やかな衣装で登場し、さっそく「フルート四重奏曲ニ長調K.285」の演奏に入ります
 そして第2楽章から第3楽章に移るところは、憂いに満ちた顔をしていた人が、急に破顔一笑したかのような曲想で、その落差が何とも言えない魅力です
そして第2楽章から第3楽章に移るところは、憂いに満ちた顔をしていた人が、急に破顔一笑したかのような曲想で、その落差が何とも言えない魅力です 「みんながいつまでも泣いている時に、モーツアルトはもう笑っている」という感じです
「みんながいつまでも泣いている時に、モーツアルトはもう笑っている」という感じです









 女王と対面した彼は、自分はアルサ―チェではなく二ニアであることを告げ、アッスールに復讐するため墓所に向かい、女王も後を追う。一方、アッスールには王の亡霊が見え、一時狂乱状態に陥るが、我に返って墓所に向かう
女王と対面した彼は、自分はアルサ―チェではなく二ニアであることを告げ、アッスールに復讐するため墓所に向かい、女王も後を追う。一方、アッスールには王の亡霊が見え、一時狂乱状態に陥るが、我に返って墓所に向かう


 また今度、K氏が来日する際に再会できれば嬉しいです
また今度、K氏が来日する際に再会できれば嬉しいです







 モーツアルトの才能は神の寵愛を受けている唯一最高のものだ
モーツアルトの才能は神の寵愛を受けている唯一最高のものだ

 オーケストラの要はオーボエとホルンと言われるようですが、都響には広田あり、といったところでしょうか
オーケストラの要はオーボエとホルンと言われるようですが、都響には広田あり、といったところでしょうか
 スカップッチの指揮で第1曲「導入唱 悲しみの御母は立ち尽くし」が低弦の重々しい演奏から開始されます
スカップッチの指揮で第1曲「導入唱 悲しみの御母は立ち尽くし」が低弦の重々しい演奏から開始されます
 『面倒?まったく。楽しかったですよ。調べたことをちゃんと小説に生かしてもらえるんですから
『面倒?まったく。楽しかったですよ。調べたことをちゃんと小説に生かしてもらえるんですから




 その当時、妻アルマの不貞が明るみに出たことによって夫婦関係が破たんしつつあったことが、この不協和音に表れているのではないかと思われます
その当時、妻アルマの不貞が明るみに出たことによって夫婦関係が破たんしつつあったことが、この不協和音に表れているのではないかと思われます










 戦争や病気で子供たちを失うという悲しみを乗り越え、無事に成長した息子のアンリ(ジェレミー・レニエ)が幼なじみのマチルド(メラニー・ロラン)と結婚したことに喜ぶ
戦争や病気で子供たちを失うという悲しみを乗り越え、無事に成長した息子のアンリ(ジェレミー・レニエ)が幼なじみのマチルド(メラニー・ロラン)と結婚したことに喜ぶ