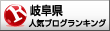1昨日、今年初めて蝉の声を聞きました。たぶんそれまでにも鳴いてはいたのでしょうけど、耳に入るほど近くで鳴かなかったり、数も少なかったのでしょう。最盛期にはやかましいほどですものね。
セミは7年間地中にいて、木の根っこから養分を吸って大きくなり、地上に出てきて脱皮、羽化してから1週間しか生きられないといわれます。そんな儚さ(はかなさ)が小説「八日目の蝉」とか源氏物語「空蝉(うつせみ)」などの題名に使われたのでしょう。

でもそう思われているのは飼育するのが難しく一週間くらいで死んでしまうからというだけで、実際には成虫になってから1ヶ月くらい生きるらしいです(参照)。では地中生活はというとセミによって短いものは3年、一般的には5~8年、長いもので13年とか17年というのもいます。
岐阜で一般的なセミはニイニイゼミ(今はあまり見かけません)、アブラゼミ(代表的なもの)、ミンミンゼミ(あまり見かけませんが)、クマゼミ(最近多くなったらしい)、そして山間に行くとツクツクボウシやヒグラシですね。ヒグラシ以外は鳴き声はやかましいです(セミの図鑑参照)
ところで私の住まいの近くに南蝉(みなみせみ)という地名があります。
律令制時代の官道である東山道(とうさんどう)に面しています。
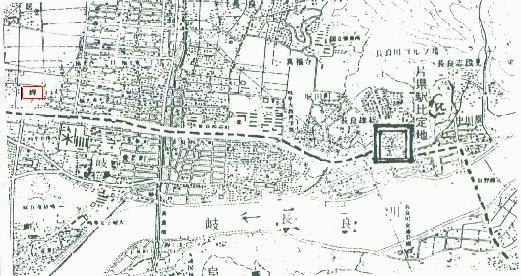
この蝉という地名は何を意味しているのでしょう?
地名語源辞典によると「せまいところ」の意味で「狭(せま)」と同根の語だと書いてあります。漢字を当てた地名では瀬見が多いようで、岐阜でも山県市谷合に瀬見渓谷とか瀬見峡温泉がありました(地図)。
でも南蝉のどこが狭いのでしょう?ひょっとすると長良川が分流していた時代には田圃とか自然堤防上の道とかが狭いなど、そう名付けるだけの要因があったのかもしれません。

セミに関しての「たわごと」でした m(_._)m
「そうなの!」と思われた方はクリックしてくださいね~♪
 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ
↑
日々更新の励みになりますので、クリックをお願いいたします。
セミは7年間地中にいて、木の根っこから養分を吸って大きくなり、地上に出てきて脱皮、羽化してから1週間しか生きられないといわれます。そんな儚さ(はかなさ)が小説「八日目の蝉」とか源氏物語「空蝉(うつせみ)」などの題名に使われたのでしょう。

でもそう思われているのは飼育するのが難しく一週間くらいで死んでしまうからというだけで、実際には成虫になってから1ヶ月くらい生きるらしいです(参照)。では地中生活はというとセミによって短いものは3年、一般的には5~8年、長いもので13年とか17年というのもいます。
岐阜で一般的なセミはニイニイゼミ(今はあまり見かけません)、アブラゼミ(代表的なもの)、ミンミンゼミ(あまり見かけませんが)、クマゼミ(最近多くなったらしい)、そして山間に行くとツクツクボウシやヒグラシですね。ヒグラシ以外は鳴き声はやかましいです(セミの図鑑参照)
ところで私の住まいの近くに南蝉(みなみせみ)という地名があります。
律令制時代の官道である東山道(とうさんどう)に面しています。
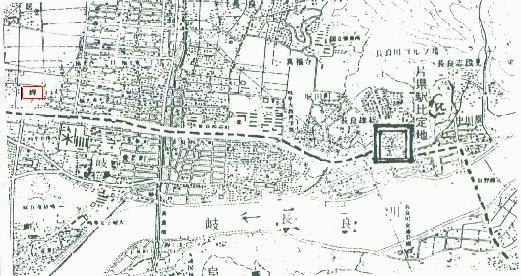
この蝉という地名は何を意味しているのでしょう?
地名語源辞典によると「せまいところ」の意味で「狭(せま)」と同根の語だと書いてあります。漢字を当てた地名では瀬見が多いようで、岐阜でも山県市谷合に瀬見渓谷とか瀬見峡温泉がありました(地図)。
でも南蝉のどこが狭いのでしょう?ひょっとすると長良川が分流していた時代には田圃とか自然堤防上の道とかが狭いなど、そう名付けるだけの要因があったのかもしれません。

セミに関しての「たわごと」でした m(_._)m
「そうなの!」と思われた方はクリックしてくださいね~♪
 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ↑
日々更新の励みになりますので、クリックをお願いいたします。