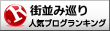今年は読みかけで止まっていたり、ここに書くつもりでなかなか書けない本が増えてしまった。
この「聖断」は、夏に見た映画「日本のいちばん長い日」の原作となったもので、8月下旬に買ったものだ。 半藤一利著 PHP文庫

「日本のいちばん長い日」は大宅壮一氏名義で、1965年に出版されたとのことだが、これはその20年後に書かれたものだ。まだ昭和時代は続いていた。
「日本のいちばん長い日」が、終戦直前のきわめて短い瞬間を描いているのに対し、「聖断」は鈴木貫太郎が生まれた慶応3年から亡くなる昭和23年までの生涯を描くと共に、彼が深く関わった海軍、そしてその背景となる、維新後終戦までの日本そのものの歴史を描いている。
漫画の描写などで、主人公とその背景をどう描くかというバランス取りは人によって様々だ。主人公のポートレイトはど~んとアップで目立つが、周りの建物や室内描写などは単純な線画で済ませる人もいるし、人物よりもむしろそちらに主題があるのだとばかり、草木や空などの風景に力が入れられているような描写をする人もいる。
半藤氏はそのたとえで言うと、背景の絵をしっかりと描くタイプなのだと思う。それも、単なる一過性の取材ではなしえないような、幅広い知識を持つ半藤氏でなければできない描写として。
だた、たとえば司馬遼太郎氏などと比べると、その描写は精密デッサンというべきもので、司馬氏のように、そのテクスチャや風合いを楽しむ、という描写ではない。
まえ書きそびれたことだけど、半藤氏や、水木しげる氏など、先の戦争のことをよく取り上げている方々って、なんとなく戦争で無念の死を遂げられた人たちに生かされているのかも、という気がする。半藤氏自身が対談でそういうことを話していた(夢でうなされて、皆さんのことを書きますから、と答えたとか)し。
昨日、テレビでドナルド・キーン氏のことを特集した番組を見た。戦前、海兵隊兵士の頃から日本を見続け、日本文学を世界に知らしめた人だ。キーンさんもなにものかが彼にその使命をあたえ、彼もそれに答えてきたことで、90歳を超えた今でもお元気で活躍され続けているのかな、などと考えながら見ていた。ちょっと奇妙な感想かも知れないが。