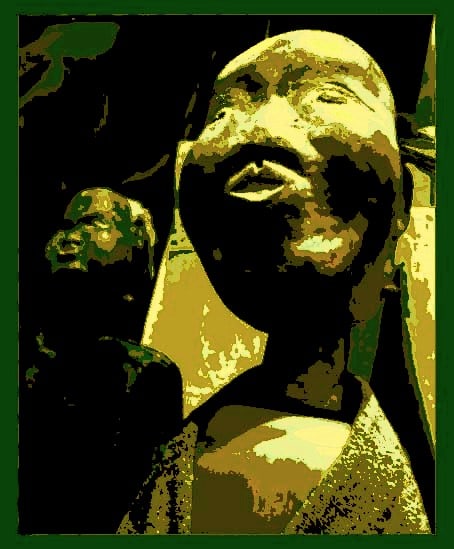(写真は民族学博物館にて撮す ↑)



(今日は奈良の広瀬神社の砂かけ祭り。2006年に撮す ↑)
記録だけ
2009年度 22冊目
民俗と文化の同一性を探る『日本文化のふるさと』






岩田 慶治 著
平成3年12月5日第1版
角川書店
角川選書 222
1300円+ 税
二月十日。
約一週間ぶりで本を読み終える。
今月は まだ五冊目か・・・。
何をするでもなく漠然とした空白の時間。
反省点は多い。
民俗と文化の同一性を探る『日本文化のふるさと』はほんの名でもわかるように日本文化をアジア諸外国戸比較検討しながら紐とかれていた。
中国やタイの話は日本文化の元になっている部分も多く、興味深い。
共通点が多いとはいえ、タイとビルマの国境産地に住むイコー族(アカ族ともいう)の村の入り口に立てられた鳥居は、今現在の日本で見られる鳥居にそっくりだ。(四十六ページ)
また鳥居の横木の取り付けられた木彫りの鳥は、日本の初期の木 一本を立て上に鳥をのせたと伝えられているる鳥居を思い浮かべる。(四十七ページ)
なお、木 一本を立て上に鳥をのせた鳥居は、大阪の国立民俗博物館でも見ることができる。
タイの出産の方法は、日本のケガレとしての隔離された様子を思い出す。
意味合いは日本とは逆とされているが、ハレとケガレは逆一対とされる考え方もあるので、あながち無関係とも言い難い。
死における『魂夜這』は興味深い。
死に瀕し 霊魂が身体から去ろうとするのを、何とかとどめようとする。
人が死に行こうとするとき、『カン・ピー』という古書を持ち出して、必ず死ぬ運命かどうかを判断するという。
こういった魂夜這の習慣は、ラオ族、タイ族、クメール族に広く行き渡っているらしい。
クメール族の神の木偶は日本のこけしの形に似ている。
二対の木偶はクメール族の村祠(そんし)である。
滋賀県の安土町の弥生式遺跡跡から発掘された日本最古の木偶と クメール族の木偶とのあいだに、一脈通じるものがあると、著者は書かれている。
稲作儀礼なども紹介され、興味は尽きない。
日本文化に焦点をひく本書は、誠に面白くためになった事を付け加えておく。