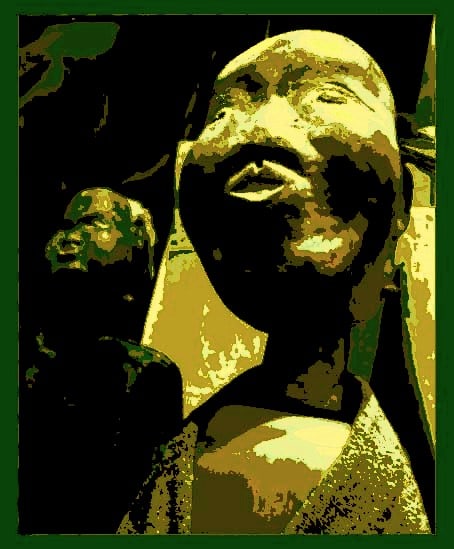最近 やたら日がたつのが早いと感じる。
年齢のせいだろうか・・・。
鏡に前で、とり繕ったような笑顔を浮かべる。
娘は若い。
そういうと シンデレラの継母は実母だったという話を読んだことがある。
私くらいのお年頃の女性は複雑。

二月になって外出を控える。
友人からさそわれていた『伊丹能』を辞退。
残念な事をしたかな・・・。

最近 家族が家にいる日がやたら多い。
加えて、子どもも後期テストを終え、家にいる。

最近 私は庭の整理と料理遊びで明け暮れる。
テレビはほとんど見てない。
映画や歌舞伎チャンネル、シアターテレビジョンもつけたことがない。
気がつけば、草花や食材対話。

去年から気になっていた紅葉の木は虫にやられたようだ。
植木屋と相談の上、灯籠と岩や石は動かさず、全面的に庭の木を入れ替えてもらうことにした。
山のように盛っていた部分は少しなだらかにしてもらう。
今までは純和風の落ち着いた庭だったが、花木を入れる。
木は季節毎に花の楽しめるものにしてもらった。
気に入ったペルシャ風の鉢に花やハーブを植え、アクセントにしよう。
日本とイランの折衷庭もいいかもしれない・・・。

庭木の植え替え後、庭でバーベキューをしよう。
ござをひき、ペルシャジュータンをひいてキャバブを食べることと楽しいかな。
夕刻には等々に火を灯すと、妙にミスマッチがしっくりいくような・・・。
妄想は尽きない。

庭の岩が黒く汚くなった。
去年の秋に気になってハイターでごしごしと洗ったが、やはり黒ずんでいる。
植木屋に問うと、奈良の生駒の岩で 黒くなり苔が生える方が価値があるという。
どびゃぁ~! 知らなかった!
それを聞いて、私は青ざめるやら、後悔するやら・・・。
灯籠は泥はとるが、苔や汚れはそのままにして楽しんでいた。
だんだん味わいが出てきて、喜んでいた。
だが、岩は黒ずんで汚かった。
いくら黒くなる方がいいとはいわれても、気に入らない黒である・・・。
苔といわれても、庭のみどりの苔のように美しくも何ともない。
まるで黴だ・・・。
一層のこと、植木屋に頼んで運んでもらいたいとも思ったが、かなりたいそうな事になるらしく、今回は諦めた。
もう少し形と色の面白い石に変えたいな・・・。

気になる料理に毎日挑戦。
イラン料理もいくつかつくってみた。
かなり近い味になり、気に入っている。

昨日はフェセンジャンという料理遊びを楽しむ。
先日行った大阪の某ペルシャ料理店よりも現地の味に近い。
トルコで購入したアナールソース(石榴ソース)やクルミなどを使い、鶏肉を柔らかく煮込んだ。
夫はご満悦。
子ども達は初めて食べる味に、驚きと喜びを表わしていた。

毎週 農家の新鮮野菜を購入。
歴史教室関係でお世話になっている物書きの方からも、月に何度かお野菜や果物を頂く。
奈良の新鮮な野菜を使い、旬の手頃な魚や肉を利用して料理するのは楽しくて仕方がない。
気がつけば 毎日、台所にたつ時間が長い。

パンも相変わらず毎日焼いている。
以前は長芋を使ってパンを膨らますことに力を注いでいた私。
今は、豆パンに明け暮れる。
いろいろな豆を煮て餡にする。
甘味料はラカントなどを使用するので、家族全員が安心して食べることができる。
この餡が友人や知人にも好評。
頼まれることが多く、多くつくってはプレゼントをしている。
かわり餡は おはぎやあんパン、また直接食パンに挟んで楽しまれているようだ。
友人の喜びは私の喜び。
人の笑顔は嬉しいものだ。

今年になってだし味の大根煮を極めた。
人はおでんとも言う。
豚肉や鳥胸肉の固まり二、三キロくらいといっしょに煮込んでポトフ風にしたり、昆布鰹出汁で煮込んだり・・・。
大根などの野菜の種類や厚さ、形も工夫してみた。
そうしてついに上手いおでんが完成した。
これは我が家オリジナルおでん。
多分奈良の何処の店にも負けないかも知れないと、妙な自信に満ち足りた快感。
これだから、料理の素人は困る!

今年になってもう一つ。
健康お好み焼きというものを考え出した。
いろいろな種類の野菜たっぷりで、味付けは鰹節など。
塩分はゼロ。
オーブンで焼くので、油も使わない。
食べる際に、好みのソースをかける。
とうふや野菜や魚や肉や、いろいろなものを試してみた。
そしてかなりいい線まできた。
これも隔日くらいに焼いている。
諸外国ではこの料理をオムレツと呼ぶかも知れない。

少し暖かになってきたので、胡麻豆腐と卵豆腐を極める予定。
さて、どういった配分が我が家に合うかが楽しみ・・・。

二月も後二十日となった。
漠然とした時間を過ごしてしまった二月前半。
後半はどういった生活を描こう・・・。
考えると心ときめく。































 2
2 3
3 4
4 5
5