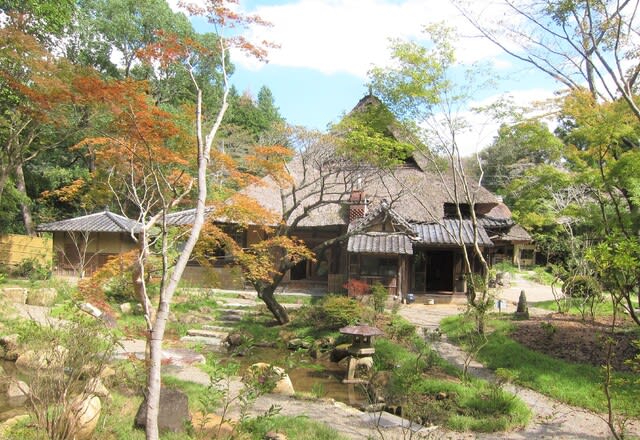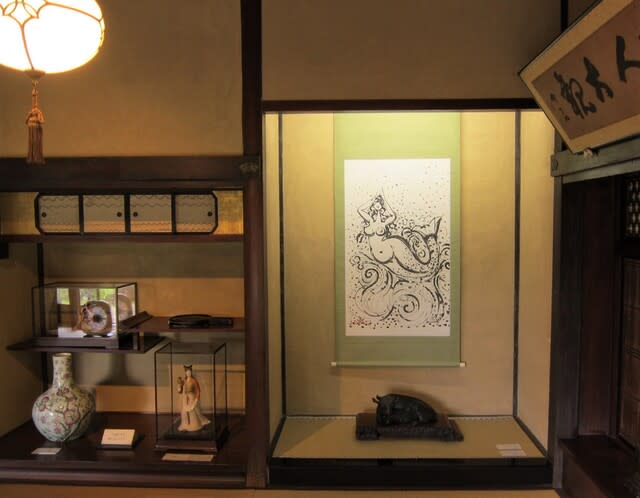10月4日、5日の2日間、嶋崎城址(潮来市)で発掘された歴代供養塔の現場見学会が行われました。2019年12月以来の2度目の訪問です。

本丸虎口の高い土塁は、御鐘台とも呼ばれ、時報や登城合図を知らせる鐘があったといわれます。
昭和55年(1980)、本丸にある御札神社社殿改修工事で資材運搬のため拡幅したところ、土塁下部に3.47mの長さにわたり板碑2点、五輪石塔材40点が敷かれているのが発見されました。その後2回にわたり解明調査をして、土塁の破壊につながるさらなる発掘はせずに埋め戻したそうです。

天正19年(1591)島崎氏を滅亡させた佐竹氏は、農耕に適した温暖で近隣の津(港)を掌握する豊かなこの地の拠点として堀之内大台城を築城しますが、慶長元年(1596)に完成するまでの5年間は城代小貫頼久がここに居城、その時に埋められたと思われます。なお、堀之内大台城発掘調査でも、主殿と城門礎石群はすべて、五輪塔・宝筐印塔・板碑の石塔を転用していることが見つかったそうです。

この石塔類はまた埋め戻されるそうですが、多量の石塔が埋められている謎は、専門家の調査を待たないとわからないとの説明でした。ただ気楽な仙人は、城を攻め落とした佐竹氏の城代、小貫頼久が嶋崎氏の跡形をすべて抹殺したかったのではないかと推測します。多分嶋崎氏を滅ぼした経緯に、疚しいうしろめたさを感じていたのではないでしょうか?
伝えられているこの話は、拙ブログ「頃藤城(大子町)…謀殺された嶋崎城主親子2021年9月14日」で紹介させていただきました。

北側から見た嶋崎城、手前に「お投げの松」が見えます。落城の際、城主義幹(安定)が大事にしていた松の銘木を、奥方が城外へ投げ捨ててしまったのが根付いたと伝わっていますが、松枯れ病で枯れてしまい、三代目の松だそうです。


さて、2年前の訪問時には、生い茂った草木に覆われて全貌がよく見えませんでしたが、今回はびっくりしました。嶋崎城址を守る会の活動により、草木が刈られた城域と歩道、随所に設置された丁寧な案内板、しかも大きな駐車場まで整備されていました。このグループは「嶋崎城址を守る会」というブログも立ち上げているので、詳しい内容がよくわかります。
上記の嶋崎城予測図は当日配られたパンフレット掲載のものです。

広い帯曲輪には休憩できるスペースもできました。右手の切岸は砂岩層、左手の一段下には腰曲輪があります。

大手道を突き当たると、東2郭の高い切岸が行く手を遮ります。右手が1郭虎口方面、左手が帯曲輪を経て物見台方面です。

1郭手前には水場のある水の手廓があり、1廓との間は空堀ですが、もとは水堀だったのではと案内の方の話です。

1廓は土塁で囲まれ、13代嶋崎長国が鹿島神宮の御札を身に着けて戦ったら無傷で勝利したので、その御札を祀ったと伝わる御札神社が建っています。

1廓の虎口を出ると土塁に囲まれた馬出廓があります。本丸攻撃を防ぐ緩衝地帯です

馬出郭から東2郭へ向かう土橋があります、城内には丁寧な案内板がいたるところに掲げられています。

東2郭は四方を深い堀や断崖に囲まれており一番奥に八幡台があります。

八幡台と物見台の間の空堀は最深部で20mもの高さがあります。
この鉄壁ともいえる守りの城も、最後の領主嶋崎安定とその子徳一丸が佐竹氏に謀殺され、その後の攻撃であっけなく落城してしまいます。そしてその佐竹氏も、嶋崎城奪取の11年後には、家康により秋田に移封され、一帯で手に入れたすべての城は廃城となってしまいました。

当日は地元の「嶋崎城址を守る会」の方々が詰めていて案内、説明をしていただきました。

要所には大きな案内看板、地元の活動に触発されて行政も予算を付けたようです。
この壮大で遺構のしっかり残った中世の城跡を、保存、管理されている地元の皆様に多大なエールを送りたいと思います。