
 三笠小学校裏の三笠山・・・観音山とも呼ばれる。
三笠小学校裏の三笠山・・・観音山とも呼ばれる。 三笠山は標高119.8mの超低山。近くには三等三角点の滝見沢・三笠山593.6mもあるが夏は行きたくない
三笠山は標高119.8mの超低山。近くには三等三角点の滝見沢・三笠山593.6mもあるが夏は行きたくない 。
。 北海道博物館資料
北海道博物館資料 明治15年(1882年)、この地に空知集治監が設置された際、奈良県出身の看守が郷土の三笠山(現在の若草山)に似ていることから三笠山と命名した。
明治15年(1882年)、この地に空知集治監が設置された際、奈良県出身の看守が郷土の三笠山(現在の若草山)に似ていることから三笠山と命名した。 500本を超す
500本を超す エゾヤマザクラやヤエザクラのほか、クロマツ、アカマツなど12種類が植樹されている。隠れお花見スポットとして近年訪れる方が増えている。
エゾヤマザクラやヤエザクラのほか、クロマツ、アカマツなど12種類が植樹されている。隠れお花見スポットとして近年訪れる方が増えている。 いまはナナカマドが色づきはじめている。
いまはナナカマドが色づきはじめている。 一番那智山からスタート
一番那智山からスタート
 きのこいっぱいである。毒キノコ
きのこいっぱいである。毒キノコ











 大杉
大杉 頂上は広い。見晴らしは良くない
頂上は広い。見晴らしは良くない

 何度か
何度か
 車で登っている達布山143.7m二等三角点▲太峰山である。漢詩の勉強兼ねて
車で登っている達布山143.7m二等三角点▲太峰山である。漢詩の勉強兼ねて 久し振りに正規の登山道から登る。
久し振りに正規の登山道から登る。 登る人が少なくなったせいかやや不明瞭である
登る人が少なくなったせいかやや不明瞭である ツユクサは多い
ツユクサは多い 青が映える
青が映える ヒグマ🐻もいるのかな
ヒグマ🐻もいるのかな
 二等三角点の頂上
二等三角点の頂上 達布山▲三角点の説明
達布山▲三角点の説明 展望台から高いほうの三笠山
展望台から高いほうの三笠山 山頂にある漢詩碑。1882年(明治15年)に内務卿として視察に訪れた山田顕義が、達布山からの眺望を詠んだ漢詩を刻んでいる。
山頂にある漢詩碑。1882年(明治15年)に内務卿として視察に訪れた山田顕義が、達布山からの眺望を詠んだ漢詩を刻んでいる。
 在眼天塩石狩洲/長川一帯入空流/可無禦侮張権策/駐馬太布山上秋
在眼天塩石狩洲/長川一帯入空流/可無禦侮張権策/駐馬太布山上秋 眼(め)に在り天塩 石狩の洲(しま)/長川(ちょうせん)一帯 空(いったいくう)に入りて流る/禦侮張権(ぎょぶちょうけん)の策 無かるべけんや/馬を駐(とど)む 太布(たっぷ)山上(さんじょう)の秋
眼(め)に在り天塩 石狩の洲(しま)/長川(ちょうせん)一帯 空(いったいくう)に入りて流る/禦侮張権(ぎょぶちょうけん)の策 無かるべけんや/馬を駐(とど)む 太布(たっぷ)山上(さんじょう)の秋 一読しても内容は難しい
一読しても内容は難しい 奥が深そう・・・
奥が深そう・・・ 【
【 日本大学法学部125年記念誌】山田は、長州藩(山口県)出身。松下村塾に入門し、明治維新時には、戊辰戦争などで政府軍の指揮を執ったほか、伊藤博文や木戸孝充らとともに、明治政府の中枢を担い、司法大臣などを歴任。三笠へは1882年(明治15年)に内務卿として、炭鉱や鉄道の視察で訪れた。このとき、三笠市内の達布山からの眺望を漢詩に残している。 日本大学や國學院大學の基礎をつくった。
日本大学法学部125年記念誌】山田は、長州藩(山口県)出身。松下村塾に入門し、明治維新時には、戊辰戦争などで政府軍の指揮を執ったほか、伊藤博文や木戸孝充らとともに、明治政府の中枢を担い、司法大臣などを歴任。三笠へは1882年(明治15年)に内務卿として、炭鉱や鉄道の視察で訪れた。このとき、三笠市内の達布山からの眺望を漢詩に残している。 日本大学や國學院大學の基礎をつくった。 簡単だけどもう整備されていない散策路
簡単だけどもう整備されていない散策路 往復25分
往復25分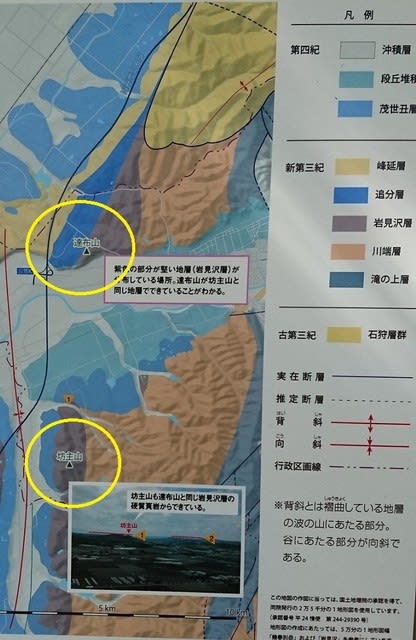 硬い岩石でできている達布山の地層の特徴がわかる山頂パネル
硬い岩石でできている達布山の地層の特徴がわかる山頂パネル 三笠市は市一帯が日本ジオパーク(地質遺産)に認定されている「三笠ジオパーク」となっている
三笠市は市一帯が日本ジオパーク(地質遺産)に認定されている「三笠ジオパーク」となっている ・・・
・・・










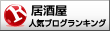

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます