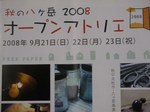昨夜は気温が9度と書いたが、朝起きたら温度計は5度になっていた。
寒さが違う。
身体で感じる温度は確かでこれまでにない冷たさを感じ取る。
今日は炬燵にしてみたところ、案の定あほ犬2匹はいそいそと炬燵にもぐっていったまま出てこない。
暫くして体が温まると出て来てはドタンと横になり身体を冷やしては、又炬燵にもぐるという繰り返し。
昨日は自分の人生を振り返ってみた。
今医療職でいるが、小さい頃母親から私は3度死に掛けたと言われて
育ってきた。
自分の記憶がのこりはじめたときにも病院通いの記憶が沢山思い出せる。
5歳の時肺炎で死に掛けた。これは覚えていないが、台湾から引き揚げて来た家族は小さな家で暮していた。山田先生という町医者が寒い家の中で寝ている私のために障子を入れて風を防いで暖め、当時やっと出始めたとてもでは高価で手が出ないペニシリンの注射を打ってくれて死に掛かっている私は助かったそうだ。
それが無かったら5歳の命だったそうな・・・・。
赤ひげ先生のお陰で今の私はいるのだ。
その後歯髄炎で高熱を出し顔中腫れて死に掛かったそうだ。
敗血症という。
これは覚えている。遠足での帰り同級生がお見舞いに寄ってくれたから。
小学校1年には大やけどで左手1本丸ごとやけどして毎日病院へ行き、水泡を鋏で切ってもらった覚えもある。
痛くて毎晩泣いていた。その傷跡はいまでも残っている。
小児の初感染結核で中学2年の時1年間薬を飲み、体育は休んだ。
蕁麻疹や中耳炎でバスに乗り遠い町まで耳鼻科に通った。
骨折したり脱臼したり、骨の成長痛で毎晩小学生の頃は泣いていた。
昔は貧乏な世の中、医療費がかかり、病気がちの子供を育てていく母親は気苦労が耐えなかったであろうと、今になって感謝するのである。
高校になってからやっと病気とは縁がなくなった。
結婚して家族の面倒を見る立場になったら、病気をすることが許されなくなった。
お陰で気強く生きて来れたが、小さいときに何度か死に掛けた子供が成長して今は、人様を病気から逃れる方法を指導する仕事をしている。
自分の生き方をしっかりと考えたことも無いのに、本当は無かった命、60才を過ぎても仕事を持って一人で生きているし、人様のために役に立っているのは神様の采配かなとも思う。
寒さが違う。
身体で感じる温度は確かでこれまでにない冷たさを感じ取る。
今日は炬燵にしてみたところ、案の定あほ犬2匹はいそいそと炬燵にもぐっていったまま出てこない。
暫くして体が温まると出て来てはドタンと横になり身体を冷やしては、又炬燵にもぐるという繰り返し。
昨日は自分の人生を振り返ってみた。
今医療職でいるが、小さい頃母親から私は3度死に掛けたと言われて
育ってきた。
自分の記憶がのこりはじめたときにも病院通いの記憶が沢山思い出せる。
5歳の時肺炎で死に掛けた。これは覚えていないが、台湾から引き揚げて来た家族は小さな家で暮していた。山田先生という町医者が寒い家の中で寝ている私のために障子を入れて風を防いで暖め、当時やっと出始めたとてもでは高価で手が出ないペニシリンの注射を打ってくれて死に掛かっている私は助かったそうだ。
それが無かったら5歳の命だったそうな・・・・。
赤ひげ先生のお陰で今の私はいるのだ。
その後歯髄炎で高熱を出し顔中腫れて死に掛かったそうだ。
敗血症という。
これは覚えている。遠足での帰り同級生がお見舞いに寄ってくれたから。
小学校1年には大やけどで左手1本丸ごとやけどして毎日病院へ行き、水泡を鋏で切ってもらった覚えもある。
痛くて毎晩泣いていた。その傷跡はいまでも残っている。
小児の初感染結核で中学2年の時1年間薬を飲み、体育は休んだ。
蕁麻疹や中耳炎でバスに乗り遠い町まで耳鼻科に通った。
骨折したり脱臼したり、骨の成長痛で毎晩小学生の頃は泣いていた。
昔は貧乏な世の中、医療費がかかり、病気がちの子供を育てていく母親は気苦労が耐えなかったであろうと、今になって感謝するのである。
高校になってからやっと病気とは縁がなくなった。
結婚して家族の面倒を見る立場になったら、病気をすることが許されなくなった。
お陰で気強く生きて来れたが、小さいときに何度か死に掛けた子供が成長して今は、人様を病気から逃れる方法を指導する仕事をしている。
自分の生き方をしっかりと考えたことも無いのに、本当は無かった命、60才を過ぎても仕事を持って一人で生きているし、人様のために役に立っているのは神様の采配かなとも思う。