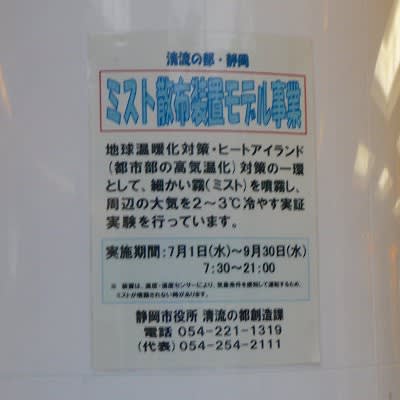▽今年のポスター

↓ 左端の拡大(小梳神社前では金魚すくいも・・・)


▽呉服町二丁目3番地附近

まだまだ先のことと思っていた夜店市
暦をあらためて見てみれば再来週のことで
この通りが人で埋めつくされるのも、もうすぐなのです。
▽呉服町一丁目7番地附近

サーカスと言えば、
戦前は、境内が広大だった下魚町(現常磐町二丁目)の寶台院でも行なわれたとか
そこまでの昔の状況は知らないのですが
サーカスと言えば
浅間神社の境内やその向かえの西草深公園で行なわれていた
4月のお祭りを思い浮かべます。
近年は祭に関係なく
駿府公園などで行なわれていましたが
現在は東静岡駅前が定位置となったようです。
▽静岡駅前・御幸町8番地附近

東京生命跡にできたビルには飲食店が入居するようだ。
銀行の隣りに飲食店というのはやや異色な感もあるが
現在の経済情勢ではどんな業種でも
入居してくればいいというところだろうか。


↓ 左端の拡大(小梳神社前では金魚すくいも・・・)


▽呉服町二丁目3番地附近

まだまだ先のことと思っていた夜店市
暦をあらためて見てみれば再来週のことで
この通りが人で埋めつくされるのも、もうすぐなのです。
▽呉服町一丁目7番地附近

サーカスと言えば、
戦前は、境内が広大だった下魚町(現常磐町二丁目)の寶台院でも行なわれたとか
そこまでの昔の状況は知らないのですが
サーカスと言えば
浅間神社の境内やその向かえの西草深公園で行なわれていた
4月のお祭りを思い浮かべます。
近年は祭に関係なく
駿府公園などで行なわれていましたが
現在は東静岡駅前が定位置となったようです。
▽静岡駅前・御幸町8番地附近

東京生命跡にできたビルには飲食店が入居するようだ。
銀行の隣りに飲食店というのはやや異色な感もあるが
現在の経済情勢ではどんな業種でも
入居してくればいいというところだろうか。

▽パウル・クレーの絵ではありません。

紺屋町(こうやまち)の小梳神社(おぐし・じんじゃ)の花火です。
20:00と20:50にそれぞれ5~6分程度の
各地のいわゆる花火大会に比べれば、ささやかな花火です。
それでも街中の神社の狭い境内で
すぐ目の前で行なわれる花火は
なかなか迫力があるのです。
それに、見物人も100人もいない程度ですので
押し合いへしあいもなく、見られるのもいいのです。
もっとも、狭い境内でこれ以上
人が集まるようになったりしたら危険で
今後継続できなくなるでしょうから
規模を大きくすることなく
御近所さんが集まる程度がかえっていいのでしょう。
なお、今夜も同時刻で実施されます。


静岡空港と
小松(石川県)、熊本、鹿児島と結ぶ
FDA(フジドリームエアラインズ)が就航した23日
通りがかった静岡駅前地下広場では
熊本県の観光キャンペーンが行われていました。
(今回の写真は携帯電話のものです。)
▽山鹿市の「山鹿灯籠踊り」

熊本県の県庁所在地である熊本市は、
明治初頭に福岡と博多が一つの地域になるまでは
(まだ市町村という概念はなかった)
九州最大の都市でした。
また来春には合併により人口が72万人となり
政令指定都市への移行も確実と言われています。
したがって、拠点都市として
それなりの格式を備えた町でしょうから
一度は訪れてみたいと思いながら
機会がありませんでした。
▽いつもは静岡の映像が流れるこの装置(名称不詳)に
熊本城築城400年を記念して復元された熊本城本丸御殿の映像が・・・

このFDAの就航をきっかけとして
ぜひ熊本を訪れてみたいとは思いますが
どうも小さな飛行機では
“ごせっぽくない”です。(笑)
▽いただいた飴「天草宝島お宝スィーツ」

やはり電車寝台のサンライズ出雲で岡山まで行き
そこから早朝の新幹線で行った方がいいかな
なんて思ったりします。
(静岡0:20→熊本9:59)
10時に現地に着けば十分「0泊3日」(正確には「2日」)で行ってこれますし(笑)
▽NHK・GTVの「いおうとう」からの中継

硫黄島は「いおうじま」と記憶している人が多いかもしれません。
でも最近は、公式には「いおうとう」と言うようです。
一般に「いおうじま」と言われるようになったのは
戦前、地元では「いおうとう」と言っていたのに
戦後、米軍が「いおうじま」と言うようになったために
広まってしまったということです。
なにやら、山手線が戦前「やまのてせん」と言われていたのに
日本語が不十分な(?)“占領軍”により「やまてせん」となってしまい
1971年に正式に「やまのてせん」に復活されたのに似た“はなし”ではあります。
まあ、固有名詞の読み方は地元優先でお願いしたいです。
まちがっても、安倍川(あべかわ)を「あべがわ」とは読まないでほしいです。(笑)

硫黄島は「いおうじま」と記憶している人が多いかもしれません。
でも最近は、公式には「いおうとう」と言うようです。
一般に「いおうじま」と言われるようになったのは
戦前、地元では「いおうとう」と言っていたのに
戦後、米軍が「いおうじま」と言うようになったために
広まってしまったということです。
なにやら、山手線が戦前「やまのてせん」と言われていたのに
日本語が不十分な(?)“占領軍”により「やまてせん」となってしまい
1971年に正式に「やまのてせん」に復活されたのに似た“はなし”ではあります。
まあ、固有名詞の読み方は地元優先でお願いしたいです。
まちがっても、安倍川(あべかわ)を「あべがわ」とは読まないでほしいです。(笑)
▽ 静岡駅前公共地下道(パルシェ前)に掲示の金沢市の観光ポスター
静岡市のコピー「色・豊かなまち静岡」が抽象的すぎて何を言いたいのか分らないのに比べ、
金沢市の「時間(とき)が心を染める街」の方がはるかに秀逸だなぁ・・・。
ローカルニュース等で報道されていますが
静岡空港(静岡県牧之原市)と小松空港(石川県小松市)とを結ぶ
FDA(フジドリームエアラインズ)が
23日に就航するのをきっかけとして
静岡市は、金沢市と観光振興などに向けた交流連携協定を締結するそうです。
(那覇市とは既に協定済みらしい。)
協定内容(例によってお役所によくある抽象的な言い回しですが)は
▽広報などを活用した両市のPR活動の推進
▽市民レベルの交流促進
▽観光振興などに向けた施策推進
▽歴史遺産や伝統工芸などの地域資源の相互活用
ということで、23日の1番機で静岡市長が金沢市役所を訪れ
調印するということです。
静岡市と金沢市は
静岡市長が「両市は伝統工芸産業が盛んなど似ているところが多い。」
と言っているように、たしかにそういう側面があることは事実です。
静岡市は政令市、金沢市は中核市で
都市としての規模は静岡市が上ということにはなっています。
でも、いくら旧静岡市が徳川宗家ゆかりの町とはいっても
金沢市の町としての品格や伝統文化の懐の深さには
ちょいとかなわないのではないかと思われます。
(旧静岡市が1940年の静岡大火と1945年の米国による無差別空襲により
城下としての街が壊滅状態になってしまったのに対し
金沢市は空襲を受けなかったため伝統や文化が温存されたということもありますが)
どうも今回の協定は
静岡市の金沢市に対する一方的な思慕にも似た
片思いの結果に終わるような気がしてなりません。(笑)
↑ 静岡県情報の人気ランキング
参 考 : 09年6月1日現在の登録人口(登録世帯数)
金沢市 448,489人(188,941世帯)
静岡市 727,665人(295,664世帯)
旧静岡 473,408人(196,410世帯)
※旧静岡は単純に清水区分を除いた数字
なお、金沢市は登録人口より推計人口の方が多い。(ちと不思議)
登録人口=住民基本台帳+外国人登録
推計人口=国勢調査の数字に毎月の人口動態の数字を加除したもの。
(国勢調査の数字には当然に未登録者が含まれる。)
全くの余談ながら、石川市は石川県にはなく沖縄県にありました(現うるま市)。念の為(笑)
今朝はクマゼミがはげしく鳴いていました。
関東甲信地方では梅雨が明けたということですが、静岡・九州北部間では、まだのようです。
(気象関係の地域区分を地理的区分でなく、
行政的区分の「関東甲信地方」という言い方もおかしいと思うのだが
そんなことを思う人はほとんどいないのでいいということなのだろう。)
▽ほぼ外観を表した再開発ビル

▽5月18日の時点では・・・

▽23日のFDA(フジドリームエアラインズ)就航に伴い倍増する(させられる?)空港行きバス
(平日で現在の5本が10本に)


▽最近、横断禁止の表示を無視して渡る人が増えてきているようだ。
都会の主要交差点で横断禁止となっているところは少ないので、
特に東京方面から来たと思われる人に多いようだ。
なかには携帯電話の案内にしたがいチュウチョなく渡る人もいる。
(地下道までは表示されないのだろう。)
たしかに今どき地下道のみの横断に固執しているのも時代遅れだとは思われる。


▽静岡ではあまり見ることがないピンク色が目立つJR西日本バス
三宮21:40発(大阪・京都経由)の夜行便で静岡に7:00到着

▽万年工事中の地下通路

こちらの上魚町からの続きです。
▽ 左:敷地が本通一丁目と金座町(きんざまち)にまたがる日本銀行静岡支店は
建物の正面が本通を向いているにもかかわらず所在地に金座町を名乗る。
(本通は「ほんどおり」ではなく「ほんとおり」。 アクセントは「高低低低低」)
▽ 右:同じく、中町(なかちょう)と金座町にまたがる清水銀行静岡支店(元、中部銀行本店があった場所)も同様に金座町所在を名乗る。
銀行にとって相性のよい町名ということも言えると思われる。
(金座町は 住居表示未実施で「番地表示地区」)
▽ 安西・茶町の製茶問屋への通り道であるこの通りは
かつてお茶の見本缶を持った「さいとりさん(お茶のあっせん業者)」が
静岡駅から自転車で争うようにここを通ったという。
そのため自転車の修繕需要も高く自転車屋さんが多い通りだったという。
この先、土手通りの向こう側は茶町、当然にお茶屋も何軒かある。
(これらのお茶屋はさりげない店構えでも江戸期からの創業もめずらしくない。)
お茶屋の隣りは金座稲荷でその前に金座跡の記念碑がある。
▽ 左:マンションなどが増えつつある金座町の通り、電柱の看板にもあるようにお茶の関連産業の事業所も多い。
▽ 右:金座町の横丁(土手通り)にはこんな店(量り売りの味噌屋)もある。
大正時代に静岡で初めての歩道付きの道路となり
小間物屋であった“千代鍛冶”が勧工場 (かんこうば:こんにちのデパートに当る)と
なるとなるなど 常に話題を提供していた上魚町が
昭和の時代になると その繁華性をしだいに失ったのは
1889(M22)年の鉄道の開業により
静岡市の町の重心が徐々に静岡駅方面に移っていったことが大きいのでしょう。
また、中心地点であるがゆえに
この地域(上魚町・旧呉服町一丁目、旧呉服町二丁目)に
銀行(安倍銀行・三十五銀行・静岡銀行など)や会社が進出し
商店街が虫食い状態のようになってしまったことも
人通りを少なくしてしまった大きな要因として
否定できないようです。
その“上魚町”が「金座町(きんざまち)」と改称したのは
1928(S3)年11月10日のことです。
これは言うまでもなく
駿河小判をつくった金座がここにあったことにちなむものです。
家康の側近であった
後藤庄三郎光次(京都の御用調金師の後藤宗家の女婿)という人が
大御所となった家康とともに駿府へ来て
ここに3000坪近い屋敷を得
江戸と駿府の二元体制である大御所政治が終わるまで
ここで金座を統括したということです。
場所は現在の日銀静岡支店の敷地を含む
通りの南側(静岡駅方面を背にして左手)のようです。
その金座も大御所政治の終えんにより
江戸(現・本石町一丁目の日銀本店のあるところ)へ移されました。
なお、銀座は旧両替町二丁目にありました。
銀座跡の碑についてはこちらの「両替町二丁目」をご覧ください。
昭和の時代になると その繁華性をしだいに失ったのは
1889(M22)年の鉄道の開業により
静岡市の町の重心が徐々に静岡駅方面に移っていったことが大きいのでしょう。
また、中心地点であるがゆえに
この地域(上魚町・旧呉服町一丁目、旧呉服町二丁目)に
銀行(安倍銀行・三十五銀行・静岡銀行など)や会社が進出し
商店街が虫食い状態のようになってしまったことも
人通りを少なくしてしまった大きな要因として
否定できないようです。
その“上魚町”が「金座町(きんざまち)」と改称したのは
1928(S3)年11月10日のことです。
これは言うまでもなく
駿河小判をつくった金座がここにあったことにちなむものです。
家康の側近であった
後藤庄三郎光次(京都の御用調金師の後藤宗家の女婿)という人が
大御所となった家康とともに駿府へ来て
ここに3000坪近い屋敷を得
江戸と駿府の二元体制である大御所政治が終わるまで
ここで金座を統括したということです。
場所は現在の日銀静岡支店の敷地を含む
通りの南側(静岡駅方面を背にして左手)のようです。
その金座も大御所政治の終えんにより
江戸(現・本石町一丁目の日銀本店のあるところ)へ移されました。
なお、銀座は旧両替町二丁目にありました。
銀座跡の碑についてはこちらの「両替町二丁目」をご覧ください。
▽ 街路樹に埋もれるように佇む金座跡の碑(1955年設置)
昔見た記憶では、もっと立派な碑だったような記憶があるのだが・・・(笑)
(他都市ならもっと誇らしげにきちんとした掲示板など設けるところだろう。)
なお、このちょいと先(安西寄り)に静岡市内線の「金座町電停」があった。
子どものころ「金座町」の町名もこの電車で覚えたのだった。
↑ 静岡県情報の人気ランキング
▽ 呉服町側から上魚町(現金座町)方面をのぞむ
左が日本銀行静岡支店、右が清水銀行静岡支店
右の角(現駐車場)にあった創業百十数年という奈良屋文具店(所在地としては中町)は昨年閉店してしまった。
▽ 小川龍彦著「続 思い出のしずおか」からの碑
(静岡駅方向を描いていると思われる。)
大正時代に静岡で初めて車道と歩道の区分のある道路となった記述がある。
上魚町は、現在の金座町(きんざまち)のことで
別称 「上之店(かみんたな)」 とも言われるとおり
商家が立ち並ぶにぎやかな町だったようです。
江戸期から明治・大正ごろまでは
静岡で商家が立ち並ぶ最も繁華な通りは
この上魚町から呉服町一丁目・二丁目・三丁目(現在の呉服町一丁目)、札の辻あたりまでで
呉服町も四丁目・五丁目・六丁目(現在の呉服町二丁目)と
現在の静岡駅方向に進むにつれ
しだいにその繁華性は尻すぼみのような状態であったということです。
(上魚町と呉服町一丁目の間には本通があるが、
昔の本通は数間程度での幅員で新通などより狭い道だったようです。)
つまり、通り沿いの繁華性の程度が現在とは全く逆進行だったわけです。
(七間町も繁華な通りだったのでしょうが
性格的には盛り場という言葉が似合う娯楽や飲食の街だったようです。)
上魚町が栄えた理由は
徒歩による交通が当たり前だった時代には
市中からはもちろん
安倍街道筋、藁科街道筋、麻機街道筋からも人が集まりやすい
地の利を得ていたということだったのでしょう。
こちらへつづく
▽もともとの上魚町は土手通りから呉服町一丁目交差点までの両側町だった。
↑ 静岡県情報の人気ランキング