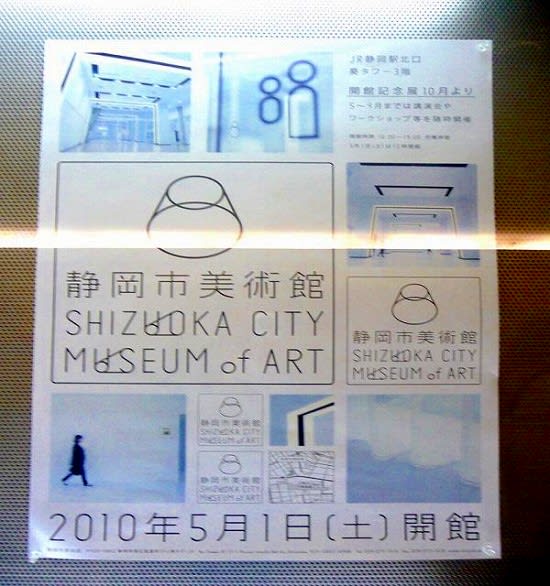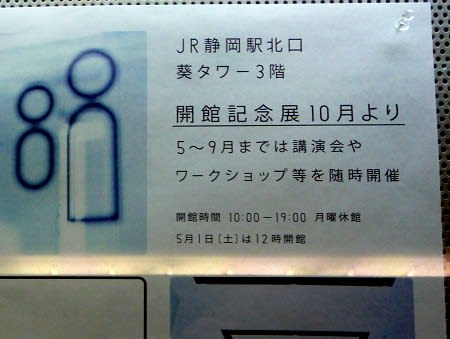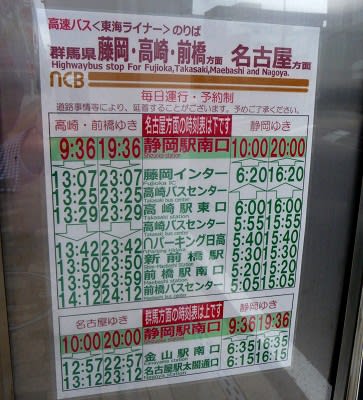▽ 四足御門跡


四足町の町名の由来である四足御門跡です。
門はこの正面ではなく(正面には石垣があった)
左手に、名前のとおり四足の御門が東向きに建っていたということです。
(つまりクランク型に進路をとることになる。)
このあたりは明治期から堀が埋められてしまって
写真右手の石垣手前のお堀だったところにはビルが建っています。
まあ、左手の新中町ビルから市立静岡病院玄関あたりは石垣も撤去されてしまっているので 石垣の一部だけでも残されたのを
よしとするしかないでしょう。
なお、駿府城への登城口は、追手門(県庁東側)のほか
横内御門(北街道、市民文化会館入口)、草深御門(東草深町、草深橋)と
この四足御門の4箇所だったということです。
また、このあたりには今川氏の居館があったということですが
詳しいことは分かっていないようです。
▽ 本 通 (安倍川方向を臨む)

本通(ほんとおり)の起点でもある中町(なかちょう)交差点から
安倍川方向を見たところです。
本通は現在でこそ幅員30mの幹線道路ですが
江戸期には東海道であった新通(しんとおり)よりも狭かったようです。
かつて走っていた静岡鉄道の市内電車の
鷹匠町(たかじょうまち) ~ 中町(新中町ビル前附近)は1925(T14)年開通
呉服町(静銀本店のある呉服町一丁目交差点) ~ 安西(安西二丁目交差点)は
1926(S1)年の開通でした。
途中の中町(停)と呉服町(停)の本通を走る区間(約100m)が開通したのは
1929(S4)年のことでした。
この区間をどうしていたかというと徒歩連絡していたのでした。
どうしてわずか100mの区間の開通が遅れたかというと
本通があまりに狭く線路を敷くことができなかったということです。
おそらく5mほどしか幅がなかったのではないのでしょう。(もちろん歩道などない)
なお、本通や昭和通が拡幅されたのは昭和始めです。
▽ 静岡天満宮

中町といえば静岡天満宮を思い浮かべる人も多いかもしれません。
本通沿いの左手(安倍川方向を見て)の中町の町域には
この天満宮のほか、岩市(いわいち)そば店、農林中金静岡支店があったのですが 数年前撤退し、 現在は静岡赤十字病院の拡張用地として空き地となっています。
また、静岡天満宮も土地の一部が呉服町一丁目にまたがっているためか
所在地表記に呉服町一丁目を名乗っていますので
本通の左手には土地の表記としては中町が存在しても
実質的に中町がなくなってしまっています。
▽ 飯田旗店

中町といえば天満宮と並んで
昔からこの飯田旗店があり変わらぬ佇まいがなつかしいです。
(もちろん大火や空襲を受けている地域ですので戦後の建物でしょうが)
この旗屋さんは創業100年を超え
旗やトロフィーなどのほか、最近は、くす玉の販売に力を入れているようです。
また、日の丸と同じ素材で作られた男を上げる“ふんどし”もあつかっているとか・・・
この前を通りかかったらのぞいてみるのも楽しいかもしれません。
↑ 静岡県情報の人気ランキング