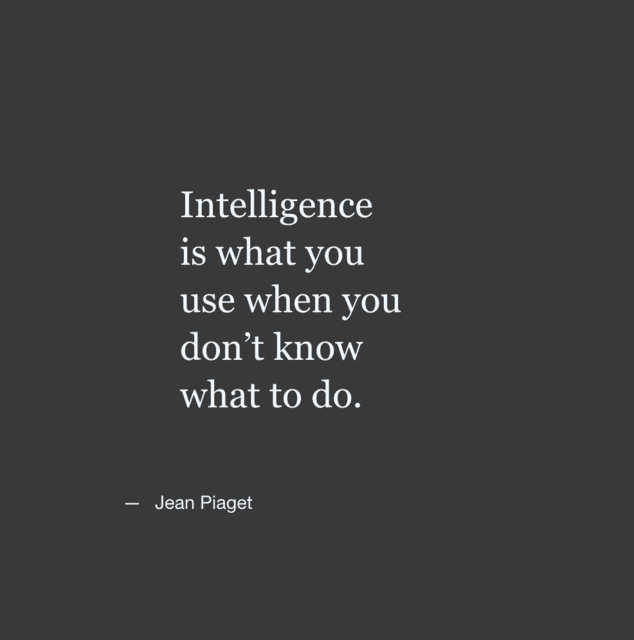(bodhisattva/11th–12th century; wood, gesso, and pigment with gilding; Saint Louis Art Museum)
たとえば、「わたし」への関心は、自分らしさや個性を強調し、それを価値とする方向にも向かいます。資本主義のシステムは、そのような価値を探り出しては消費していくことで成長しますので、両者は実に親和的です。自分の個性や価値が商品化されていくのです。自分の事を伝えるセルフ・プレゼンテーションを考えてみましょう。自分の事を他人に上手に伝えるのは大事な能力ではありますが、それは多くの場合、何かの商品と同様に、自分の個性や価値を売っているように思われます。時には無理をしてでも、「自分はこんなにユニークな人である」と言わなければなりません。ただし、それは差異をつくり出し、差異を消費する資本主義の論理を人間に適用したものです。はたして、それはどこまで許容できるのでしょうか。
可能性の次元というのは、計算可能な次元ということです。モノにせよコトにせよ偶発性に乏しく、計算可能な次元で展開していきます。ここでは、人間も計算可能な「価値」として測られます。それに対して、私たちには可欲性という次元もあります。可欲性とは耳慣れない言葉でしょうが、何を欲するのか、何を望むのかが問われる次元です。資本主義は人間の欲望をかき立てます。私たちはしばしば、他人の欲望を欲することでモノやコトを消費しますが、本当は何を欲しているのでしょうか。何を望んでいるのでしょうか。
所有からも差異からも離れたところで、何を欲するのか。それは計算可能なものではありません。計算を超えたもの、可能性とは異なるものであり、何か根底的に偶然な出来事の到来を歓待することではないでしょうか。それはおそらく「わたし」というより「わたしたち」が出会う複数性の次元であるはずです。「わたし」がコントロールできるようなパッケージ化されたものではありません。ここでは、「わたし」は根底的に無力であることでしょうが、同時に極めて豊かな経験にさらされるのです。
こうした方向に資本主義がどう寄与するのか。それは、みずからの原理である計算可能性の次元に、別の次元を受け入れるようなスペース開けることによってだろうと思います。スペースをモノやコトによって埋め尽くすのではなく、出来事が生じるのを待つのです。
現在は貨幣が富の象徴だと考えられているのかもしれませんが、貨幣は単なる記号です。アダム・スミスが「国富論」で論じたのは、貨幣は富ではなく、労働が生み出すものが富だということでした。労働という新しい概念で富を理解し直そうとしたのですね。いまや労働に代えて富を再定義しなければなりませんが、いずれにしても富は貨幣ではないわけです。貨幣をどれだけ蓄えようが、或いは資本として回転させようが、それ自体が富だというわけには、ただちにはなりません。そうではなく、貨幣や労働を通じて可能になる社会的な条件の先に、人間にとっての豊かな富があるはずです。
ハンナ・アーレントは、人間に必要なのは労働ではなく活動だと言っています。アーレントの言う活動とは言葉を交換すること、より詳細には、ある種の公共的な空間で言葉を交換することです。自分が伝えたいことを持つためには、パッケージ化されたコトを追いかけても仕方ありません。また、言葉にするための技術は意味を持つでしょうが、プレゼンの能力を高めるだけではこれまた仕方ありません。伝えたいことがないのに、伝えるスキルばかりを磨けと言われても困りますよね。大事なことは何を伝えたいか、です。まさに何を欲するのかをギリギリと考えて、それを言葉にすることが重要なのです。
そのためには、「わたし」の内面に訴えるアプローチよりも、他人とのつながりの中でともに生きつつ、共同の経験を豊かにするアプローチのほうが有効だと思います。何も自分らしさや個性といった形で、無理やり差異をつくり出す必要などありません。それよりも「わたし」などというものを突き放して、可能性の次元を超えて、想像力を思い切り羽ばたかせたほうがずっとよいとおもいます。豊かさとは、こうした想像力が開くのですから。
近年広く共有されてきたマインドフルネスやセルフ・コンパッションという概念は、要するに自分をそこまで厳しく審問する必要はないのではないかという提案です。そして、その背景には、西洋近代哲学が問うてきた「わたし」という問いへの違和感があると思います。そもそも、真面目に「自分とは何か」などと問うことがおかしいのではないのか。どうしても問うのであれば「そんなものはわかりません」と答えておけばよいのではないか。そんな提案ではないでしょうか。
-切抜/中島隆博‘あなたを苦しめる「わたし」の正体’より
たとえば、「わたし」への関心は、自分らしさや個性を強調し、それを価値とする方向にも向かいます。資本主義のシステムは、そのような価値を探り出しては消費していくことで成長しますので、両者は実に親和的です。自分の個性や価値が商品化されていくのです。自分の事を伝えるセルフ・プレゼンテーションを考えてみましょう。自分の事を他人に上手に伝えるのは大事な能力ではありますが、それは多くの場合、何かの商品と同様に、自分の個性や価値を売っているように思われます。時には無理をしてでも、「自分はこんなにユニークな人である」と言わなければなりません。ただし、それは差異をつくり出し、差異を消費する資本主義の論理を人間に適用したものです。はたして、それはどこまで許容できるのでしょうか。
可能性の次元というのは、計算可能な次元ということです。モノにせよコトにせよ偶発性に乏しく、計算可能な次元で展開していきます。ここでは、人間も計算可能な「価値」として測られます。それに対して、私たちには可欲性という次元もあります。可欲性とは耳慣れない言葉でしょうが、何を欲するのか、何を望むのかが問われる次元です。資本主義は人間の欲望をかき立てます。私たちはしばしば、他人の欲望を欲することでモノやコトを消費しますが、本当は何を欲しているのでしょうか。何を望んでいるのでしょうか。
所有からも差異からも離れたところで、何を欲するのか。それは計算可能なものではありません。計算を超えたもの、可能性とは異なるものであり、何か根底的に偶然な出来事の到来を歓待することではないでしょうか。それはおそらく「わたし」というより「わたしたち」が出会う複数性の次元であるはずです。「わたし」がコントロールできるようなパッケージ化されたものではありません。ここでは、「わたし」は根底的に無力であることでしょうが、同時に極めて豊かな経験にさらされるのです。
こうした方向に資本主義がどう寄与するのか。それは、みずからの原理である計算可能性の次元に、別の次元を受け入れるようなスペース開けることによってだろうと思います。スペースをモノやコトによって埋め尽くすのではなく、出来事が生じるのを待つのです。
現在は貨幣が富の象徴だと考えられているのかもしれませんが、貨幣は単なる記号です。アダム・スミスが「国富論」で論じたのは、貨幣は富ではなく、労働が生み出すものが富だということでした。労働という新しい概念で富を理解し直そうとしたのですね。いまや労働に代えて富を再定義しなければなりませんが、いずれにしても富は貨幣ではないわけです。貨幣をどれだけ蓄えようが、或いは資本として回転させようが、それ自体が富だというわけには、ただちにはなりません。そうではなく、貨幣や労働を通じて可能になる社会的な条件の先に、人間にとっての豊かな富があるはずです。
ハンナ・アーレントは、人間に必要なのは労働ではなく活動だと言っています。アーレントの言う活動とは言葉を交換すること、より詳細には、ある種の公共的な空間で言葉を交換することです。自分が伝えたいことを持つためには、パッケージ化されたコトを追いかけても仕方ありません。また、言葉にするための技術は意味を持つでしょうが、プレゼンの能力を高めるだけではこれまた仕方ありません。伝えたいことがないのに、伝えるスキルばかりを磨けと言われても困りますよね。大事なことは何を伝えたいか、です。まさに何を欲するのかをギリギリと考えて、それを言葉にすることが重要なのです。
そのためには、「わたし」の内面に訴えるアプローチよりも、他人とのつながりの中でともに生きつつ、共同の経験を豊かにするアプローチのほうが有効だと思います。何も自分らしさや個性といった形で、無理やり差異をつくり出す必要などありません。それよりも「わたし」などというものを突き放して、可能性の次元を超えて、想像力を思い切り羽ばたかせたほうがずっとよいとおもいます。豊かさとは、こうした想像力が開くのですから。
近年広く共有されてきたマインドフルネスやセルフ・コンパッションという概念は、要するに自分をそこまで厳しく審問する必要はないのではないかという提案です。そして、その背景には、西洋近代哲学が問うてきた「わたし」という問いへの違和感があると思います。そもそも、真面目に「自分とは何か」などと問うことがおかしいのではないのか。どうしても問うのであれば「そんなものはわかりません」と答えておけばよいのではないか。そんな提案ではないでしょうか。
-切抜/中島隆博‘あなたを苦しめる「わたし」の正体’より